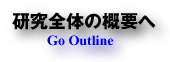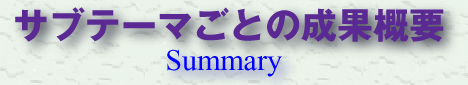
検索画面に戻る Go Research
[B−9 太平洋域の人為起源二酸化炭素の海洋吸収量解明に関する研究]
(1)太平洋の海洋表層二酸化炭素データ解析による二酸化炭素吸収放出の解明に関する研究
独立行政法人国立環境研究所
|
|
地球温暖化研究プロジェクト
炭素循環研究チーム
|
野尻幸宏・荒巻能史・渡辺幸一
|
同
|
藤井賢彦(日本学術振興会特別研究員)
|
同
|
M.Chierici(EFフェロー)
|
同
|
A.Fransson(日本学術振興会外国人特別研究員)
|
[平成13〜17年度合計予算額]
平成l5〜17年度合計予算額 69,519千円
(うち、平成17年度予算額 20,513千円)
※上記の予算額には、間接経費 16,051千円 を含む)
[要旨]
国立環境研究所による北太平洋横断定期航路の表層海洋CO2観測データを利用して、北太平洋中高緯度海域のCO2吸収の制御要因に関する解析研究を行った。最も密な観測データがある2000年前後に注目し、水温変化、生物過程、ガス交換過程を分別した。CO2分圧制御要因としては、どの海域区でも水温と生物効果が大きく、ガス交換効果は小さかった。西部亜寒帯循環海域と東部のアラスカ循環域のCO2分圧年間振幅はそれぞれ100μatmと45μatmであり、ほぼ2倍の差がある。その制御要因には、西部で生物過程項がより卓越し、東部で水温変化項がより卓越するという相違があった。生物効果による月あたりCO2分圧低下は西部亜寒帯循環域では7月に95μatmの最大値を示し、アラスカ循環域の月あたり低下最大値のほぼ2倍であった。また、北太平洋中高緯度域のCO2吸収における年々変動の解析研究を行った。季節を完全にカバーする観測がある緯度・経度グリッドを抽出して、各年平均△pCO2値と6年間平年値の比較を行い、平年値からの偏差偏差マップを作成した。平年値からの最大偏差は29μatmであり、△pCO2の季節変動と比較して小さな偏差であった。海盆全体を平均すると、西部亜寒帯太平洋においては、この6年間の年々変動は小さく、東部亜寒帯太平洋では15μatmほどの変動幅で年々変動があったことがわかった。さらに、1995年から2001年にかけての継続的なデータが存在するベーリング海南部におけるCO2分圧と大気‐海洋間フラックスの詳細な年々変動解析を行った。期間中に海洋表層CO2分圧は大気CO2濃度増大以上の増加傾向を示した。この海域は通年フラックスではCO2放出海域であるが、観測期間前半の1998年以前はCO2放出がゼロに近かったのに対し、2000年には大きな放出源(4mol m-2 yr-1)になった。これは、海洋表層CO2の年々変動の結果であり、特に1997年には大きな生物生産に伴う海洋表層CO2分圧の低下が起こりCO2放出量は最小となった。これらは、赤道太平洋海域以外では、海洋表層CO2分圧の年々変動を観測から明らかにした初めての解析である。
[キーワード]
海洋表層二酸化炭素分圧、貨物船観測、季節変動、海域分布、北太平洋
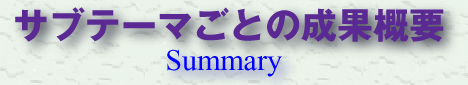
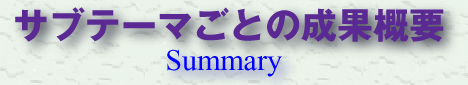
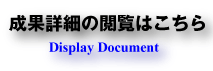 (3.73MB)
(3.73MB)