

|
|
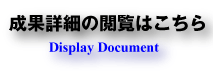 (2.0MB) (2.0MB)
|
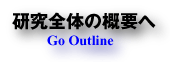
|
東京大学海洋研究所 |
|
津田 敦 |
独立行政法人水産総合研究センター北海道区水産研究所 |
||
亜寒帯海洋環境部 |
生物環境研究室 |
小埜恒夫 |
京都大学化学研究所 |
|
宗林由樹 |
平成13〜15年度合計予算額 58,596千円
(うち、平成15年度予算額 17,708千円)
2001年6月28―8月6日に水産庁調査船開洋丸を用いて、鉄濃度調節および生物の応答調査
を西部亜寒帯太平洋において行った(実験名SEEDS)。さらに2002年7―8月にカナダSOLASグルー
プとの共同研究により東部亜寒帯太平洋において実施し、3船でSEEDSの2倍の観測期間となる計26
日間の観測を実施した(実験名SERIES)。日本側は水産庁調査船開洋丸を用いて散布から15―26
日目を観測した。SERIESにおいて改善された探査サーベイ能力は開洋丸観測期間中、一日だけ、
衛星により鉄濃度調節域が観測され実証された。2002年実験では、2001年実験とは異なり、植物
プランクトンブルームのピークは2週間後に観察され、我々の観測終了時には植物プランクトン
濃度はピーク時の1/4以下になった。すなわち高緯度域鉄濃度調節実験では初めてブルームの消滅
期を観測したといえる。2回の実験を通して以下8項目の主な成果を得た。1)外洋域における鉄
濃度調整技術を確立した。2)SF6の連続測定技術、これを用いた水塊追跡技術を確立した。3)
外洋域における鉄濃度調整に対する生物応答観測法を確立した。4)動物プランクトンの植物に
対する摂餌速度は4―15倍に上昇し、増えた珪藻を摂餌し、生残率、成長速度が高くなること
が明らかになった。5)鉄濃度調整実験で初めて微量金属の変動が測定され、その動態が明らか
になった。6)国際的協力体制のもと鉄濃度調節実験を行い、長期(26日間)の観測を実現し
た。7)東部・西部亜寒帯太平洋における鉄濃度調節に対する生物化学的応答の差が明らかとなった。
8)東部では珪藻の応答が西部に比べ遅く、珪藻増殖前に円石藻が増殖しDMSの放出を観測した。
二酸化炭素、海洋鉄濃度調節、観測技術、微量金属、生物応答