

|
|
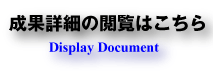 (1.4Mb)
(1.4Mb)
|
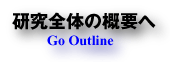
|
独立行政法人農業環境技術研究所 地球環境部 食料生産予測チーム |
谷山一郎 |
豊橋技術科学大学工学部 |
後藤尚弘 |
平成12〜14年度合計予算額 8,821千円
(うち、平成14年度予算額 2,812千円)
これまでの気候変動枠組み条約締約国会議のなかで、農耕地からの温室効果ガスの排出抑制や吸収拡大が議論されてきた。本研究では吸収源対策(アクティビティ)が農耕地土壌における温室効果ガス交換へ及ぼす影響について既存の数理モデルを用いて推計し、日本、アメリカおよびEUなどでどのような違いがあり、それらの国と地域が農耕地の温室効果ガス吸収能に対してどのような戦略をとることが予測されるかを検討した。数理モデルにはローザムステッドモデルとIPCCのモデルを用いた。結果によると、二酸化炭素に関して最も有効であったのは農作物残渣の土壌還元量を増大するアクティビティであった。ただし、アクティビティによる土壌炭素増加量は農耕地の面積に大きく依存する。また、肥料投入による亜酸化窒素の発生は二酸化炭素の固定に比べて小さいことがわかった。目標削減量に占める各アクティビティ実施による削減量の割合は、必ずしも土壌炭素増加量に比例しない。また、亜酸化窒素の排出に関しては、農業、畜産業に対して、窒素施肥管理の改善と家畜糞尿処理施設の改良と増設の二つの亜酸化窒素削減対策を行った。窒素施肥管理の改善では日本がアメリカおよびEUに比べて有効であった。また、家畜糞尿処理施設の改良と増設についての対策を行った場合はアメリカおよびEUにとって有効であった。これらの結果から、削減策の効果は、各国や地域における農業の特性および土壌種、気候、作物種によって違ってくることがわかった。しかし、アクティビティによる削減分を計上する上で最も有利となるのは広大な農耕地面積を持つ国といえる。
農耕地、二酸化炭素、亜酸化窒素、数理モデル、京都議定書