

|
|
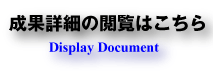 (1010Kb)
(1010Kb)
|
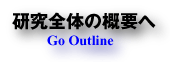
|
岩手医科大学 |
サイクロトロンセンター |
世良耕一郎 |
国立水俣病総合研究センター |
赤木洋勝・松山明人 |
|
独立行政法人 |
産業技術総合研究所 |
地圏資源環境研究部門 村尾智 |
東京外国語大学 |
外国語学部 |
山本真司・温品廉三 |
慶應義塾大学 |
商学部 |
吉川肇子 |
〈研究協力者〉 |
早稲田大学 |
文学部 竹村和久 |
フィリピン |
University of the Philippines, Maglambayan Victor |
|
フィリピン |
University of the Philippines, Clemente Elegia |
|
フィリピン |
Mines and Geosciences Bureau-CAR, De la Cruz Neoman, |
|
イギリス |
Bugnosen Minerals Engineering, Bugnosen Edmund |
|
モンゴル |
BEMM Co., Ltd. Tumenbayar Baatar |
|
タンザニア |
University of Dar es Salaam, Justinian R., Ikingura |
|
平成12〜14年度合計予算額 28,677千円
(うち、平成14年度予算額 18,643千円)
本サブテーマは、ゴールドラッシュ地域における水銀汚染について、実態を明らかにするとともに、その理解の上に、今後の環境管理計画に必要な地域との協働について考察することを目的としている。研究では、まず、初年度と次年度にゴールドラッシュに伴う水銀汚染の特徴を抽出するため、フィリピン、モンゴル、タンザニアの金鉱採掘地帯で得られた環境試料を分析した。また、試料として毛髪が多数得られたため、その簡易分析法として知られる岩手医大のPIXE装置が総水銀測定に対して有効か否かを検証した。フィリピンとモンゴルでは鉱夫の毛髪を、タンザニアでは選鉱かす、河川の底質、魚類、地衣類を分析した。こうしてゴールドラッシュに伴う水銀汚染の特徴を明らかにした後、最終年度に金鉱のスモールスケールマイニングに対する一般住民の意識を分析した。また、鉱業と環境に関する円卓会議を開催し、鉱業界が現時点で行っているベストプラクティスの実態を明らかにするとともに今後のリスクコミュニケーションの可能性を検討した。
PIXE法は毛髪中の総水銀値を測定する方法として極めて簡便であった。試料の調製や標準試料の測定が不要なため短時間で測定が可能であり、数ppm程度の総水銀を定量できることがわかった。また、ビーム照射による水銀の信号の減少はみられなかった。
フィリピンとモンゴルの鉱夫の毛髪分析からは総水銀濃度が高いものから低いものまで広い範囲(0-305ppm)にわたることが判明した。タンザニアの選鉱かすには乾重量あたり200ppmをこえる総水銀が含まれ、メチル水銀も0.6ppm含まれるが、メチル水銀の水への溶解性は極めて低かった。魚類の分析では肉食魚の水銀含有量が比較的高いが全体としてはそれほど高い値は得られなかった。地衣類の分析では2種類の地衣類が水銀による大気汚染の指標になる可能性を見出した。
地域住民の意識調査ではリスク認知の高いものは2種類に分類できると考えられる。それらは、テロや、核兵器、原子力発電所のように大規模なものと、地滑りや水銀という身近に存在するものである。スモールスケールマイニングによる水銀汚染に対する対策としては、政府や開発会社による介入が相対的には有効と判断されていた。特に教育や啓蒙活動が有効な方策と見なされていた。大規模開発とスモールスケールマイニングを比較すると、スモールスケールマイニングの方がハザードに対する寄与が多くの項目で低いと評定された。すなわち、スモールスケールマイニングの方がおおむね安全、あるいは環境に負荷がより少ないと見なされていた。スモールスケールマイニングに対して地域住民は寛容であるように見える。
円卓会議においては、水銀汚染防止キャンペーンを公的機関が実施する際の留意点を、アマゾンの体験をもとにまとめた。
スモールスケールマイニング、水銀汚染、環境管理、リスク認知、リスクコミュ