

|
|
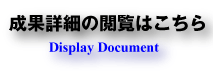 (1.5Mb)
(1.5Mb)
|
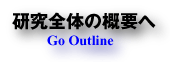
|
独立行政法人産業技術総合研究所 |
||
ライフサイクルアセスメント研究センター |
副センター長 |
匂坂 正幸 |
地域環境研究チーム長 |
八木田 浩史 |
|
地域環境研究チーム |
玄地 裕 |
|
平成12〜14年度合計予算額 13,402千円
(うち、平成14年度予算額 3,994千円)
未利用エネルギーの導入促進を図るためには、省エネルギー、CO2排出量削減等の技術的な側面だけでなく、それに伴うコストの評価が不可欠であり、導入によるコスト上昇が大きい場合には何らかの経済的誘導施策が必要である。本研究では、未利用エネルギーの導入に際して経済的誘導施策がなされた場合に、その効果を省エネルギー及びCO2削減に対する費用対効果のかたちで明らかにするため、都市におけるエネルギー需給構造モデルを構築した。モデル中に、補助金、炭素税等の経済的誘導施策を金額の形で入れることによってその効果を推定することができる。
従来の都市熱供給システムに、下水熱、ごみ焼却熱等の未利用エネルギーを導入した際のエネルギー需給構造に関して、建物構成の異なる10地域を特定し需給構造最適化のスタディを行った。その結果、事務所の割合がほとんどを占める地域では、ごみ焼却熱による熱供給の導入がCO2削減に有効であることが明らかになった。一方、住宅が大部分を占める地域では、熱供給配管敷設費用が大きいため未利用熱の導入がなされないことが明らかになった。
未利用排熱を活用するガスタービンコジェネレーションを適用したときの評価を行った。実際の建屋(産業技術総合研究所つくば西事業所)を対象として最適化モデルによる導入効果の評価を行い、発電効率30%の再生サイクルガスタービンを導入したとき、従来と同等のコストでCO2排出量を7.5%削減できること、発電効率20%のシングルサイクルガスタービンを導入したとき、従来システムよりCO2排出量は増加するもののコストは6.1%削減できることが明らかになった。
さらに、マイクロガスタービンコジェネレーションを導入する場合について、従来型の系統電力と吸収冷温水機による供給システムとの評価をおこなった結果、複数の種類の建屋間で熱の融通を図ることによって、従来システムのおよそ12%の省エネルギーになること、ESCO事業としての補助金対象にすべきことを明らかにした。
都市、需給構造、下水熱、ごみ焼却熱、最適化モデル