

|
|
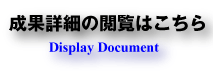 (2.3Mb) (2.3Mb)
|
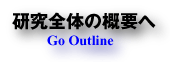
|
独立行政法人国立環境研究所 |
|
社会環境システム研究領域 環境計画研究室 |
原沢英夫・高橋潔 |
熊本大学法学部* |
有吉範敏 |
慶應義塾大学大学院政策メディア研究科** |
西岡秀三 |
*:平成ll年度のみ参画、**:平成12年度のみ参画 |
|
(研究協力機関) |
|
京都大学大学院工学系研究科 |
松岡 譲 |
平成11〜13年度合計予算額 33,374千円
(うち、平成13年度予算額 10,639千円)
人口増加、工業化、灌漑面積の増加といった様々な原因により、水資源不足は世界各地において深刻な問題となりつつある。本研究では、気候変化を考慮した中長期の水需要と利用可能な水資源量の予測を行ない、渇水リスクの高い地域や気候変化に対して脆弱な地域を抽出する方法を検討した。その方法を2050年〜2059年の9年間を対象として適用し、水需要と利用可能な水資源量の比(需給比率)を推計し、水資源の逼迫度を流域ごとに評価した。その結果、中国のアムール川・長江では人口増加と工業化を反映した水需要増加傾向のため水資源が現状より逼迫する、ガンジス川流域では急激な水需要増加が見込まれるが同時に気候変動による流出量の増加も見込まれるため需給比率で見た水資源の逼迫度としてはあまり変化しない、ミシシッピ川流域やナイル川流域においては流出量の年々変動が現状よりも大きくなる、といった流域ごとの水資源逼迫度の定性的な将来見通しを示すことができた。
さらに、需要推計モデルを改良し、2030年までを対象期間として、アジア太平洋地域各国のより詳細な水需要推計を行った。将来の水需要の決定因子として、工業部門についてはGDP、農業部門については灌漑面積、家庭部門については給水人口を用いた。決定因子の将来変化については、過去の実績値をもとにした回帰によって設定した。国連環境計画の「第3回地球環境見通し」で検討された「現状傾向発展型」、「政策改革型」、「地域孤立型」、「大変革型」の4つの社会経済発展パターンについて推計を行ったところ、3部門計の水消費量で比較した場合、どの地域においても地域孤立型が最も需要の伸びが大きいと見積もられた。部門別に見ると、工業部門については現状傾向発展型の水消費量がもっとも大きく、農業部門については急激な人口増加と遅い技術進歩速度を反映して地域孤立型の水消費量がもっとも大きい。
アジア地域、水資源、水需要、水不足、シナリオ分析