

|
|
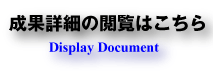 (510Kb) (510Kb)
|
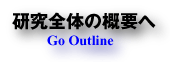
|
富山国際大学地域学部 |
安藤 満 |
独立行政法人国立環境研究所 |
|
環境健康研究領域生体防御研究室 |
山元昭二・藤巻秀和 |
大阪大学医学部保健学科 |
彼末一之・大野ゆう子・雑賀公美子・ |
京都女子大学 |
中井誠一 |
産業医科大学産業生態科学研究所 |
高橋謙・實珠山務 |
松本歯科大学 |
川原一祐 |
山梨県環境科学研究所所長 |
入來正躬 |
日本農村医学研究所 |
清水茂文・浅沼信冶 |
海外研究協力機関 |
中国環境衛生・衛生工程研究所・ |
平成11〜13年度合計予算額 34,792千円
(うち、平成13年度予算額 9,122千円)
近年世界各地において夏季の異常高温が頻繁に報告されているが、日本においても夏季の記録的高温が報告されている。IPCCの最新報告(2001)によると、今後一層の気温上昇が予測されており、都市域のヒートアイランド現象の増強と併せ、夏季の熱ストレスによる健康影響が重要課題と考えられる。ヒトは一般に気温変化に対する馴化による適応能を保持しているが、気温が順応可能な閾値温度を超えて上昇したときには、健康に対するリスクが増加する。健康のリスクを把握するため、疫学調査と気象データを収集し、気温と健康影響の相互関係について検討した。
代表的熱ストレス疾患である熱中症は毎年全国的に発症し死亡例も多数見られるため、熱中症発症のリスクに関してヒトの適応能を予測するため、地域による変化を比較検討した。日本の調査対象地域は熱中症のリスクの高い亜熱帯域の沖縄県、温帯域の福岡県、神戸市、山梨県と東京都を選定し、中国においては熱中症の発生の顕著な南部の武漢市を選定し、地域住民の熱中症発症と地域の気象条件との関連を解析し、閾値温度を相互比較し適応能について検討した。
熱中症関連疾患で救急搬送患者症例のデータを収集し解析した結果、日本においては熱中症の一発生動向は類似し、地域差は比較的少ないことを伺わせていた。熱中症は男性のリスクが女性に比べ著しく高い特徴がある。男性においては、15歳以上65才未満の年齢層は65歳以上の高齢者と変わらない高い熱中症のリスクを示す。女性においては、65歳以上の高齢者のリスクは同世代の男性に類似したリスクを示す。その一方、15歳以上の65才未満の年齢層においては、男性に比べ女性のリスクが著しく低く、行動的・生理的適応現象が現れていると考えられる。
熱中症の急増する気温には明確な地域差が観られず、日本においては地域による住民の閾値気温に関する適応は少ないことを伺わせる。母集団の多い東京都において1980年から1995年の16年間(リスク人口:1億9千万人)の救急搬送の熱中症患者データを解析した結果、日最高気温が30℃を超える真夏日は、熱中症発生の閾値温度を超えるため、「熱中症注意報」が必要な日と予想される。さらに日最高気温が35℃を超える酷暑日は、熱中症発生が急増する状態のため、「熱中症警報」が必要な日と予想される。今後温暖化の進行に備え、熱中症発症のリスクの低減化に向けた猛暑の直近における熱中症予報や警報が必要と考えられる。日本においては、30℃を超える日最高気温は熱中症発生の閾値温度と予想されるため、リスク低減化のため猛暑の直近における熱中症予報や警報が必要と考えられる。同時に学校教育や一般啓蒙により熱中症のリスクの低減化を図る必要がある。
一方中国武漢市においては、日本に比べ熱中症発生の閾値温度が2℃高く、日最高気温が32℃を超えると熱中症のリスクが上昇する。同じモンゴロイドに属する日本人と中国人ではあるが、馴化による生理的適応と行動学的適応により、夏季の気温に対する熱中症リスクの閾値気温には、明確な適応の違いが存在する。
将来温暖化の進行に際し、このような適応の差が日本でも生じる可能性があるかどうか非常に興味がある課題である。アジアの種々の社会集団に対して技術的適応策と並行して、馴化による生理的適応と行動学的適応を促進し住民の適応能を利用した温暖化対応策により、夏季気温の上昇に脆弱な地域社会を改善していく可能性の検討が必要と考えられる。このことは、熱ストレスの感染症への影響等さらに広範な健康影響を予防していく上からも重要と考えられる。
熱中症、熱ストレス、ヒートアイランド、健康影響、呼吸器疾患、