<参考> 地球温暖化防止のため、個人の日常生活においての取り組み
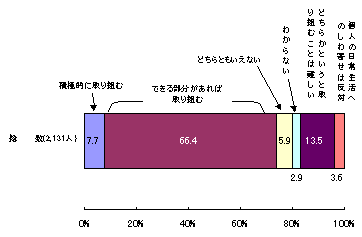 |
<参考> 地球温暖化防止のため、個人の日常生活においての取り組み
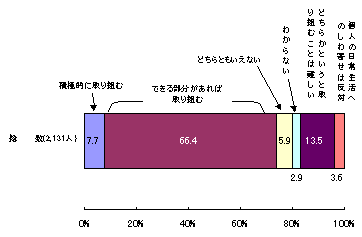 |
|
<参考> 「持続可能な開発」の概念は、国連の「環境と開発に関する世界委員会」(通称ブルントラント委員会)報告書(1987年)において打ち出されたものであり、「将来の世代の欲求を充たしつつ、現在の世代の欲求も満足させるような開発」と定義され、そこに含まれる鍵となる概念として、「何にも増して優先されるべき世界の貧しい人々にとって不可欠な必要物の概念」と「技術・社会的組織のあり方によって規定される、現在及び将来の世代の欲求を満たせるだけの環境の能力の限界についての概念」が示されている。 この概念は、その後の地球環境保全のための取組の重要な道しるべとなっている。 (訳:大来佐武郎監修「地球の未来を守るために」,1987,福武書店 より)
|
|
<参考> (宣言抜粋) 6 持続可能性を達成するために、多くの重要なセクター内で、及び消費と生産パターンの変化を含む急速で抜本的な行動とライフスタイルの変化の中において、取組の大掛かりな調整と統合が求められている。このために適切な教育とパブリック・アウェアネスが法律、経済及び技術とともに、持続可能性の柱の一つとして認識されるべきである。 10 持続可能性に向けた教育全体の再構築には、全ての国のあらゆるレベルの学校教育・学校外教育が含まれている。持続可能性という概念は、環境だけではなく、貧困、人口、健康、食糧の確保、民主主義、人権、平和をも包含するものである。最終的には、持続可能性は道徳的・倫理的規範であり、そこには尊重すべき文化的多様性や伝統的知識が内在している。 (訳:(財)地球環境戦略研究機関)
|
<参考> 市区町村におけるテーマ別の環境教育・環境学習実施状況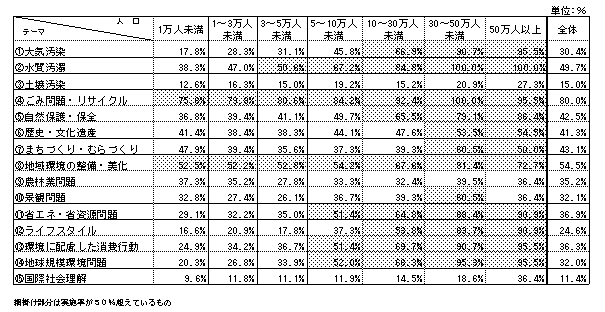 (環境教育の総合的推進に関する調査、環境庁、平成10年3月)
|
①総合的であること
今日の環境問題は、都市・生活型公害から地球環境問題に至るまで、極めて多岐にわたるが、これらは、エネルギー、食糧、人口問題を始め、現代のライフスタイルからそれを支える社会システムに至る様々な事項が、相互に関連しながら、多面的・複合的に、環境に影響を与えた結果生じている。また、環境の問題は、文化、歴史、さらには政治、経済、人間の精神的な面にも影響を与えるものである。 このような環境問題の特質を踏まえると、環境教育・環境学習においては、ものごとを相互連関的かつ多角的にとらえていく総合的な視点が欠かせない。②目的を明確にすること
環境教育・環境学習は、持続可能な社会の実現に向け、多様な場、多様な対象、多様な手法を通して総合的に行われるものであり、結果として持続可能な社会づくりへの学習者の主体的参加を促すものである。③体験を重視すること
環境教育・環境学習は、各人が学びの主体として環境問題にかかわり、主体的に持続可能な社会の実現に向けて具体的な行動に結びつける資質を育てるものである。④地域に根ざし、地域から広がるものであること
環境教育・環境学習は、生活の様々な局面で行われることが重要であり、その中心となるのは、日々の生活の場としての、多様性を持ったそれぞれの地域である。したがって、国が画一的なやり方を示すものではなく、地域や実践現場の自主性、主体性が尊重されるべきである。その際、地域の素材や人材、ネットワークなどの資源を掘り起こし、環境教育・環境学習に活用していくことが大切である。地域の伝統文化や歴史という観点を取り入れることも重要であり、そのような意味からも、先人の知恵を環境教育・環境学習に生かしていくことが望まれる。
<参考>
2 子どもたちの集まることのできる日時を調整することが難しい 3 サポーターが忙しくて活動に時間をかけられない 4 子どもたちの自主性・主体性を生かした活動を行うのが難しい 5 子どもたちの意欲・関心が低い 6 環境に関する情報が不足している 7 具体的な活動方法が分からない 8 クラブの活動について相談できる人が近くにいない 9 クラブの活動に対する子どもたちの親の参加・協力が得られない 10 クラブの活動を行う場所の確保が難しい 11 クラブの活動を行うのに金がかかる 12 子どもたちの安全確保に関する不安がある 13 その他 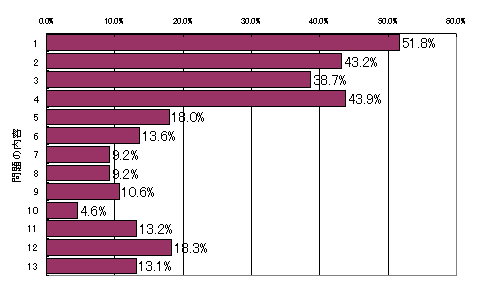 |
<参考>
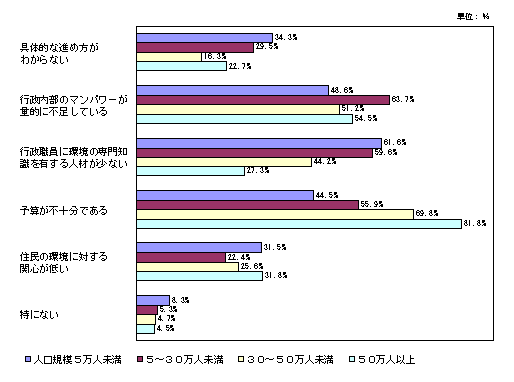
|
<参考>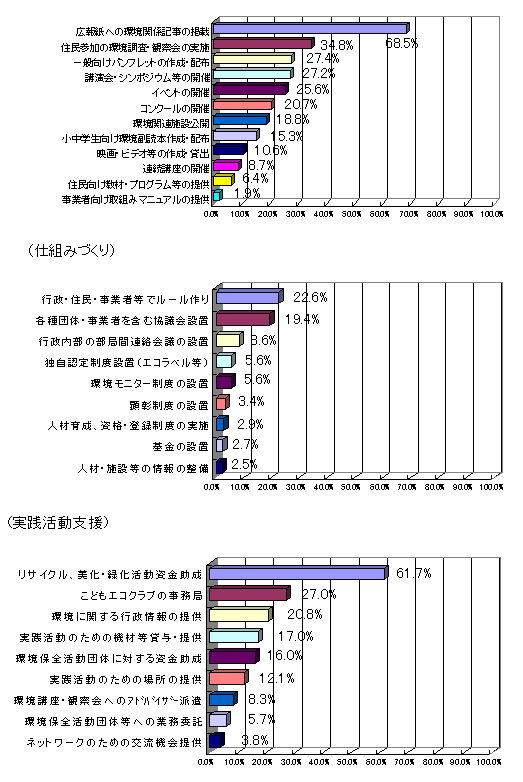
|
<参考>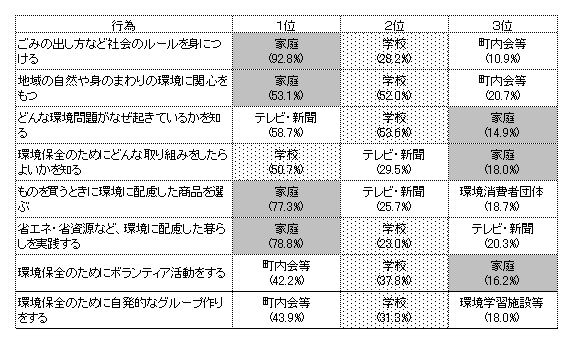
|
|
<参考> ○環境教育シンポジウム’96(平成8年) ○アジア太平洋環境教育シンポジウム(平成8年11月) ○APEC持続可能な都市のための環境教育シンポジウム(平成10年9月) ○アジア太平洋環境教育国際会議(平成11年2月) |
<参考>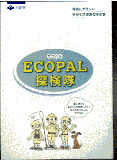

労働団体においても、職場での取組に加え、組合員とその家族を対象に「身近なところから、できることからはじめよう」と日常生活でのライフスタイルの見直しの実践を呼び掛ける運動を展開し、多くの参加者を得ている例がある。 

|
|
<参考> 文部省では、完全学校週5日制の実施に向けて、平成13年度までに、地域で子どもを育てる環境を整備し、親と子どもたちの様々な活動を振興する体制を整備することを目的として「全国子どもプラン」を策定し、次のような取組を推進している。 ○子どもたちの活動の機会と場の拡大 ○地域における子どもの体験活動の情報提供体制の整備 |
|
<参考> 環境報告書とは、事業者が事業活動に伴って発生させる環境に対する影響の程度や影響を削減するための自主的な取組などをまとめて公表するものであり、環境に関する経営方針、組織体制など環境マネジメントシステムに関わる内容や環境負荷物質の排出状況や環境負荷の低減に向けた取組の内容などが記載される例が多い。 現在、民間団体の主催により、優れた環境報告書等を表彰する「環境レポート大賞」が実施されている。これは、環境情報の開示と環境コミュニケーションを促し、事業者の自主的な環境保全の取組等を促進することを目的としている。 |
|
<参考> 環境庁環境研修センターでは、国、地方公共団体において環境行政を担当する職員等を対象に、職務遂行に必要な専門的知識と技術の付与等を目的にした環境行政研修を実施している。平成11年度は、行政関係研修として、環境教育研修、環境基本計画研修、自然保護研修、環境影響評価研修など19コース、国際関係研修として、地球環境保全研修、海外研修員指導者研修など6コース、分析関係研修として、機器分析研修、大気分析研修、水質分析研修など10コースなど全36コースを実施する予定である。平成10年度末までの研修修了者は延べ28,391名である。 なお、人事院では、政府全体で取り組むべき課題や国際関係業務の増大、政策担当の専門家としての国家公務員の資質向上の必要性等に鑑み、行政研修を始め各種研修を実施している。平成11年度においては、課長補佐級や課長級を対象とした行政研修において政策課題研究として、「地球環境の現状と課題」など環境問題をテーマとして取り上げている。 |
| 平成10年7月13日 | 「環境教育・環境学習の今後の推進方策の在り方について」諮問。 企画政策部会に付議。 |
| 同日 | 第57回企画政策部会 |
| ○環境教育小委員会を設置。 | |
| 7月17日 | 第1回環境教育小委員会 |
| ○環境教育・環境学習の現状について | |
| ○一般意見公募について | |
| (7月17日 | 一般意見公募開始) |
| 8月 4日 | 第2回環境教育小委員会 |
| ○諸外国の環境教育の取組について | |
| ○環境教育・環境学習の推進に向けた方向性と緊急に取り組むべき課題について | |
| (8月17日 | 一般意見公募締切) |
| 8月31日 | 関連団体からのヒアリング |
| 9月 8日 | 第3回環境教育小委員会 |
| ○中間取りまとめ骨子について | |
| 9月22日 | 第4回環境教育小委員会 |
| ○中間取りまとめ案について | |
| (9月28日 | 環境教育小委員会中間取りまとめ公表) |
| 10月26日 | 第5回環境教育小委員会 |
| ○情報提供体制の整備について | |
| 11月30日 | 第6回環境教育小委員会 |
| ○環境教育・環境学習に関する各主体の取組について | |
| ○環境教育・環境学習に関するプログラム等の体系化に向けた検討課題について① | |
| 12月22日 | 第7回環境教育小委員会 |
| ○環境教育・環境学習に関するプログラム等の体系化に向けた検討課題について② | |
| 平成11年1月28日 | 第8回環境教育小委員会 |
| ○人材の育成・確保について | |
| ○環境カウンセラーからのヒアリング | |
| 3月18日 | 第9回環境教育小委員会 |
| ○国際協力の推進について | |
| 5月19日 | 第10回環境教育小委員会 |
| ○環境学習拠点について | |
| 6月24日 | 第11回環境教育小委員会 |
| ○環境教育・環境学習を推進するための課題の整理について | |
| 8月26日 | 第12回環境教育小委員会 |
| ○環境教育・環境学習を推進するための仕組みについて | |
| ○小委員会報告の構成について | |
| 10月 4日 | 第13回環境教育小委員会 |
| ○小委員会報告案について | |
| (11月 2日 | 環境教育小委員会報告案公表、一般意見公募開始) |
| (11月30日 | 一般意見公募締切) |
| 12月 9日 | 第14回環境教育小委員会 |
| ○環境教育小委員会報告取りまとめ | |
| 12月14日 | 第71回企画政策部会 |
| ○環境教育小委員会報告、答申案の取りまとめ | |
| 12月24日 | 中央環境審議会答申 |


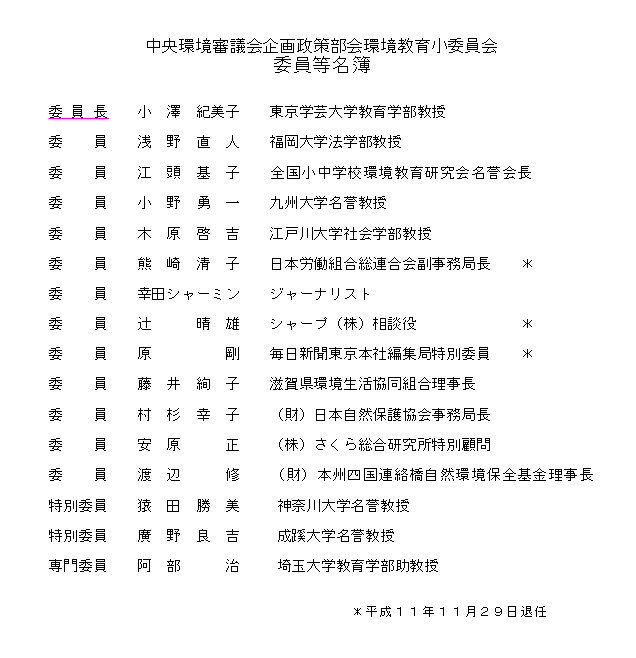
| EICのホームページへ | 環境庁のホームページへ |