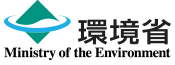平成14年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書について
その主な内容は、以下のとおりである。
[1] オゾン層の状況
| ・ | オゾン全量の長期的傾向については、低緯度地域を除いた領域では減少傾向が続いている。日本上空でも、那覇を除く国内3地点で長期的な減少傾向がみられ、その傾向は札幌において最も大きい。 |
| ・ | 2002年の南極域上空のオゾンホールは、最大時の面積が1991年以降最小で、またその形状が変形・分裂し、1989年以降最も早く消滅した。しかしながら、これは南極上空の成層圏の気温や風等の気象状況が特異であったことによるものであって、オゾンホールの回復の兆しを示すものとみることはできない。 |
[2] CFC等の大気中濃度の状況
| ・ | CFC-12の濃度は1990年代後半以降はほぼ横ばい、CFC-11、113については減少してきている。一方、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)やHFC(ハイドロフルオロカーボン)の濃度は増加の傾向にある。 |
| ・ |
現在のCFC等オゾン層破壊物質の大気中濃度は、1970年代に比べてかなり高い状況にあり、成層圏オゾン層の状況が改善されるためには、これら物質の濃度が大幅に低下することが必要である。 なお、モントリオール議定書の科学パネル報告書では、成層圏中でCFC等から生成してオゾンを破壊する塩素の成層圏中の量はピークかそれに近く、臭素量は依然として増加している。モントリオール議定書が遵守されれば、南極域のオゾン層は2010年までには増加に転じると予測されている。 |
[3] 太陽紫外光の状況
| ・ | 1991年の観測開始以来、国内4ヶ所における有害な紫外光(UV−B)量の観測値に大きな変化傾向は見られない。 |
| ・ | オゾン全量の減少に伴いUV−Bの地上照射量が増加することが確認されていることから、1970年代に比べて、オゾン全量が明らかに減少している地域においては、UV−B量は増加しているものと考えられる。 |
1. 背景
環境省は、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護 法)第22条第2項の規定に基づき、今般、平成14年度における[1]オゾン層の破壊の状況、 [2]CFC(クロロフルオロカーボン:いわゆるフロンの一種)等の大気中濃度の状況、[3]太陽紫外光 の状況の監視結果を取りまとめた。
なお、取りまとめにあたっては、「成層圏オゾン層保護に関する検討会」科学分科会(座長:富永健 東京大学名誉教授)及び環境影響分科会(座長:滝澤行雄 国立水俣病総合研究センター顧問)の指導を仰いだ。
| (参考) | オゾン層保護法第22条 | |
| 気象庁長官は、オゾン層の状況並びに大気中における特定物質の濃度の状況を観測し、その成果を公表するものとする。 | ||
| 2 | 環境大臣は、前項の規定による観測の成果等を活用しつつ、特定物質によるオゾン層の破 壊の状況並びに大気中における特定物質の濃度変化の状況を監視し、その状況を公表するも のとする。 | |
2. 平成14年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書の主な内容
(1)オゾン層の状況
オゾン全量の長期的傾向については、低緯度地域を除いた領域では減少傾向が続いており、高緯度の春季に減少傾向が顕著である。日本上空でも、那覇を除く国内3地点で長期的な減少傾向がみられ、その傾向は札幌において最も大きい。
2002年の南極域上空のオゾンホールは、最大時の面積が1991年以降最小で、またその形状が変形・分裂し、1989年以降最も早く消滅した。昭和基地上空のオゾン全量は8月中旬からオゾンホールの目安である220m atm-cm以下の値を観測した後、9月中旬まで大きく変動し、9月下旬以降少ない状態が続いた。10月中旬以降は多めに推移し、10月は月平均値として最近20年で最も多い値を記録し、11、12月も2番目に多かった。以上より、2002年はオゾンホールの規模が小さくなったが、これは特異な気象状況によるものであって、オゾンホールの回復の兆しを示すものとみることはできない。
2002年の日本上空のオゾン全量は、参照値(1971〜2000年の平均;那覇は1974〜 2000年の平均)と比べて、少なかったのは札幌の1、4、5月、つくばの2、3、7月、鹿児島の1、7月で、多かったのは、つくばの6、9、11、12月、鹿児島の10、 11月、那覇の9〜12月であった。特につくばの7月は観測開始以来最も少なく、那覇の10、12月は観測開始以来最も多かった。
なお、オゾン層の全球的な減少傾向は、既知の自然現象では説明できず、CFC等の大気中濃度が増加したことが主要因であると考えられる。特に、1980年代以降の南極オゾンホールの発達は、大気中のCFC等の濃度増加によると考えることが最も妥当である。
なお、モントリオール議定書のアセスメントパネル(2002年WMO(世界気象機関)/UNEP(国連環境計画)科学パネル報告書)によると、[1]成層圏観測によると塩素総量はピークかそれに近いが、臭素量はおそらく依然として増加している、[2]化学・気候モデルは、成層圏のハロゲンが予想通り減少すると、南極域の春季のオゾン層は2010年までには増加に転じると予測している、[3]観測が蓄積されるにつれ、オゾン全量の減少がUV放射量の増加をもたらしていることが確証されつつある、などとされている。
(2)CFC等の大気中濃度の状況
CFC等の大気中濃度については、北半球中緯度の平均的な状況を代表するとみなせる北海道の観測点において、CFC-12の濃度は1990年代後半以降はほぼ横ばい、CFC-11、113については減少してきている。また、大気中寿命の短い1,1,1-トリクロロエタンについては、すでに減少傾向を示している。都市域の状況の一つとして川崎市で測定したCFC-11、12、113、1,1,1-トリクロロエタン及び四塩化炭素の大気中の濃度については、次第に北海道におけるこれらの物質の大気中濃度のレベルに近づきつつある。これらは1989年7月から開始されたモントリオール議定書に基づく規制の効果と考えられる。一方、ハロン1211及び1301については、今なお、増加の傾向が続いている。また、CFCの代替物質であるHCFC-22、141b、142b及びHFC-
134aの北海道における大気中濃度については増加の傾向にある。
現在の特定物質の大気中濃度は、例えば南極域でオゾンホールが観測される以前の 1970年代に比べてかなり高い状況にあるので、成層圏オゾン層の状況が改善されるためには、これらの物質の濃度が大幅に低下することが必要である。
(3)太陽紫外光の状況
成層圏オゾン層の破壊に伴い、有害な紫外光(UV−B)の地上への照射量が増大した場合には、皮膚がんや白内障の増加、さらに免疫抑制などの人の健康への影響のほか、陸生、水生生態系への影響や大気汚染の増加が懸念されるため、UV−B量の変化の傾向を把握する必要がある。
それにはなお一層のデータの蓄積を必要とするが、日本においては1991年の観測開始以来、国内4ヶ所におけるUV−B量の観測値に大きな変化傾向は見られない。またオゾン全量の変化に敏感な波長300nmの紫外光についても、明らかな傾向は見られていない。しかしながら、UV−B量の観測値はオゾン全量のほか、天候(雲量)や大気混濁度等の影響を受けることに留意する必要がある。なお、これまでの国内4ヶ所における晴れた日のオゾン全量とUV−B量の観測結果に基づく気象庁の解析によると、太陽高度角が同じであれば、オゾン全量の減少に伴いUV−Bの地上照射量が増加することが確認されている。したがって、1970年代に比べて、オゾン全量が明らかに減少している地域においては、UV−B量は増加しているものと考えられる。
(4)その他
モントリオール議定書に基づく、科学パネル及び環境影響パネルそれぞれの報告書が昨年、4年ぶりにまとめられたところであり、その内容を取り入れるとともに、それぞれの報告書要旨の和訳を参考資料に掲載した。
| [1] | 科学パネル報告書のポイント |
| ・ | 対流圏では、オゾン層破壊物質の総量は1992年〜1994年のピーク以来、ゆっくりと減少し続けている。 |
| ・ | 成層圏観測によると塩素総量はピークかそれに近いが、臭素量はおそらく依然として増加している。 |
| ・ | モントリオール議定書は機能しており、議定書で規制された物質によるオゾン層破壊は今後10年程度以内に改善し始めると予想される。議定書が完全に遵守されればオゾンホールは今世紀中頃までにはなくなるという予測もあるが、議定書の完全遵守をもってしても、オゾン層は特に今後10年程度は脆弱なままである。 |
| [2] | 環境影響パネル報告書のポイント |
| ・ | 紫外線が人の健康や生態系に与える影響を確認する研究結果が得られている。特に、UV−Bが眼、皮膚、免疫システムに与える悪影響が確認され続けている。 |
| ・ | 人の健康や生態系に対する気候変動とオゾン層減少の相互作用は、プラスの影響もマイナスの影響もあり、影響の予測をさらに不確実なものにするとされた。 |
添付資料
- (参考)成層圏オゾン層保護に関する検討会
- 日本上空のオゾン全量の年平均値の推移
- 南極上空オゾンホールの三要素の経年変化
- 北半球中緯度及び南半球における特定物質の大気中平均濃度の経年変化
- UV-B量の日積算値
- 連絡先
- 環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
室長 :宇仁菅伸介(内6750)
専門官:新田 晃 (内6755)
担当 :早野 晶子 (内6753)