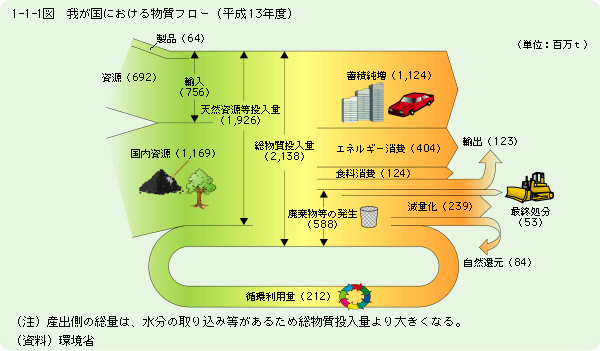
|
第1章
|
廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の状況
|
|
第1節 我が国の物質フロー
|
|
1. 我が国の物質フロー
|
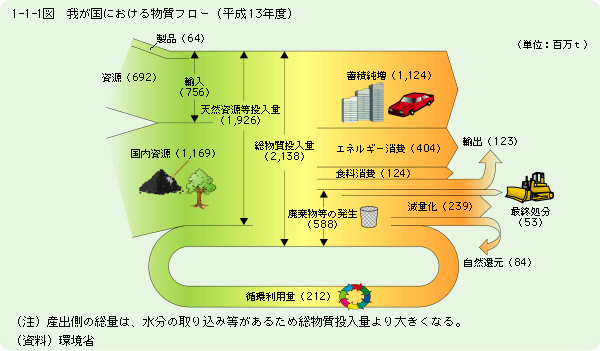
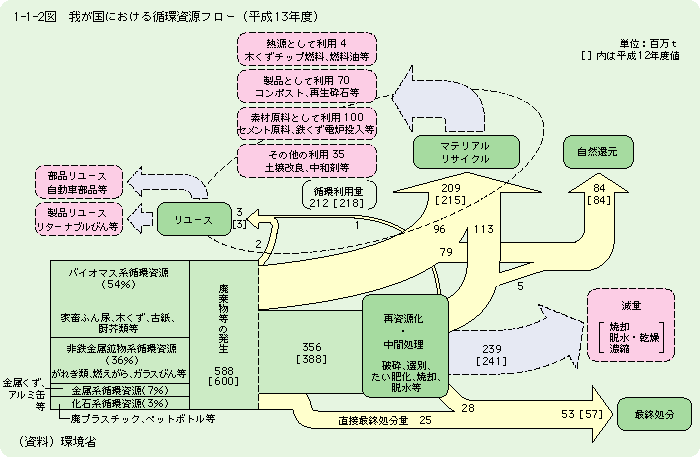
| ア 平成13年度における我が国の循環資源フロー (ア)発生段階 資源や物品がある人に不要となっても直ちに廃棄物となるわけではありません。リサイクルショップや中古自動車、中古家電などの中古品を販売する業者に引き取られて、さらに販売されることがあります。また、工場等では、端材を生産工程に戻したり、溶剤を浄化して再使用したりして、廃棄物の排出抑制に努めています。 これらの取組によってもなお、廃棄物等として排出された量は、平成13年度では5.9億tです。このうち、一般廃棄物(ごみ(0.55億t)及びし尿等(0.29億t)の合計量)が0.84億t、産業廃棄物が4.00億t、その他の副産物・不要物が1.03億tでした(1-1-3図)。国民1人当たりでは4.6t、GDP(国内総生産額)百万円当たりでは1.1tの廃棄物等が発生していることになります。 発生量をものの性状別に見ると、有機性の汚泥やし尿、家畜ふん尿、動植物性の残さといったバイオマス系が最も多く3.2億t、無機性の汚泥や土砂、鉱さいなどの非金属鉱物系(土石系)が2.1億t、鉄、非鉄金属などの金属系が0.4億t、プラスチック、鉱物油などの化石系が0.2億tでした。 (イ)自然還元段階 廃棄物等のうち、家畜ふん尿の一部や稲わら、麦わら、もみがらといった畜産や農業に伴う副産物が排出され、肥料などとして農地等に還元された量は0.84億tでした。 |
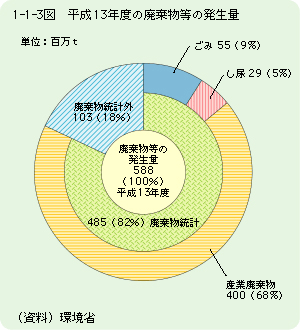 |
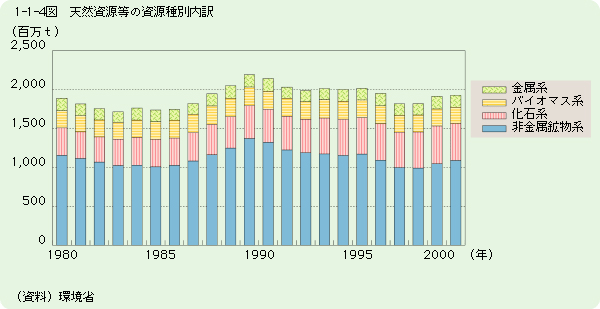
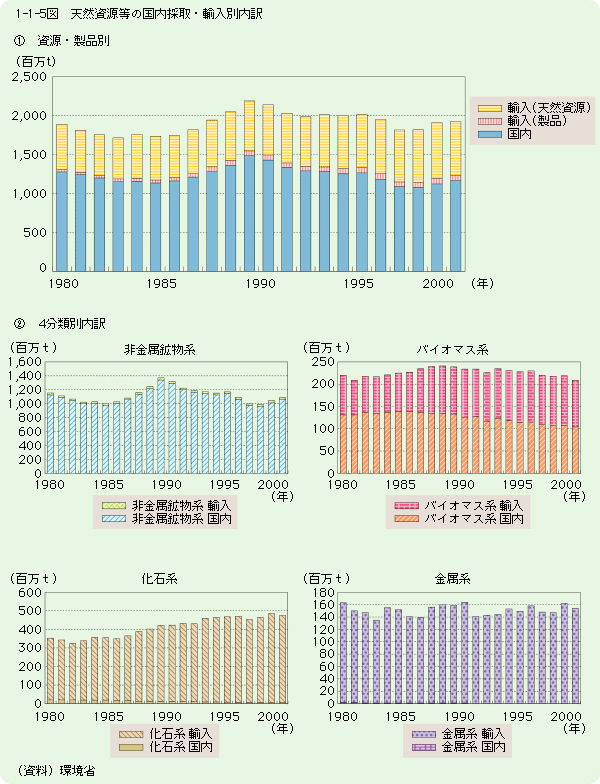
| さらに、これらの4つの種別ごとに、我が国で発生する循環資源がどのように循環利用されているか、その特徴をまとめると以下のとおりです(1-1-6図)。 (ア)バイオマス系循環資源 バイオマス系循環資源は、廃棄物等発生量全体の54%を占めています。その中身を見ると、家畜ふん尿、下水道業や製造業などにおいて水処理の際に発生する有機性汚泥、建設現場や木製品製造業の製造工程から発生する木くず、家庭から発生する厨芥類(生ごみ)などがあります。 バイオマス系循環資源は、水分及び有機物を多く含むため、現状で自然還元率が27%、循環利用率が14%、減量化率が55%、最終処分率が5%と、焼却や脱水による減量化の割合が高いことが特徴として挙げられます。また、循環利用の主な用途としては、農業でのたい肥、飼料としての利用が挙げられます。このほかには、汚泥をレンガ等の原料として利用している場合や、木くずを再生木質ボード等として利用する場合などがあります。我が国におけるバイオマス系資源の投入量は2.1億tですので、投入量に占めるバイオマス系循環資源の循環利用量の割合は21%となっています。 バイオマス系循環資源の循環利用量の拡大及び最終処分量の削減に向けては、農業分野での肥料、飼料としての受入れの拡大、メタン発酵施設などでのエネルギー化や残さの焼却等による減量化処理の徹底などが考えられます。 |
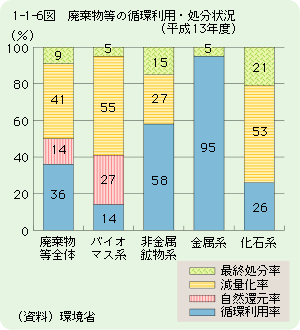 |
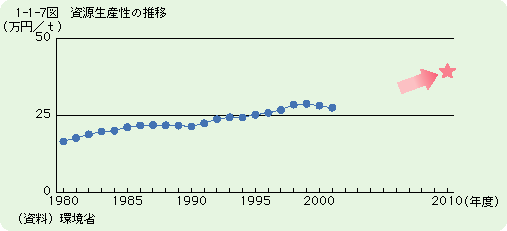
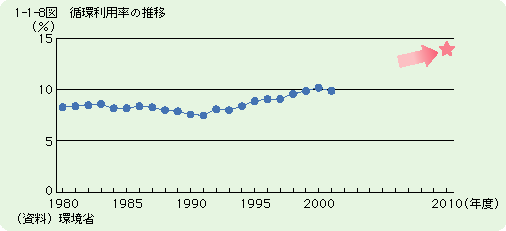
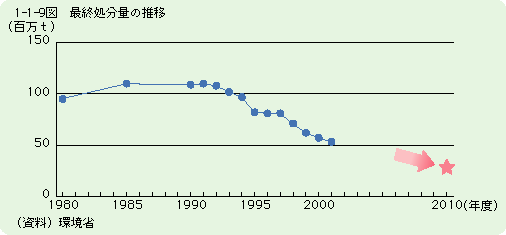
| コラム 8 | 資源生産性 |
ある変数がどのような要因で変化するのかを分析する際に、その変数をいくつかの要因に分析することがあります。例えば、環境問題を考えるときに最も基本となる要因分解は次のようなものです。 環境負荷の程度= GDP×環境負荷の程度/GDP 環境負荷の程度とは、CO2や様々な汚染物質の排出量や環境中の濃度、廃棄物の発生量などを代表します。この式で、環境負荷の程度を低くするためにはGDPを小さくするか、GDP当たりの環境負荷の程度を小さくする2つの方法があることが分かります。後者のGDP当たりの環境負荷の程度の逆数(環境負荷の程度当たりのGDP)は、いわゆる「環境効率性」と呼ばれるものです。 循環型社会基本計画で目標を定めた「資源生産性(=GDP/天然資源等投入量)」も天然資源等投入量(一種の環境負荷の程度)当たりのGDPを示すものであり、「環境効率性」の一種です。 つまり、循環型社会基本計画で「資源生産性」の改善を目指すということは、経済を抑える(GDPの抑制)という方法ではなく、産業や人々の生活がものを有効に利用している社会(より少ない資源でより大きな豊かさを生み出す社会)を実現しようとするものと言えます。 |
|
|
2. 廃棄物の排出量
|
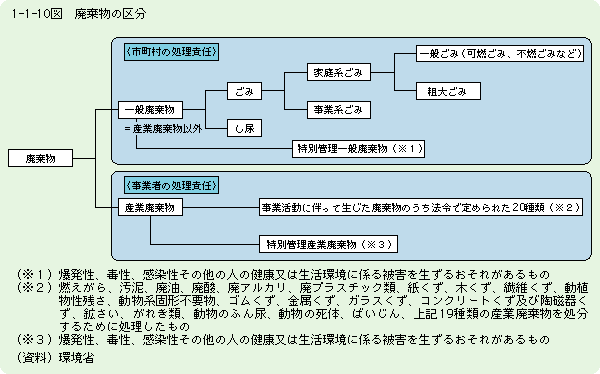
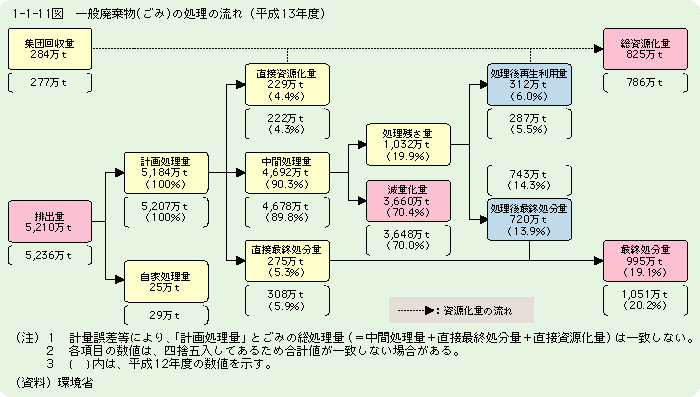
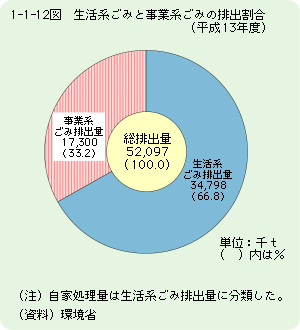 |
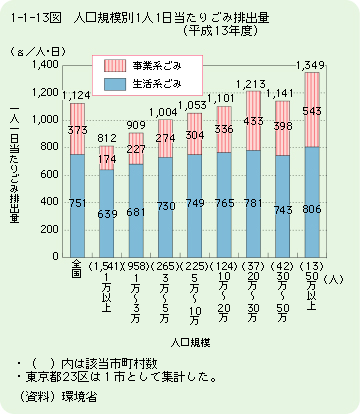 |
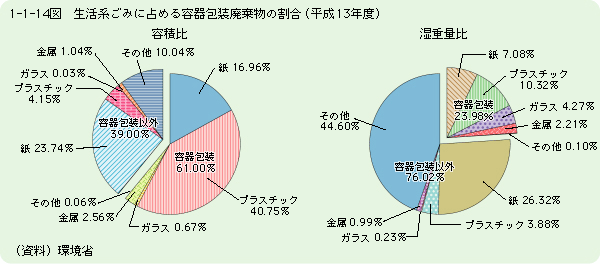
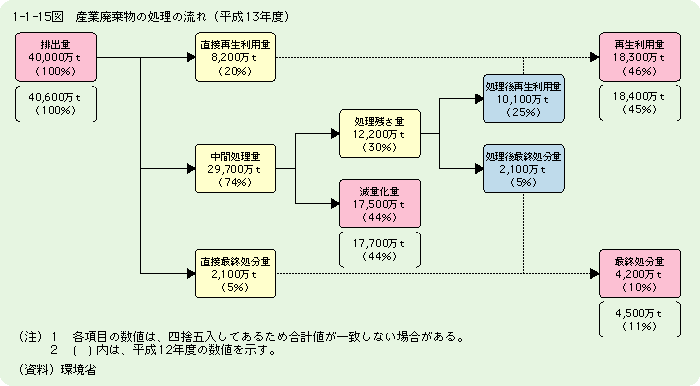
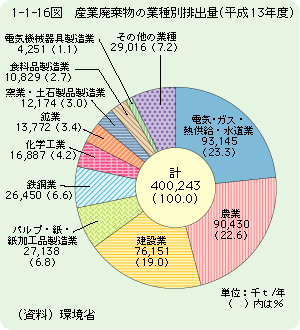 |
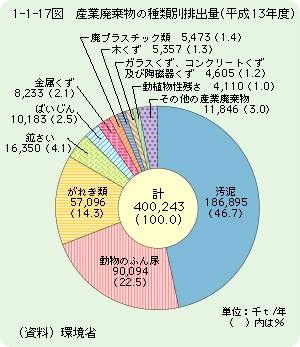 |
|
3. 循環的な利用の現状
|
| (1)容器包装(ガラスびん、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装等) 容器包装リサイクル法に基づく分別収集及び再商品化の実績は1-1-1表のとおりです。 平成15年度の実施状況で見ると、平成9年度から分別収集の対象となった品目では、紙パックを除いて、9割以上の市町村が分別収集を行っています。なお、平成12年度から追加されたプラスチック製容器包装、紙製容器包装、段ボールについては、分別収集に取り組む市町村が着実に増加しています。 ア ガラスびん ガラスびんの生産量は平成14年で約168.9万tであり、減少傾向にあります。これは、重く、割れることがあるガラスびんに比べ、デザインが多様で、軽く、携帯の利便性に優れるペットボトルなどの容器に、消費者の嗜好が変化したためと考えられます。 ガラスびんは1回限りの利用を前提として作られるワンウェイびんと洗浄して繰り返し利用されるリターナブルびんとに分けられます。 廃棄されたワンウェイびんは砕かれてカレットになり、新しいびんを作る場合の原料などとしてリサイクルされています。カレットとはガラスを砕いたもので、カレット利用率とは新しいガラスびんの生産量に対するカレット使用量の比率を表したものです(1-1-18図)。 |
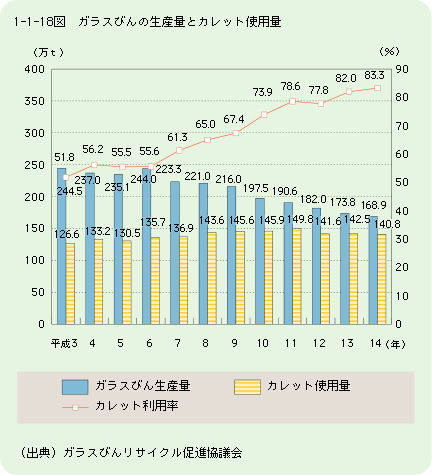 |
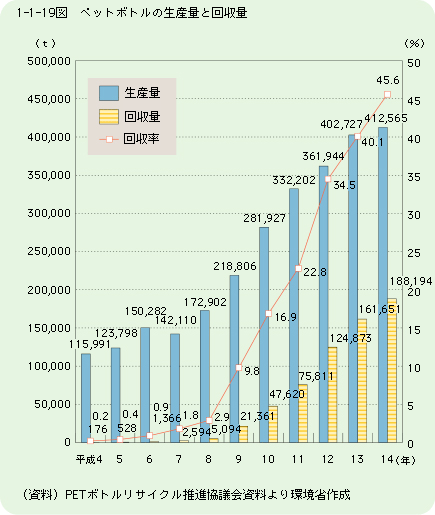 |
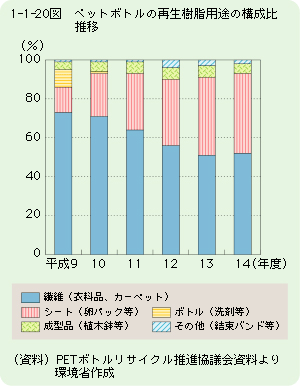 |
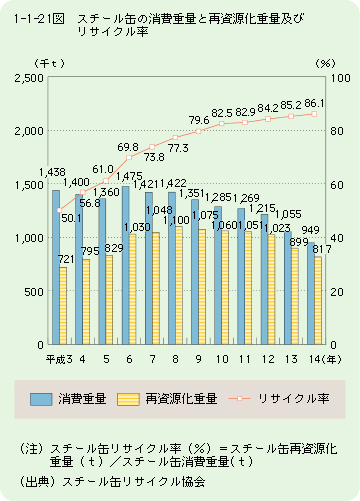 |
 |
| ク 段ボール 段ボールは平成12年度から新たに容器包装リサイクル法に基づく対象品目となり、市町村による分別収集が始まりました。平成14年度の分別収集実績量は、50.3万tとなっています。 また、分別収集を実施した市町村数は、2,105であり、同じ時期に容器包装リサイクル法に基づく対象品目となったプラスチック製容器包装や紙製容器包装と比較するとかなり多くなっています。 これは、既に段ボールのリサイクルシステムが確立されていたためであると考えられます。段ボールリサイクル協議会によれば、利用された段ボールは回収され、再び段ボールとなって使用され、約7回まで使用可能といわれています。 平成14年の段ボール原紙の生産量は863.1万tあり、段ボール古紙の回収量は879.2万tで、リサイクル率は101.9%となっています。 (2)紙 平成13年度の古紙の回収率及び利用率はそれぞれ63.2%、58.3%となっています(1-1-23図)。紙の中には、トイレットペーパーなどの回収の不可能なものや、書籍のように長期間にわたって保存されるものなどがあるため、約72.9%の回収率が限界と考えられています。古紙の回収率及び利用率を向上させるためには、一人ひとりが注意して分別排出を心掛けるとともに、再生紙の利用に努めることが必要と言えます。 なお、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)に基づき、国内で製造される紙の古紙利用率を平成17年度までに60%に向上することが目標として定められています。 |
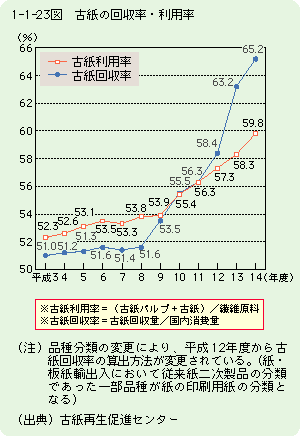 |
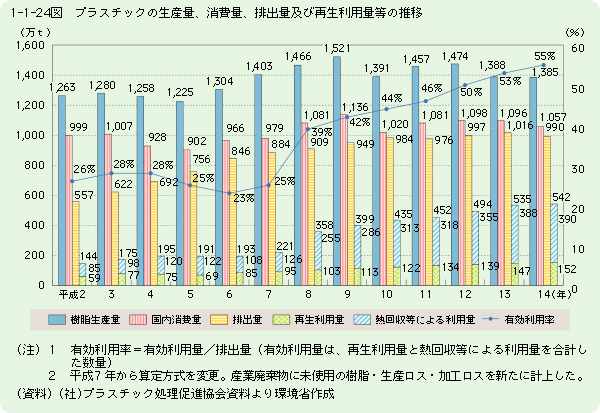
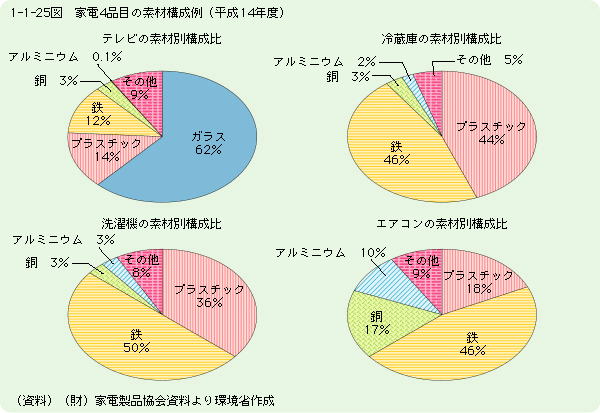
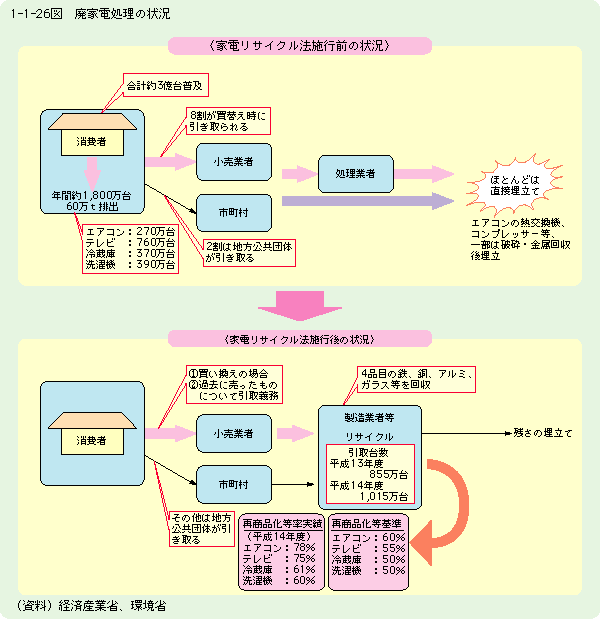
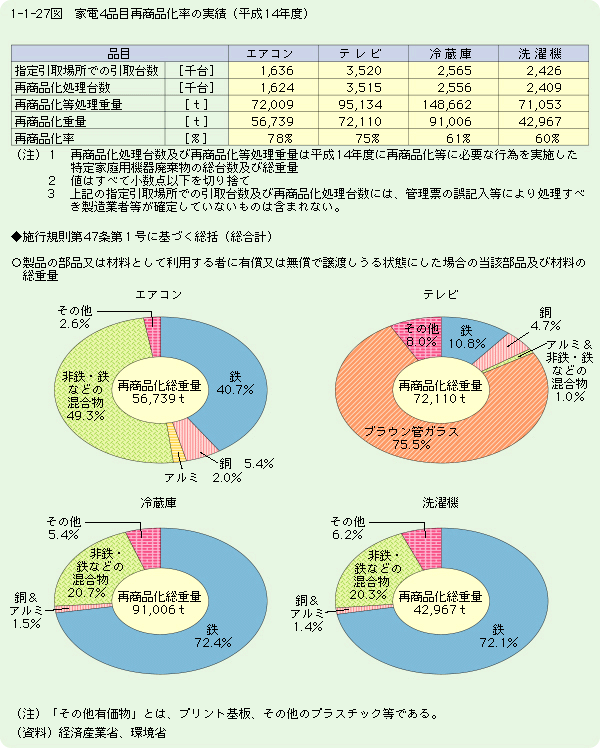

| コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊については、平成3年12月より「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について」(平成14年5月改訂 国土交通省)の策定、各地方整備局での運用に伴い、再資源化率が大きく伸びています。これらは、平成14年度の実績でいずれも「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)の目標である95%を超えており、今後はその維持が課題となっています。また、建設発生木材や建設汚泥は再資源化等が進展しているものの、さらなる取組が求められています(1-1-29図)。これらの再資源化等率の維持・向上のためには、今後とも再生品に関する技術開発や需要創出が鍵となっています。 (6)建設発生土 建設工事現場から場外に搬出された建設発生土は平成14年度の実績で約2億4,500万m3で、このうち工事間利用した割合は30%となり、平成12年度と比較して建設工事で利用する土砂のうち新材利用量は約26%減少しました。さらなる工事間利用の推進に向けて、平成15年10月に国土交通省が策定した「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」に基づき、各種の取組を進めていくことが必要となっています。 |
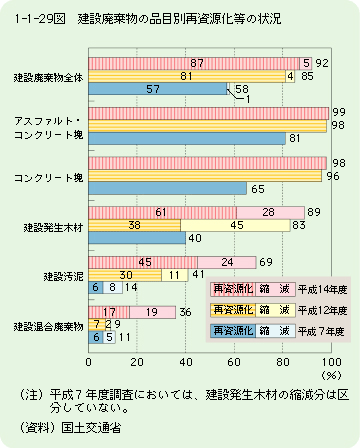 |
| (7)食品廃棄物 食品廃棄物は、食品の製造、流通、消費の各段階で生ずる動植物性の残さ等であり、具体的には加工食品の製造過程や流通過程で生ずる売れ残り食品、消費段階での食べ残し・調理くずなどです。 これら食品廃棄物は、食品製造業から発生するものは産業廃棄物に、一般家庭、食品流通業及び飲食店業等から発生するものは一般廃棄物に区分され、平成13年度において前者が411万t、後者が1,778万t(うち一般家庭から発生するもの1,250万t)、合わせて2,189万tが排出されています(1-1-2表)。 食品製造業から発生する食品廃棄物は、必要量の確保が容易なこと及びその組成が一定していることから比較的再生利用がしやすく、たい肥化が89万t(22%)、飼料化が104万t(25%)及び油脂の抽出その他が54万t(13%)で合計247万t(60%)が再生利用されています。 |
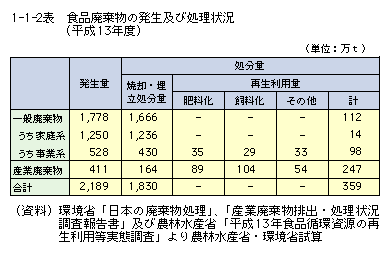 |
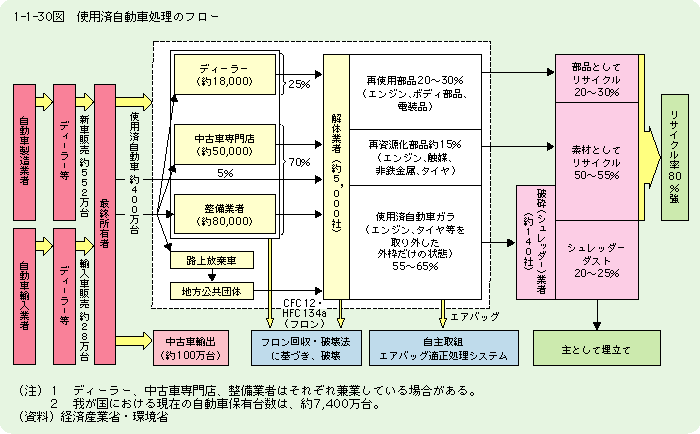
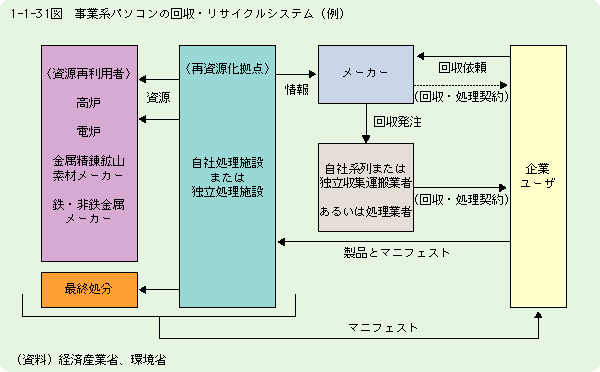
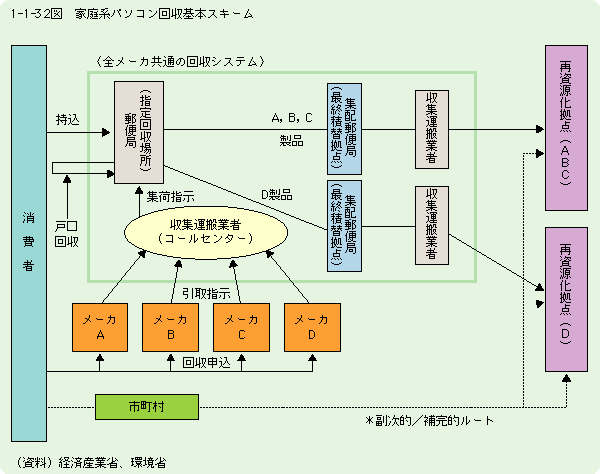
| (10)携帯電話・PHS 携帯電話・PHSは、軽量化・廉価化・高機能化に伴いその利用者が急増し、平成14年度末時点での携帯電話・PHSの契約数は8,112万台となっています。一方、携帯電話の平均使用期間は約1年半との推計もあり、普及率の上昇とともに買換え需要も増加し、旧機種の廃棄台数も急増しているため、資源の有効活用等の観点から循環的な利用や適正な処分が必要となっています。 (社)電子情報技術産業協会によると、平成14年度における携帯電話(自動車電話を含む)・PHSの国内出荷台数は4,422万台ですが、それに伴い年間約3,900万台が解約・機種変更等により不要となると推計されます。 (社)電気通信事業者協会と情報通信ネットワーク産業協会によると、そのうち回収される台数は1,137万台(回収率29%)です。この回収された携帯電話・PHSを重量に換算すると746tで、このうち再資源化される量は138t(再資源化率19%)となります。また、携帯電話・PHSで使用する電池の回収数は973万台(回収率25%)で重量に換算すると193t、そのうち再資源化される量は102t(再資源化率53%)、充電器の回収数は336万台(回収率9%)で重量に換算すると251t、そのうち再資源化される量は57t(再資源化率23%)となっています(1-1-3表)。 なお、現在、回収された携帯電話・PHSの再資源化については焼却・破砕等を行い、有価金属を取り出す方法が主であり、携帯電話1tから金280g、銀2kg、銅140kgが回収されると推計されます((財)クリーン・ジャパン・センター「再資源化技術の開発状況調査報告書(平成12年3月))。 |
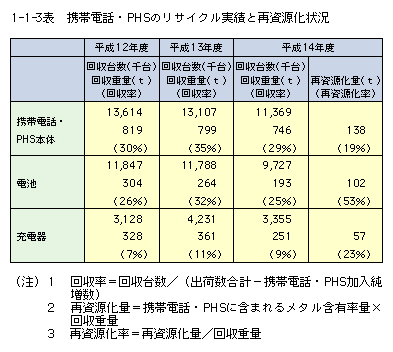 |
| (13)下水汚泥 下水道事業において発生する汚泥(下水汚泥)は、下水道の普及に伴って年々増加する傾向にあります(1-1-33図)。平成13年度現在、全産業廃棄物の発生量の2割近くを占める約7,790万t(対前年度約210万t増、濃縮汚泥量として算出)が発生していますが、最終処分場に搬入される量は85万t(対前年度比約13万t減)であり、脱水、焼却等の中間処理による減量化や再生利用により、最終処分量の減量化を推進しています。なお、平成14年度において、下水汚泥の有効利用率は、乾燥重量ベースで60%となっています。 下水汚泥の再生利用の形態は多岐に渡っています。有機物に富んでいる下水汚泥の性質に着目して古くから緑農地利用が行われています。以前は脱水ケーキの状態で利用されていましたが、最近はコンポスト化して肥料として用いる方法が主流となっています。汚泥が焼却・溶融処理されるようになった近年では、建設資材としての利用が増加しています。 平成14年度には乾燥重量ベースで126万tが再生利用され、用途としては、セメント原料(56万t)、肥料等の緑農地利用(29万t)、レンガ、ブロック等の建設資材(41万t)などに利用されています。 また、下水汚泥の熱回収の取組として、嫌気性消化過程で発生するメタンガスなどの消化ガスを用いた消化ガス発電を全国18か所で実施しているほか、下水汚泥焼却廃熱の利用、汚泥自体の燃料化などが行われています。 |
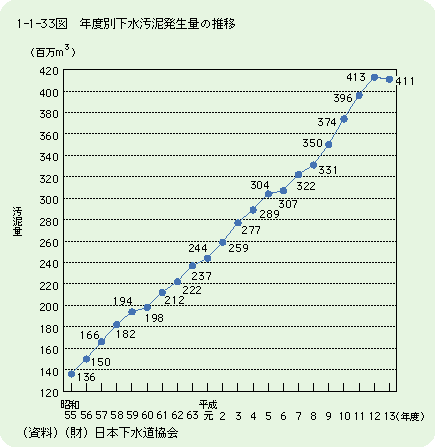 |
| コラム 9 | 使用済携帯電話の回収・再利用へ向けた取組 |
携帯電話やパーソナルコンピュータなどの電気電子廃棄物の処理は、イーウェイスト(e-waste)と呼ばれ、バーゼル条約における取組として重要な課題となっています。例えば、世界で約11億台が流通し、年間約4億台製造されているという携帯電話ですが、先進国の使用済機器が途上国において環境配慮されずに再資源化が行われているといった問題が指摘されています。 このため、平成14年12月にスイスのジュネーブで行われたバーゼル条約第6回締約国会議では、スイスのロシ環境大臣の提案により、携帯電話メーカー10社、バーゼル条約事務局、国連環境計画(UNEP)らは、使用済携帯電話の回収・再利用システム構築検討のためのパートナーシップ・イニシアティブ(MPPI:Mobile Phone Partnership Initiative)について合意しました。現在、作業部会等において具体的な取組の検討が進められています。 日本においても携帯通信事業を行う事業者らが中心となって「モバイル・リサイクル・ネットワーク」という自主的なリサイクルシステムを運営していますが、平成14年度の携帯電話・PHS回収率は29%で、平成12年度の30%、平成13年度の35%に比べ鈍化傾向にあります。この理由の1つとしてはカメラ機能など携帯電話・PHSの高機能化に伴い、解約後も使用者が手元に機器を残す場合が増えているためと考えられます。  |
|
|
第2節 一般廃棄物
|
|
1. 一般廃棄物(ごみ)
|
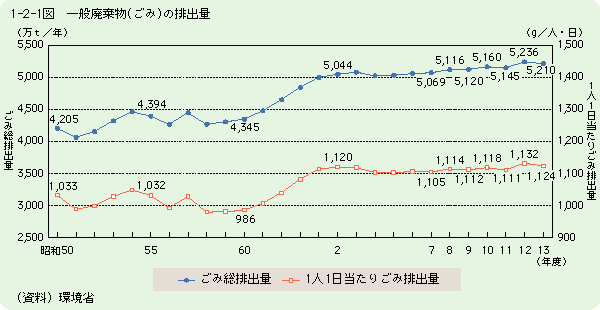
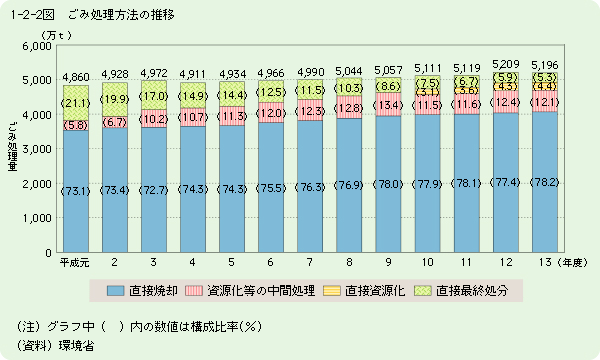
| ウ 焼却施設数の推移 ごみ焼却施設数は全国で約1,800施設で推移していましたが、平成6年度より徐々に減少し、平成13年度のごみ焼却施設数は1,680施設でした。その燃焼方式に着目すると、1日ごとに埋火するタイプの焼却施設は減少し、ダイオキシン対策に有効でかつごみ発電が可能な24時間燃焼方式(全連続炉)の焼却施設が増加しています。なお、平成13年度の全連続炉数は549施設となっており、前年度より15施設増加しています。 (2)一般廃棄物処理対策 ア 補助実績 ダイオキシン類の排出削減とともに一般廃棄物のリサイクル促進のため、平成15年度は、約1,220億円の補助金等により、ごみ処理施設、汚泥再生処理センター、コミュニティ・プラント、埋立処分地、リサイクルプラザ等の一般廃棄物処理施設の整備を図りました。 イ ごみ処理事業費の推移 ごみ処理事業経費については平成13年度で2兆6,029億円であり、国民1人当たりに換算すると、2万500円となり、前年度より1,800円増加しています(1-2-3図)。 |
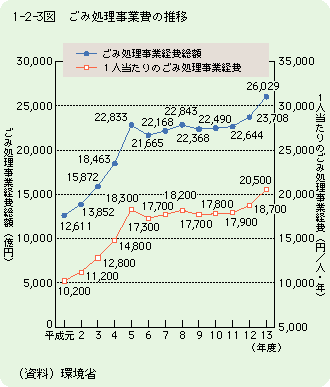 |
|
2. 一般廃棄物(し尿)
|
| (1)し尿処理の推移 し尿処理人口の推移を見ると、浄化槽人口がほぼ横ばいの推移であるのに対し、下水道人口(7,357万人)の増加により、これらを合わせた水洗化人口(1億763万人)は年々増加しています(1-2-4図)。 平成14年度末の浄化槽の設置基数は877万基(平成13年度882万基)で、初めて前年度と比べて減少しました。内訳を見ると、合併処理浄化槽(し尿と生活雑排水の処理)が195万基(平成13年度176万基)と増加しているのに対し、単独処理浄化槽(し尿のみの処理)が682万基(平成13年度705万基)と大きく減少しており、その結果、合併処理浄化槽の割合は22.3%(平成13年度20.0%)に上昇しています。国庫補助制度の充実等により合併処理浄化槽の整備が進む一方、平成12年の浄化槽法改正によって単独処理浄化槽の新設が原則として禁止され、合併処理浄化槽への設置替えや下水道等の整備により、単独処理浄化槽の廃止が進んでいることが影響しているものと考えられます。 (2)し尿及び浄化槽汚泥の処理状況の推移 平成13年度の実績では、し尿及び浄化槽汚泥3,052万klはし尿処理施設又は下水道投入によって、その95.5%(2,914万kl)が処理されています。 また、海洋投入処分量は、123万klと計画処理量の4.0%を占めていますが、その割合は年々わずかずつ減少しています。なお、海洋投入処分については、平成14年2月より現に海洋投入処分を行っている者に対して5年間の経過措置を設けた上で禁止されました。 |
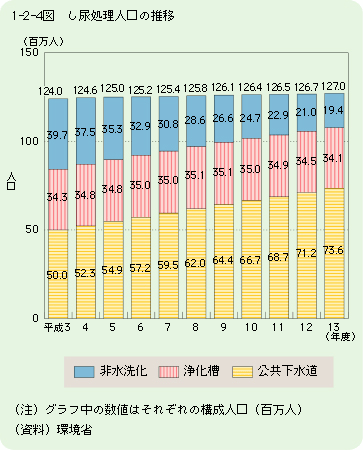 |
|
第3節 産業廃棄物
|
|
1. 産業廃棄物
|
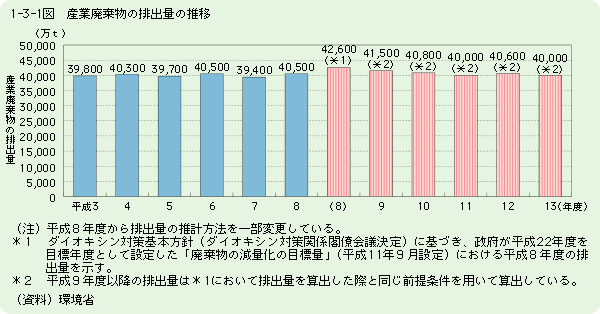
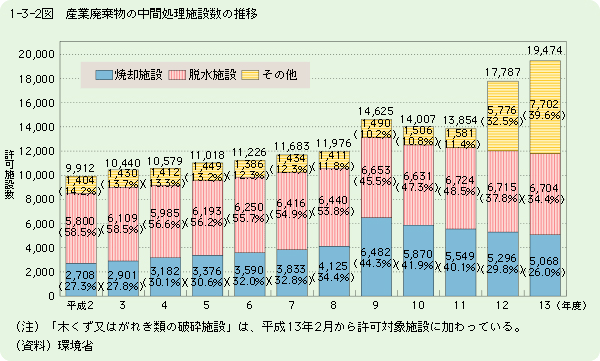
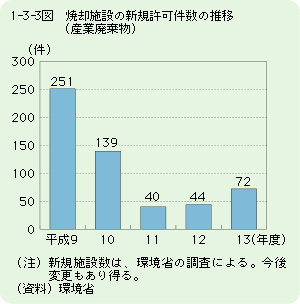 |
 |
|
2. 大都市圏における産業廃棄物の広域移動
|
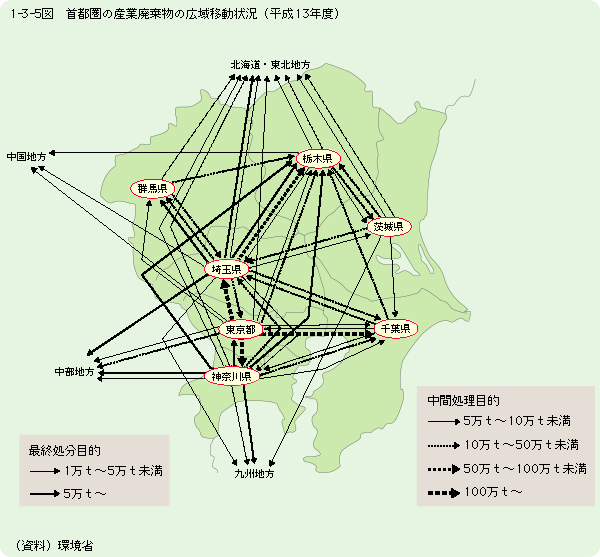
|
第4節 廃棄物関連情報
|
|
1. 最終処分場の残余容量と残余年数の推移
|
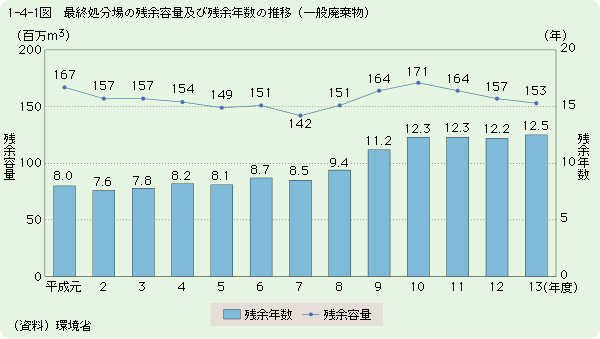
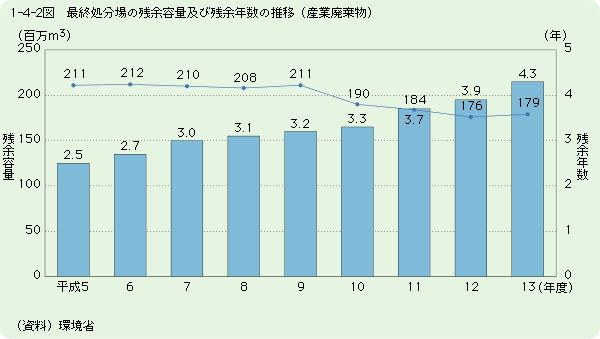
|
2. ごみ焼却施設における熱回収の取組
|
| (1)ごみの焼却余熱利用 ごみ焼却施設からの余熱を有効に利用する方法としては、後述するごみ発電をはじめ、施設内の暖房・給湯、温水プール、老人福祉施設等社会福祉施設への温水・熱供給、地域暖房への供給等がありますが、施設内の暖房・給湯が最も普及しています(1-4-3図)。 余熱利用の動機、目的を見ると、清掃工場で使用する資源エネルギーの節約、地域還元が大きな割合を占めています。 このような施設内での余熱利用の推進に加えて、施設外部への熱供給等を更に推進する体制づくりを進めていく必要があります。そのためには、廃棄物の量・質の変動への対処などの技術上の問題、ガスや石油による熱供給とのコスト比較、電気事業法等関係法令との調整などについて十分な検討が必要となります。 平成4年には、ごみ焼却余熱の有効利用を推進し、ごみ焼却施設に対する社会的評価の向上を図ることを目的とした「ごみ焼却余熱有効利用促進市町村等連絡協議会」が結成され、ごみ焼却余熱の有効利用に関する諸課題について、参加している市町村等を中心に研修や連携交流などの活動が行われています。 |
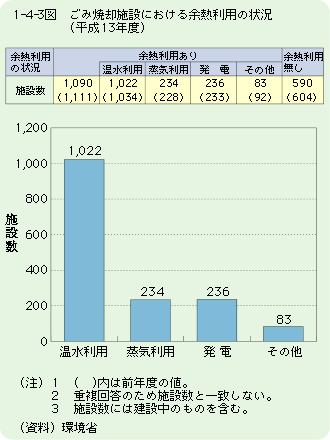 |
| (2)ごみ発電 ごみ発電とは、ごみを焼却する時に発生する高温の排出ガスの持つ熱エネルギーをボイラーで回収し、蒸気を発生させてタービンを回して発電を行うもので、ごみ焼却施設の余熱利用の有効な方法の一つです。 我が国で最初の実施例は、昭和40年の大阪市西淀工場であるとされます。その後、国では、ごみ焼却施設の新設、更新時における余熱利用設備や既存の施設に余熱利用設備を設置する場合に補助を行うなど、ごみ発電の推進に努めてきました。 平成13年度末において、稼働中又は建設中のごみ焼却施設のうち、発電を行っている施設は236に上ります(1-4-1表)。また、大規模な施設ほどごみ発電を行っている割合が高いため、ごみ発電を行っている割合は施設数ベースでは14.0%ですが、ごみ処理能力ベースでは約50%となっています。その総発電量は、約55億kWhであり、1世帯当たりの年間電力消費量を4,300kWhとして計算すると、この発電は約128万世帯の消費電力に匹敵します。また、ごみ発電を行った電力を場外でも利用している施設数は152施設(約64%)となっています。 |
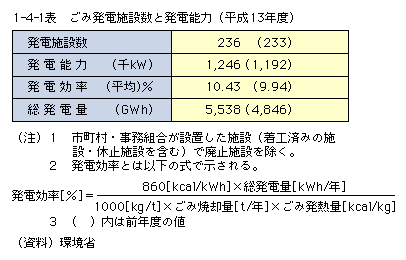 |
|
3. 特別管理廃棄物
|
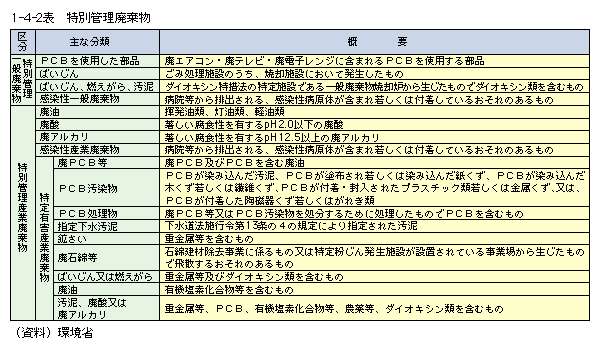
|
4. ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理体制の構築
|
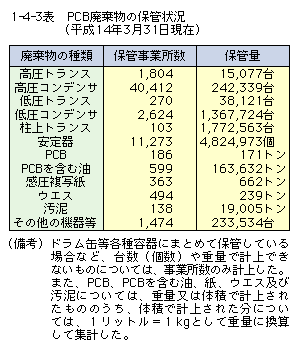 |
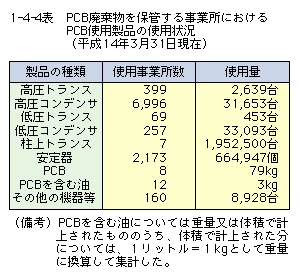 |
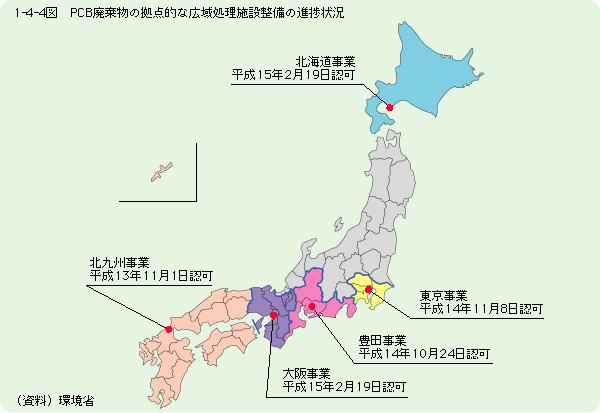
|
5. ダイオキシン類の排出抑制
|

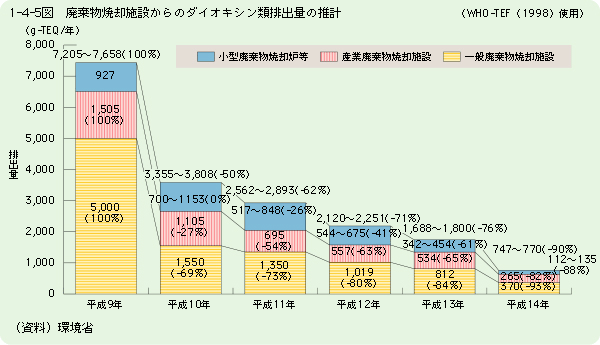
|
6. 有害廃棄物の越境移動
|
| 我が国では、地球環境の保全に資するという観点から早期にバーゼル条約に加入することが必要であるとの認識のもと、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)が、バーゼル条約の国内対応法として平成4年12月に制定、公布されると同時に、廃棄物処理法が国内処理の原則を盛り込んで改正され、平成5年9月にバーゼル条約に加入しました。この条約は同年12月から我が国について発効し、同月、バーゼル法も施行されました。 また、平成4年3月に採択されたOECDの「回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定」についても、バーゼル条約の我が国における発効に先立ち受け入れており、同決定が適用される廃棄物のOECD加盟国との間の越境移動は平成5年12月以降バーゼル法に基づき、必要な規制が行われています。平成15年1月から12月までのバーゼル法の施行状況は、1-4-6表に示すとおりです。 バーゼル条約の締約国は158か国及び1機関(EC:欧州委員会)となっており(平成16年2月末現在)、おおむね2年ごとに開催される締約国会議において条約の効果的実施についての検討等が行われています。 また、バーゼル条約の制度の趣旨やバーゼル法及び廃棄物処理法の周知を図り、不適正な輸出入を防止するためのバーゼル法等説明会を全国各地で税関等の協力を得て開催するとともに、環境省・経済産業省において輸出入に関する事前相談を行っています。 |
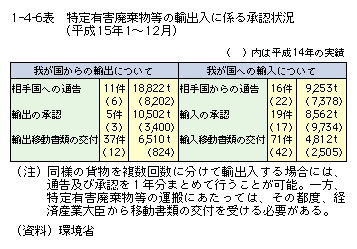 |
|
7. 小売業者から製造業者等への廃家電の確実な引渡しについて
|