
第1章第3節で示した循環共生型の地域を実現するためには、それぞれの地域が有する地形、自然環境、人的資源、伝統文化、その地域を支える市民・住民などそれぞれの地域の特性を把握し、生かすことにより、地域を活性化していくことが重要です。そうした地域の特性は、正にその地域に根ざした「地域資源」と言うことができます。地域資源という用語は様々な定義がされますが、既存の分析では「地域内に存在する資源であり、地域内の人間活動に利用可能な(あるいは利用されている)、有形、無形のあらゆる要素」と定義されており、ある資源は他の地域資源と関係を持ち、一つの地域資源は人間活動に多様な機能を提供するものとして整理されています(表3-2-1)。

地域資源は多種多様であり、どの地域にも存在するものですが、地域住民にとっては身近過ぎて、それが地域資源であると気付いていないことも少なくありません。しかし、ありふれた地域資源であっても、その活用方法によって、地域活性化の源泉となることがあります。例えば、徳島県勝浦郡上勝(かみかつ)町は、昭和30年には約6,300人であった人口が、平成22年には1,800人を切るまでに減少し、65歳以上の人口割合(高齢化率)が52.4%と、四国4県の中で最も高くなりました。しかし、高齢化と過疎化が進む中で、高齢者自身が木の葉や野草を料理のツマモノとして販売する「葉っぱビジネス」という地域興しのビジネスを考案し、その結果、億単位の売上げを収めています。これは、表3-2-1で言うところの、植物の生育地である里地里山といった「自然資源」がある地域において、高齢者という「人的資源」が、自身の持つ「情報資源(地域に存在していた美しい木の葉や野草を地域資源として再発見し、それを料理のツマモノとして活用・販売するという発想を含む)」を生かした事例と言えます。
地域資源と人間活動の関わりは、社会・経済システムの変化(時代の変化)と共に変化してきました。地域資源の中には、例えば里地里山の薪炭林などのように、二次的自然が地域資源として活用されなくなるとともに、その活用の知恵という知的資源やノウハウを有した人的資源等も失われつつあるという例も見られます。一方で、近年では、気候や地理的条件といった地域特性資源、伝統や豊かな自然に根ざした文化・社会資源、そして、地域活性化を図る主体となる人的資源を有効活用しようという動きが見られます。
本節では、地域資源を効率的に活用したり、複数の地域資源を組み合わせるなど、地域資源を有効活用することで、地域活性化につなげる可能性について紹介していきます。
島根県隠岐(おき)郡海士(あま)町は、平成23年に「ないものはない」宣言を行いました。この独特の表現には[1]無くてもよい、[2]大事なことはすべてここにある、という二重の意味が込められています。離島である海士町は、都会のように便利ではなく、モノも豊富とは言えないまでも、潤沢な自然や郷土の恵みを生かせば暮らすためには十分にそろっていて、だからこそ今あるものの良さを上手に生かしていこうとする考え方です。海士町のこの取組は島内外から関心を呼び、平成26年9月の第187回臨時国会における安倍内閣総理大臣の所信表明演説でも取り上げられました。
このように、それぞれの地域に備わる様々な特性が「地域資源」として認識され、さらには付加価値が加わることにより、地域の人々の暮らしのために役立てられ、地域活性化が実現し、持続可能な地域づくりの源泉にできる可能性があります。本項ではそうした問題意識に立って、代表的な資源を四つ取り上げて紹介していきます。
ア 再生可能エネルギー資源活用の概況
第1章でも触れたように、我が国は資源小国としてエネルギー資源の大部分を海外に依存しており、自給率が低いという脆(ぜい)弱なエネルギー供給構造を抱えています。また、東日本大震災以降、火力発電による発電量の増大によって燃料調達コスト及びCO2排出量の増加が顕著となっています。こうした課題を解決する手段として、再生可能エネルギーの活用が注目を浴びています。
こうした背景によって、平成25年度の我が国の総発電量に占める再生可能エネルギーの割合は約2.2%(水力除く、前年度比+0.6%)となっています。また、我が国の再生可能エネルギーについて、エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因による設置の可否を考慮したエネルギー資源量である導入ポテンシャルに関する調査結果を見ると、それぞれ種類によって地域の偏りはあるものの、国内の多くの地域は、何らかのエネルギー資源が備わっていることが分かります(図3-2-1)。
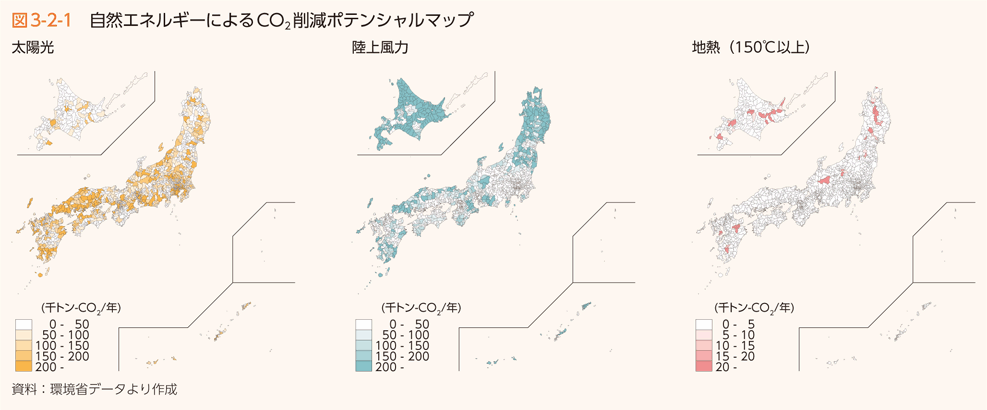
我が国では、エネルギー政策を考える際の一つの視点として、「3E+S」を挙げています。三つのEとは[1]Energy Security:安定供給、[2]Economic Efficiency:経済効率性の向上、[3]Environment:環境への適合を指し、SとはSafety:安全性を指しています。これらの視点を踏まえバランスよくエネルギー政策を実現していくため、国では固定価格買取制度(以下「FIT」という。)によって再生可能エネルギーの導入推進を図っているほか、平成26年4月に閣議決定したエネルギー基本計画では「有望かつ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源」と位置付けています。
以下では、地域の再生可能エネルギー資源の一例として、賦存量が東北地方を始め特に地方圏に多く分布する木質バイオマスに焦点を当て、その活用について紹介します(図3-2-2)。
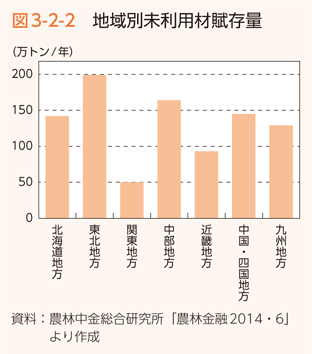
イ 地域の自然エネルギー活用による活性化 ~木質バイオマスを事例として~
木質バイオマスについて、前項で触れたように、我が国には賦存量が広く分布していることが分かっています。その大きさを示す指標である森林蓄積を見ると、日本には60億m3が賦存し、バイオマスに関して先進的な取組をしているドイツの34億m3を大きく上回っています。
バイオマスは、エネルギーとして利用しても温室効果ガスの実質的な増大がない(カーボンニュートラル)ことから、その利活用を地域の土地利用計画や産業構造とうまく合致させることができれば、特に農山漁村にエネルギー等の供給という新たな役割を与えて林業の衰退を食い止めるとともに、森林の適正管理により農林漁業の自然循環機能(森・里・川・海の連環)を維持増進させ、持続的な地域の発展につなげることが期待されています。また、地域密着型で小規模分散型のバイオマス活用に関しては、その活用が地域への経済効果や雇用機会の増大といった効果のみならず、自立・分散型のエネルギー源となるため、前節でも触れた地域の防災・減災にも寄与します。
この地域密着型の木質バイオマスの活用について、国内の先進事例として挙げられるのが北海道の北部に位置する下川(しもかわ)町です。下川町は人口約3,500人、町の面積6万4,420haの約9割を森林が占める町で、「森林未来都市」を目指す一環として平成16年からバイオマスボイラーを導入しました。現在では、数十kW~千kW級の比較的小規模のボイラーが複数稼働し、地域の公共温泉、学校、福祉施設等に熱エネルギーを供給しています。その結果、公共施設全体の熱需要量の約6割を木質バイオマスで賄っています。町は今後もバイオマス利用率を高めることで、地域の収支を示す域際収支の更なる改善に努め、地域活性化を図る方針です。具体的には、現在54%となっているバイオマス利用率を平成30年に65%、平成34年に78%と次第に高めることにより、林業・林産業の域内生産額を平成25年の25.2億円(域内総生産額の約15%)から平成30年には35億円へと、林業・林産業の雇用人数については平成25年の271人から平成34年には380人へとそれぞれ拡大させることを目標としています。
現在、FITの対象の中でも、バイオマスを利用した発電の認定容量は大きく伸びており、注目を集めていることが分かります。現状のFITにおけるバイオマス発電のうち、最も高い売電価格が設定されているのは、伐採後に未利用のまま林地に放置される間伐材などの「未利用材」であり、導入件数の増加も顕著です(図3-2-3)。
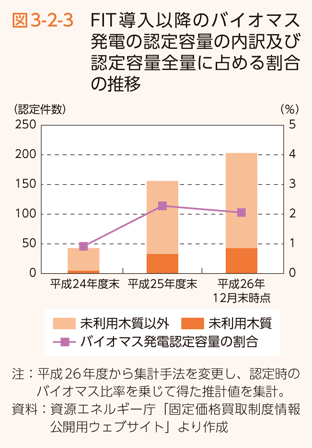
様々な効果が期待されるバイオマス発電事業を持続可能な形で導入するためには、配慮しなければならない点が幾つかあります。まずはエネルギーの効率です。未利用材を既存の発電ボイラーで使用する場合、製材工場等残材等と比べて含まれる水分が多いため、乾燥に多くのエネルギーを消費し、エネルギー効率が低くなります。また、FIT施行後に計画されたバイオマス発電は、未利用材を利用して採算が合うとされる5,000kW以上の大規模設備に集中しています。用地確保等の制約により発電時に発生する熱を有効利用する需要を近隣に確保できないため、エネルギー効率が20%程度と低くとどまる弱点も抱えています。
次に考えなければならないのが原料確保です。5,000kW級の大規模設備を稼働させるためには年間6~10万m3もの木質バイオマス燃料が必要になりますが、年間10万m3という規模は一県の年間木材生産量にも匹敵します。さらに、未利用材は、製材して様々な用途に用いられる素材の副産物も多く含まれているため、今後の未利用材の増産余地は限定されるとの試算もあります。
事業の継続のためには、長期にわたって価格・質・量の全ての面で求められる要件を満たした燃料を安定的に確保することが必要になります。もし未利用材の確保が難航し、安価な木質バイオマス燃料を輸入した場合、燃料の輸送に伴う温室効果ガスの排出が加わるなど、環境保全の効果が大幅に低下してしまいます。近年は原料の確保の見通しが立たないという理由で木質バイオマスによる発電の事業化を断念するケースもみられます(図3-2-4)。
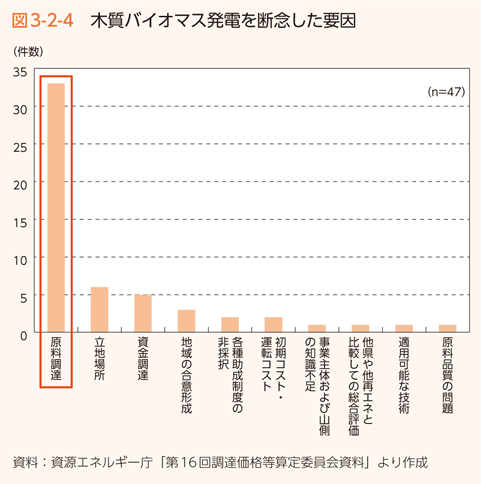
バイオマス発電を円滑に導入するために、今後は森林資源の持続可能性を考慮して木質バイオマス発電事業間の燃料の配分や林業、製材業、製紙業等との原料の配分についても整理しながら計画していくことが必要です。また、地域密着型の小規模熱電併給(コジェネレーションシステム)による木質バイオマス利用により、エネルギー効率を80~90%まで高めながら、限られた資源の効率的に活用することも必要です。国ではFITの制度内容の見直しも視野に入れつつ、小規模な木質バイオマス発電に推進に向けて、[1]森林整備の加速化・林業再生対策、[2]木質燃料製造施設やボイラー等の利用促進施設の整備、[3]サポート体制の構築や技術開発等に関する支援による利用拡大を図っています。
熱は熱で
国内の運輸・民生(家庭・業務)・産業分野で消費されるエネルギーのうち、7割程度が使われない熱(未利用熱)エネルギーとして環境中に排出されているという推計があります。また、この未利用熱の大半を占める150℃未満の熱の9割以上は、回収して発電等に利用することが困難とされています。
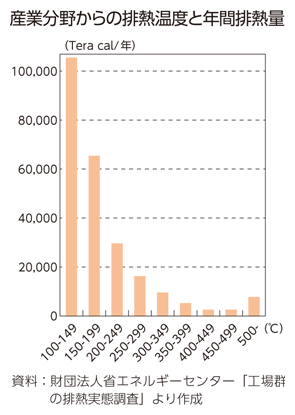
一方で、民生部門の最終エネルギー使用量のうち、約4割を占める家庭部門のエネルギー消費は、暖房や給湯といった数十℃レベルの比較的低温の用途が5割以上を占めるという特徴があります。現在こういった家庭部門の熱需要は、ほぼ全てが電力や化石燃料を使用し、熱に変換することによって賄われていますが、電力を熱エネルギーに変換して利用することは、発電時の効率まで考慮すると、投入する一次エネルギーの20~30%しか利用できていない計算となり、エネルギーの効率的な利用方法とは言えません。このことからも、エネルギーの効率的な利用に向けて、未利用熱エネルギーの活用が課題となっています。
その点で、産業等における比較的低い温度の排熱を家庭に導いて直接給湯や暖房に活用し、太陽熱システムや太陽光発電システム、地中熱を利用するヒートポンプシステム等の分散型電源を家庭に導入すれば、発電の際に生じる排熱等を家庭内の熱エネルギー需要に有効活用することが可能となるため、家庭における電力消費の節減が期待されるだけでなく、エネルギーの効率的な使用を通じ、CO2排出削減や資源の有効活用につなげることができます。
こうした未利用熱に着目し、その積極的な活用を図る動きが地域で見られます。例えば東京都は平成24年に「熱は熱で」というキャンペーンを開始し、平成26年から首都圏九都県市と民間企業・団体の共同キャンペーンとして、インターネット広告を制作して配信を行うなど積極的な普及啓発活動を行っています。
地域が抱える課題を地域の工夫で解決する
冬場の暖房の確保や融雪といった雪国ならではの課題について、地域に眠る未利用資源を利活用することによって、より低炭素な方法で解決でき、更には地域活性化にもつなげることができるとしたら―。
山形県最上郡最上町は、冬期の暖房用のエネルギー消費に関して、灯油が大きな割合を占めるという特徴があり、域外への資金流出が課題となっていました。そこで、同町は地球温暖化の原因となるCO2排出量を削減しながら、医院及びデイケアセンターを含む住宅団地の整備等から構成される「若者定住環境モデルタウン」を具体化し、人口減少に歯止めをかける構想を掲げ、平成26年7月に、国が実施しているグリーンプラン・パートナーシップ事業(以下「GPP事業」という。)の採択を受けました。
同町は、GPP事業を活用し、暖房用灯油の代替燃料として木質バイオマス(未利用間伐材)を活用した給湯・暖房の地域熱供給設備や地下水熱を利用した道路融雪設備の導入等を進めており、これらの一連の施策によって、地域のCO2排出量の削減(153トン/年)のみならず、新規雇用の創出(5人)のほか、燃料購入代金の域内留保(256万円/年)など持続可能な地域づくりの実現を見据えています。今後は一般家庭への導入促進を図り、更なるCO2削減につなげたいとしています。
GPP事業は、国が地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、地方自治体が策定する「地球温暖化防止地方公共団体実行計画」に計上されたプロジェクトの実現に必要な設備導入等を支援する事業です。こうした事業も活用しながら、それぞれの地域の特性や創意工夫も生かした地域やコミュニティと一体となった豊かな低炭素地域づくりの進展が期待されます。

ア エコツーリズム
(ア)エコツーリズムとは何か
地域の自然環境そのものを貴重な資源とみなし、歴史・文化も含めた地域固有の魅力も資源として捉え、地域ぐるみで観光旅行者に伝えて、活力ある持続的な地域づくりにつなげる取組として、エコツーリズムが挙げられます。国では、エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)に基づいてエコツーリズム推進基本方針を定めていますが、そこでは、エコツーリズムを推進する意義を、[1]自然環境の保全と自然体験による効果、[2]地域固有の魅力を見直す効果、[3]活力ある持続的な地域づくりの効果の三つの効果が相互に影響し合い、好循環をもたらすこととしています。エコツーリズム推進法では、動植物の生息地又は生育地その他の自然環境に係る観光資源と自然環境に密接な関連を有する風俗慣習その他の伝統的な生活文化に係る観光資源を「自然観光資源」として定めています。核となる自然観光資源について、現在国内で行われているプログラムの例を挙げてみると、様々なものが資源として活用されていることが分かります(表3-2-2)。こうして挙げてみると、中には意外と思われるものもあるように、普段は「観光資源ではない」と捉えられがちなものであっても、エコツーリズムによって活用することができると言えます。
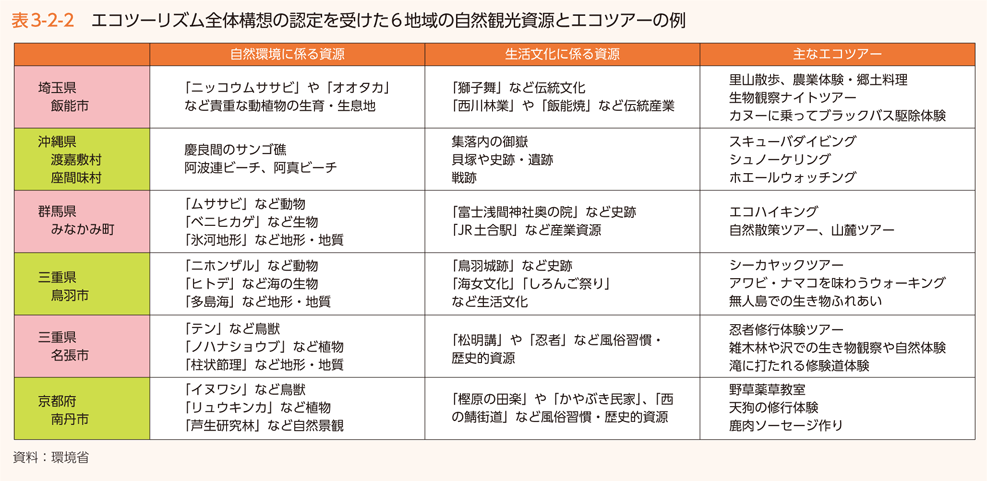
(イ)エコツーリズムによる地域活性化の可能性
財団法人経済広報センターが、国内3,000人の会員を対象として行った観光に関する意識・実態報告によると、国内の観光地を選ぶ決め手として、58%が「自然の豊かさ」と回答しています(図3-2-5)。加えて、訪日外国人消費動向調査を見てみると、我が国を訪問する外国人観光客が期待を寄せる日本観光の魅力として、「自然・景勝地」が食・ショッピングに次ぐ高さとなっています(図3-2-6)。この結果から、各地域が有する多様で豊かな自然環境には、国内外問わず大きな関心が寄せられており、地域活性化のための貴重な地域資源として、大きなポテンシャルを有していると言えます。
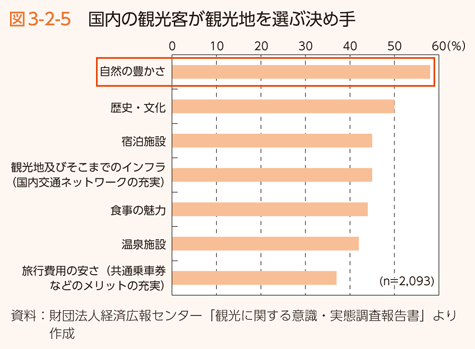
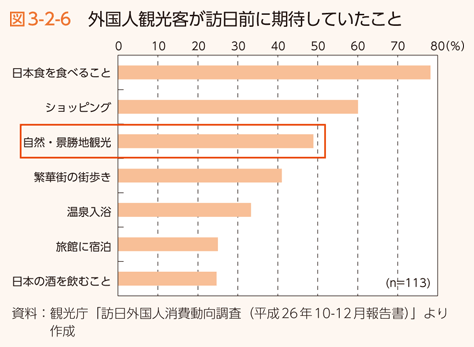
また、エコツーリズムによる地域づくりは、地域住民から賛同が得られやすいと考えられます。平成26年に実施した内閣府の「平成26年度環境問題に関する世論調査」によれば、エコツーリズムによる地域づくりに対する意識として、「自分の住む地域でエコツーリズムによる地域づくりを行いたいと思うか」という問いに対して「思う」とする回答が58.2%を占めました。都市規模別に見ると、「思う」とする者の割合は、東京都区部で53.0%、政令指定都市で61.2%、中都市で57.3%、小都市で55.7%、町村で65.2%と、小規模な自治体の住民ほど高いという結果となっており、地域活性化の手段としてエコツーリズムに期待を寄せていることがうかがえます。また、年代別では、「思う」とする回答が20代で72.5%と最も多くなっており、若い世代ほど関心が高いという点では、将来にわたってエコツーリズムを通じた地域活性化の取組の継続が期待できる結果となっています。
実際に、エコツーリズムの参加者は増加傾向にあると考えられます。例えば、里地里山の地域資源を生かしたエコツーリズムに取り組み、エコツーリズム推進法に基づく「全体構想」を策定して、平成21年に国による認定第1号となった埼玉県飯能(はんのう)市のデータを見ると、参加者数は上昇傾向にあり、それに比例してツアーの企画数も次第に増加していることが分かります(図3-2-7)。
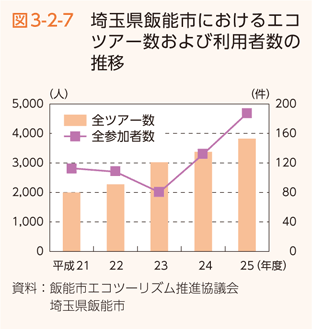
(ウ)エコツーリズムを実施することの目的・効果
平成27年3月に特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)日本エコツーリズム協会が同協会の会員に対して実施したアンケート(図3-2-8)によると、エコツーリズムに取り組む目的として、地域の活性化や観光の振興を挙げる回答が78%と最も多く、地域資源の有効利用や環境保護の推進がそれに続いています。
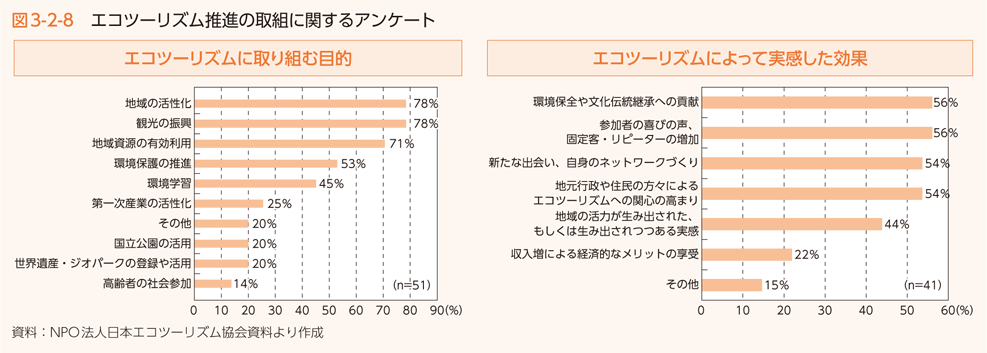
また、エコツーリズムによって実感した効果として、環境保全や伝統継承への貢献のほか、参加者との出会いや地元行政・住民の関心の高まりなどネットワークの強化に関する回答が約60%で並び、地域の活力が生み出された(生み出されつつある)実感が続く結果となっています。
このように、エコツーリズムは地域活性化も含めて様々な社会的効果を得られる手段として、その活用について注目が集まっていることが分かります。今後は、現在取り組まれている活動が更なる深化を遂げるのみならず、エコツーリズムの取組が全国的に普及・定着することも期待されます。
(エ)エコツーリズムの推進
ここまで見てきたように、エコツーリズムは自然観光資源の保全に配慮しながら地域の創意工夫を生かし、自然環境の保全、観光振興、地域振興、環境教育の場等として活用され始めています。
現在、国内の各自治体においては、地域発のエコツーリズムを企画するため、エコツアーに関わる事業者、地域住民、非営利団体(以下「NPO」という。)、専門家などや行政機関など多様な主体と協議会を組織して、自然観光資源を利用するにあたってのルールやガイダンス方法などを定めたエコツーリズム推進全体構想を作成する事例が広がっています。国では、各自治体の全体構想の申請を認定することで、その内容を広報しています。またエコツーリズム推進法においては、協議会がエコツーリズムに係る事業を実施するために必要な許可等の行政処分を求めた場合には、その事業が円滑かつ迅速に実施されるよう適切に配慮することとされるなどによりエコツーリズムの取組を後押しする規定も設けられています。
平成26年度エコツーリズム大賞
環境省では、平成17年度から、環境をテーマにした観光に関する取組の表彰を行っています。第10回目となる今年度は、農業経営の傍ら、長年にわたって、敷地内で持続可能な森林経営を目指した植林活動を実施し、また観光客向けの自然観察や森林散策などのツアーを開催してきた小岩井農牧株式会社が大賞を受賞しました。
同社の森林づくりによって、動植物の生息・生育数、種数が共に増加したのみならず、森林の防災や保水の機能にも注目が集まっています。また、この取組はその継続性のほか、農場のある雫石町だけでなく、周辺自治体のエコツーリズムと連携するなどして「環岩手山エコツーリズム」の核となっている点も評価されました。
同社は「小岩井農場物語」と題し、1891年(明治24年)創業当時の制服に身を包んだガイドが随行し、農場の歴史や文化の紹介や森歩き、畜産林業体験などを催行しています。同社の企画には平成24年から3年連続で全国から延べ3万人以上の来場があり、うち東北地方以外からの来場者の割合が約67%を占めています。ここから、ガイドツアーに参加された来場者によってもたらされる岩手県への経済効果は、年間でおよそ2.6億円以上と試算されています。

イ 国立公園の利用
我が国は、傑出した自然の風景地を自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づき国立公園に指定しています。平成27年3月に妙高戸隠連山(みょうこうとがくしれんざん)国立公園が新しく誕生したことで、国立公園の数は32か所となりました(写真3-2-1)。

国立公園は我が国の国土面積の約5.6%を占め、緯度や標高、地形等の変化により、それぞれ異なる自然の魅力を有しています。また日本の国立公園の制度は、国有地しかない米国等と異なり、国有地・公有地だけでなく民有地も含まれていることが特徴です。そのため、国有地・公有地等にほとんど手付かずの自然が残されているところがある一方、自然と人の暮らしが営まれていることの多い民有地では、その地域の織り成す歴史や文化、里地里山や草原等の人が利用することで維持されてきた自然にも触れることができ、そのことは日本の国立公園の大きな魅力の一つとなってきました。
国立公園には、年間延べ3億人を超える利用があります。国立公園を有する地域では、公園利用者が周辺の宿泊施設や公共交通機関、飲食店を利用することにより、経済波及効果がもたらされていると考えられます。例えば、阿蘇くじゅう国立公園の阿蘇地域には2万2千haもの広大な草原が広がっており、これは野焼きやあか牛の放牧等によって長い年月をかけて地域住民による農業の営みにより成立した自然です。当地には、平成25年には一年間で約1,600万人の観光客が訪れ、牧歌的な草原の風景やこの草原で育った地元名産のあか牛を使った食事を楽しんでいます。
また、観光立国を目指す我が国にとって、海外からの旅行者の獲得も重要な課題です。日本政府観光局(JNTO)の発表する訪日外客数は、平成24年の836万人から平成25年には1,036万人に増加しました。環境省の調査によると、訪日外客のうち国立公園を訪れた外国人旅行者数の割合は、平成24年の約22%から平成25年の約24%へと伸びており、平成25年に国立公園を訪れた外国人旅行者数は約256万人となりました。観光庁による訪日外国人旅行者を対象にした活動内容の満足度の調査では、活動実施率上位10種について、「日本の生活・文化体験」を期待以上だったと回答した割合が70.0%と、最も高い結果となっています。自然に関する活動においても、「自然・景勝地観光」は62.5%、「自然体験ツアー・農漁村体験」は66.2%と、期待以上と感じる外国人が多い結果となっています。このことから、訪日外国人による我が国の自然ひいては国立公園に対する関心の高さが推察されます。
さらに、国立公園別に見ると、平成25年に国立公園を訪れた外国人旅行者数のうち約4割が富士箱根伊豆国立公園を訪れており、これは平成25年に世界文化遺産に登録された富士山や箱根の国際的な知名度の高さによるものと推察されます。我が国の他の国立公園も富士箱根伊豆国立公園と同様に日本の優れた自然を代表する傑出した風景地であり、観光資源としてのポテンシャルが高いことから、その魅力を国内外に一層積極的にアピールすることにより、利用者数の更なる増加が期待できます。
上述したように、国立公園は、豊かな自然環境を保全すると同時に、その自然資源を持続的に活用する場となっています。今後は、地域と協働した管理運営を行うことで、地域ごとの実態に即したきめ細やかな利用サービスを提供する魅力ある国立公園の創設を目指していきます。加えて、地域の自然の魅力を維持しながら、より多くの観光客を獲得することで、国立公園を持続的に自然観光資源として利用していくことが可能となり、長期的な消費の増大や雇用の創出も期待できます。この機能を更に効果的なものとするためにも、国立公園管理に携わる国と地域の人々が、利用実態、課題等の情報を共有し、共通の目標を持ちながら連携することで、それぞれの特徴を生かした取組を協働で進めることが重要です。
こうした中、国では国立公園の戦略的活用に向けて、インターネット等を活用した宣伝や、四季折々の美しい国立公園の風景を毎月楽しむことができるカレンダーの作成等を行い、広くアピールを行っています。2020年(平成32年)には、第32回オリンピック競技東京大会・第16回パラリンピック競技東京大会(以下「2020年東京大会」という。)の開催を控え、更なる訪日外客数の増加が見込まれます。このため、外国人利用者に対する受入れ体制の強化策として、「人と自然の共生」という日本の国立公園の特徴を生かした外国人向け利用プログラムの開発や地域におけるネットワークの構築などの地域による外国人の受入体制づくり、イベントの開催といった取組の充実を図っていきます(図3-2-9)。また、国立公園整備に関係する団体、事業者等に対し多言語対応ガイドラインを周知する等、国立公園の標識やビジターセンター等の多言語対応を推進しています。これらの取組を総合的に進めることは、国立公園による観光面からの地域経済への更なる貢献が期待できるだけでなく、地域の人々が自分の地域の自然に触れることで、地域の魅力を再認識し、誇りを持つという、地域活性化における重要な要素を生み出すことが期待できます。

第1章第2節1でも述べたとおり、シカやイノシシといった野生鳥獣による農作物被害が深刻化しています。中国山地の山間にある島根県邑智(おおち)郡美郷(みさと)町も農作物被害に悩まされてきた町の一つですが、同町はこの状況を逆手にとって、地域の活性化につなげています。
野生鳥獣による農作物被害は、特に山間地域において、かねてから大きな懸案となってきました。かつては害獣の進入を防ぐ目的で木や竹などを組み、石を積み上げるなどして、山と農地との間に「シシ垣」を築く文化も見られました。しかし、国の推定では平成元年に約25万頭だった全国のイノシシの生息数が、平成24年度末には約89万頭にまで増加しています。一方で、有害鳥獣捕獲等によって得られるイノシシの肉については、食品衛生法により、捕獲した個人が許可なく販売できません。そのため、狩猟者自身が自家消費する以外は、大半が廃棄物として焼却するか、埋設するなどして処理せざるを得ず、有害鳥獣の捕獲が進まなかったという面もあります。
こうした中、美郷町では住民が主体となり、猟友会のみならず、農家や自治会関係者も巻き込んで、平成16年に「おおち山くじら生産者組合」を結成しました。同組合では、地域の多様な主体が連携・協働してイノシシの捕獲・解体から販売までを手掛ける仕組みづくりを行い、6次産業化を図っています。組合は休止中であった町内の既存の鴨肉処理施設を再活用するとともに、当該施設に対して付与されていた食品衛生法上の許可を「食鳥」から「食肉」に変更することにより、捕獲したイノシシの解体処理を行って、精肉に「おおち山くじら」というブランドを名付けて、ジビエとして販売を行っています(図3-2-10)。他にも美郷町内の女性グループが中心となって、イノシシの皮革製品への加工・販売、惣菜や弁当の販売も行っており人気を集めています。

これらの取組の結果、捕獲したイノシシを活用できた割合(食肉や皮革として活用したイノシシ数÷捕獲したイノシシ数)を示す「資源利用率」は上昇傾向にあるだけではなく、イノシシ関連の売り上げも平成26年度見通しで1,000万円を超えることが見込まれています(図3-2-11)。また、美郷町によれば、町にもたらされたのは経済効果ばかりではなく、町が抱える問題に主体的に取り組もうとする住民の意識の変化もあったとしています。その一例として、美郷町でも高齢化と人口減少が進む中で、町内で狩猟免許を取得してイノシシの駆除に当たる人員はここ10年で、ほぼ一定数で推移してきています。このように、美郷町は害獣をブランド化し、有効活用するという逆転の発想で、地域の活性化に取り組んでいます。
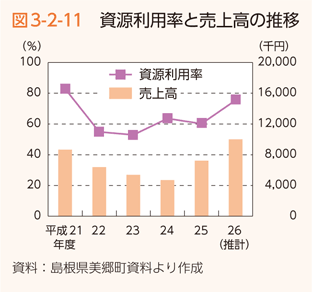
生きものの力で引き出す地域の活力
各地域に生息・生育する希少種を地域の象徴として取り上げ、それを地域資源として地域の産品のブランド力を強化する取組は、その地域の生産農家の所得を向上させ、個性的で魅力的な地域づくりに寄与するだけでなく、地方や県という物理的な距離を越えて、波及効果を生み出す可能性があります。
長崎県の対馬では、平成21年に地元の農家等がツシマヤマネコとの共生を目指し、「佐護ヤマネコ稲作研究会」を立ち上げました。同研究会では、環境保全型農業を実施し、生産したお米を「ツシマヤマネコ米(以下「ヤマネコ米」という。)」としてブランド化しています。一方、栃木県那須町にある那須どうぶつ王国では、ツシマヤマネコの保全に協力するため、平成26年から園内のレストラン「ヤマネコテラス」において、ヤマネコ米を使用した料理を提供しています。那須どうぶつ王国では、ヤマネコ米を使用することによってレストランの売上げ自体が増加する効果があったことから、対馬におけるヤマネコ米の年間生産量の2.8トンを超える3トンを毎年購入する契約を生産農家と結び、持続可能な営農を支援しています。
このように、ヤマネコによりブランド化された米の流通を通じて、ツシマヤマネコの保全に貢献したいとする両者にとってメリットのある関係が築かれています。

ア 自然環境と地域文化との共存
地域文化の中には、自然環境と人間の長きにわたる共存関係によって育まれて来たものがあります。例えば、今でも日本各地に存在する「鎮守(ちんじゅ)の森」は、その地域文化が表現される場所の一つです。私たちは鎮守の森と相対するに当たり、古くから「山や森や林には神が鎮(しず)まるという特有の感覚」と「信仰を越えた畏れと慎みの心」をもって接してきました。こうした鎮守の森がいま地域活性化にとって重要な役割を担いつつあります。
例えば、鎮守の森は、神社の創建等を通じた人々と信仰をつなぐ場としてのみならず、人間相互の寄り合いや自治の場となったほか、周辺で開催される「市」を通じた経済的機能や「寺子屋」などのような教育機能を担い、様々な面から地域コミュニティを支える場となってきました。また鎮守の森では定期的に「神事や祭り」が催され、祭りは地域のエネルギーを結集し、住民の結束を高める求心力としての機能も果たしているとされています。
京都市にある下鴨神社境内の糺(ただす)の森は、12万m2(東京ドーム3個分)ほどの、賀茂川と高野川の合流地点に発達した原生林で、平成6年には下鴨神社と一体で世界文化遺産に登録されています(写真3-2-2)。下鴨神社には推計で年間32万人が訪れ、隣接する糺(ただす)の森では祭事のほか、納涼古本まつりや音楽コンサートが開催されるなど、観光客のみならず地元の人々も多く訪れる憩いの場として、賑わいを見せています。糺(ただす)の森は過去の火災や開発等によって規模の縮小を余儀なくされる場面もありましたが、地域住民による保護活動等が展開され、現在見られる森の姿は明治時代の半ば頃から保たれてきたと言われています。
毎年5月、糺(ただす)の森を舞台として、上賀茂神社・下鴨神社の例祭「葵(あおい)祭」の祭事が開催されます。その装束や牛車などには、祭の名前にもなっているフタバアオイが飾られていますが、これは上賀茂神社・下鴨神社の御神紋であり、神と人を結ぶ神聖な植物とされています。葵(あおい)祭は「祇園(ぎおん)祭」や「時代祭」と並んで京都の三大祭と称され、例年約8万人が観覧に訪れています(写真3-2-3)。葵(あおい)祭が有する潜在的な能力について、民間の試算によれば、平成20年(2008年)3月時点でのソーシャルキャピタル(信頼に裏打ちされた社会的なつながりあるいは豊かな人間関係)の価値は931億円にも上るとの結果になっています(表3-2-3)。このように糺(ただす)の森と共に歩む葵(あおい)祭の関係は、京都市地域にとってかけがえのない貴重な地域資源となっていると言うことができます。


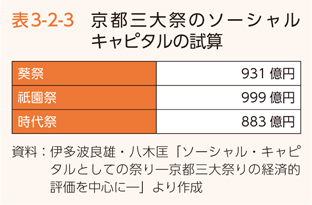
また、鎮守の森が持つ機能に着目すると、フクロウ類や巨樹・巨木のような、地域の守り神とみなされる動植物の生息・生育の場として生物多様性の維持に寄与してきました。また、國學院大学の調査によれば、鎮守の森に生育する樹木は、一般の森林で生育する同程度の樹木に比べてCO2蓄積量が3.3倍も多く、地球温暖化防止にも役立つことが分かっています。
このように、鎮守の森には、原生林等の自然的特性、神社等の歴史的特性、神事や祭り等の文化・社会的特性という、複合的な地域資源の要素を備えています。さらに最近では、国内の多くの地域で、鎮守の森が地域コミュニティの拠点として再認識され、自然環境と地域文化の関係性が見直されつつあります。各地で鎮守の森を核として祭りや神事が継承・再興され、地域の祭りが活発な場所においては、若者がその地域にとどまり、地域に戻ってくる割合が高いという指摘もあります。さらには、鎮守の森が持つ独特の雰囲気を生かして高齢者向けの健康・福祉のための森林療法の場とする研究がみられるなど、地域活性化のツールとして幅広い機能を発揮することが期待されています。
イ 自然の恵みを生かした地域づくり
私たちの暮らしは、豊かな飲み水、きれいな空気、食料や資材、自然の上に成り立つ特色ある文化やレクリエーションなど、森・里・川・海やその連環が形成する豊かな自然の恵みによって支えられています。こうした自然の恵みは地域の資源と捉えることができ、それらを活用することにより、地域ならではの文化・風土に即した独自の豊かさの実現につながる可能性があります。第1章で示したとおり、それぞれの地域が生み出すモノやサービスの付加価値を高めていくことが求められる中、特に地域の自然とのつながりが深い農林水産業や観光業においては、自然の恵みを地域資源として、地域産業や地域そのものもブランド化し活用できる可能性を秘めています。本項では、自然の恵みを地域資源として活用し、環境の保全と利用を両立させ、地域における魅力の再発見と豊かな暮らしの実現につなげている事例を紹介します。
豊岡市は、昭和46年に我が国で野生のコウノトリが絶滅する前、最後に生息していた土地です。豊岡とその周辺地域では、古くからコウノトリを「ツル」と呼び、めでたい鳥「瑞鳥(ずいちょう)」として愛でるなど、コウノトリがいる暮らしを当たり前のこととして受け止めてきました(写真3-2-4)。コウノトリも住めるような豊かな自然と、コウノトリを自分たちの暮らしの中に受け入れるおおらかな文化とが一体となって、豊岡市の独自の風土が形成されてきました。
国内の野生のコウノトリが絶滅する6年前から、市民の声を受け、豊岡市はこの豊かな自然と文化の関係を再び築き上げるために、兵庫県と協力して人工飼育を行ってきました。平成27年2月時点で、飼育下の約100羽に加え、70羽を超えるコウノトリが自然の中で暮らしています。コウノトリが自然の中で生きていく上で、魚類やカエル、バッタ等の餌となる生物が多く生息できる水辺環境が保全されている必要があるため、豊岡市では国、兵庫県と連携して河川の自然再生や休耕田を活用したビオトープの設置等を行い、水田・河川・湿地等のネットワーク化に取り組んでいます。

そうした背景の下、豊岡市では、コウノトリに代表される地域独自の自然の恵みを資源とした様々な取組が行われています。そのひとつが、「コウノトリ育(はぐく)む農法」と呼ばれる環境創造型農業の普及に向けた取組です。この取組では、コウノトリ野生復帰を営農分野で支えるという明確な意識を持ち、地域のシンボルであるコウノトリの保護を始めとした生物多様性への寄与により生産物の付加価値を高め、それにより「米の生産」と「生物多様性の保全」を同時に実現しています。この農法で栽培された米は、通常の慣行農法に比べ無農薬では2倍、減農薬では1.6倍の価格で販売されますが、平成22~24年に生産された米はすぐに完売するなど大変な人気を集めました。
この農法の特徴は、減農薬・無農薬で米の栽培を行うことに加え、田んぼで様々な生きものを育むために、冬期や早期に湛(たん)水し、栽培期間中も深水管理を行うことにより、ドジョウやカエルといった多くの生きものの生息に役立っています。中でもオタマジャクシがカエルに変態するのを農家が確認してから、落水する「中干延期」は生きものを育む特徴的な取組となっています。このように農家が生きもの調査を実施することを栽培要件としている点が最大の特徴です。菊地らが平成24年に実施した聞き取り調査によれば、生きもの調査を実施することで、農家自身が田んぼでは米だけでなく様々な生きものが育まれていることを実感でき、この農法を継続しようとする動機につながっているとされています。同農法による作付面積は平成15年度の0.7haから、平成26年度には約300haまで拡大し、近隣市町村にもその取組が広がりつつあります(図3-2-12)。農業者はこの農法を通じ、経済的な利益が得られることはもちろん、地域の自然やそれを支える自らの取組に誇りを持つことで、環境保全にも意欲的に取り組む姿勢が広がっています。
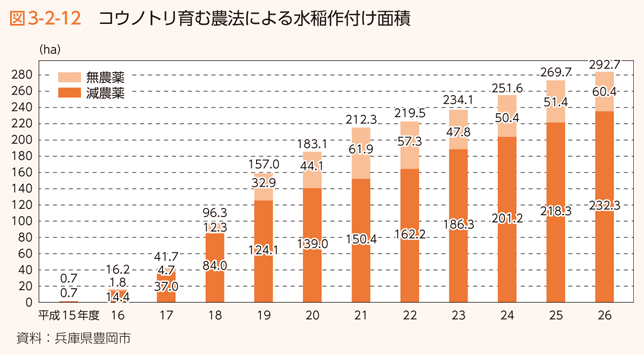
また、豊岡市は、コウノトリ野生復帰の取組をエコツーリズムにも活用しています。コウノトリを見るために豊岡市を訪れる観光客の数は平成17年のコウノトリ放鳥後に急激に増え、コウノトリを間近に観察できる兵庫県立コウノトリの郷公園は、平成17年度に約17万人だった来場者数が現在では約30万人になっています。また、同公園訪問と合わせてコウノトリ育むお米を味わうツアーや、湿地の清掃・除草・外来種駆除などの保全活動等で野生復帰に貢献するボランティアツーリズムなど、国内はもとより、アジアを中心に世界各国からの環境学習旅行を受け入れています(写真3-2-5)。慶應義塾大学の大沼教授らによる推計では、観光客の増加による経済波及効果は年間10億円程度(平成21年時点)になると試算されています。

このように、コウノトリも住めるような豊かな自然と文化を再構築してきた豊岡市は、「穏やかに響きあう いのちと地域」を目標として、平成25年9月豊岡市生物多様性地域戦略を策定し、生きもののバランスだけでなく、地域社会全体の在り方を考える中で自然との共生に取り組んでいます。
地域産業が支える循環関係
広島県東広島市の西条地域は、里山の麓に位置し、良質で豊富な湧水に恵まれた地域で、この里山と水と田の恵みを受けて、酒づくりが地場産業として営まれてきました。水と米を原料とする酒づくりにとって、里山や農地の保全は地場産業のために必要不可欠です。西条酒造協会は、その保全と酒づくりを結び付けて、里山の資源を活用し、美しい風景を保全することにより、地域の伝統文化産業が生きていく必要があると考え、平成13年5月に自ら中心となって「西条・山と水の環境機構」を設立しました。
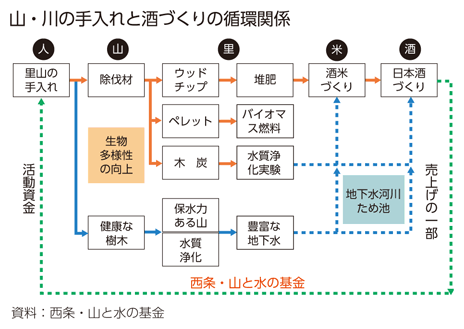
酒造協会会員の造り酒屋が酒1升の売上げごとに1円を拠出して基金を作り(年間約600万円)、それをもとに、流域の里山林整備活動団体への報奨、環境教育、調査研究等の活動を展開しています。事業の方向付けと決定は、酒造協会関係者と行政、市民、大学関係者で構成される理事会及び運営委員会が行い、活動は西条・山と水の環境機構を事業主体とし、産官学民の協働によって行われています。水源涵養のための山の手入れで出るバイオマスは、発酵して酒米づくりの水田の肥料にし、その米を酒づくりに活用しており、経済も資源も循環する仕組みとなっています。
同機構は、地場産業からの出資により設立されたファンドを母体とし、明確な目的と分かりやすい地域貢献効果、事業者を中心とした安定的な運営組織により、多数の参加者・賛同者を得て継続的に活動を行っています。同機構が山のグラウンドワークとして行っている除伐、間伐等の森林整備活動は、高校生、大学生、企業、地元の人々、ボランティア団体の交流の場となるとともに、森林整備活動参加のきっかけづくりの場としての役割を果たしており、そこへの参加者及び参加グループは増加傾向にあります。また、この活動が行われている龍王山では、10年間で水質の悪化がほとんど認められなかったほか、降雨の少ない冬季の表層水が増加する傾向が認められ、森林整備活動により山の地下水涵養能力が増加している可能性が示唆されるという調査結果が出ています。
このように、地域の豊かな自然とそのつながりを再認識し、恵みを享受しながらそのつながりを広く支え合うことは、持続可能な地域づくりのカギであり、地域の活性化にも資するものです。
自然を生かした住み良いまちづくり~上水道普及率0%の町・写真の町、東川町~
北海道の最高峰「旭岳」の麓、旭川空港からおよそ7kmに位置する上川郡東川町は、近年移住者が増加しています。同町の人口は、平成5年度に6,973人まで減少しましたが、平成26年度には約7,967人へ増加しており、平成5年から平成26年までの社会増の合計は1,575人に上ります。平成24年に東川町役場が約130名の移住者等に対して実施したアンケート調査によると、「東川町を移住や複数地居住に選んだ理由」の中で、「とても大きな理由」及び「まあ大きな理由」として多く挙げられたのは、「自然が保たれている」の75%、「独特な景観、風景がある」の71%でした。他にも、「美味しい地下水」を挙げる意見も多く見られ、水や豊かな緑、景観などの自然の恵みを生かしたまちづくりが、住み良い町として移住先等に選ばれている背景となっています。
そんな東川町は、「上水道普及率0%」という全国でも珍しい町です。なぜなら東川町の地下には、旭岳を含む大雪山連峰からの雪解け水がしみ込んだ地下水源が張り巡らされており、各家庭から地中に20mほど管を打ち込めば、無料で塩素消毒なしで飲める地下水を利用することができるからです。この地下水はミネラルが豊富に含まれるのみならず、カルシウムとマグネシウムの配合バランスが、ミネラルウォーターの理想とされる2:1に近く、環境省の「平成の名水100選」に選定されるとともに、商品化もされています。こうした高品質な天然水は、地域内の豆腐や味噌、米づくりなどにも生かされ、「東川米」の栽培にも不可欠な要素となっています(地域名をブランドに冠したお米は、全国でも魚沼産コシヒカリと東川米の2例のみ)。
また、東川町は、昭和60年に「写真の町」宣言を行い、「写真映りの良いまちづくり」を進めてきました。平成18年には景観法に基づく景観計画を策定し、大雪山の山並みと調和する緑豊かな住宅景観を目指しています。具体的には、町と同計画で定められた景観協定区域内に住居を建築する者との間で「建築緑化協定」を結ぶことで、外観等に一定の統一性と美しさを確保し、街並みとしても優れた住宅景観の形成を推進しています。このほか、平成6年から開始された「全国高等学校写真選手権大会」(通称:写真甲子園)では、全国から3万人もの人が東川町に集まります。このうち、大会に参加する高校生達が町民の住居でホームステイを行うなど様々なイベントを通じて町民との交流が図られています。このような豊かな自然や美しい景観を生かしたイベントも、重要な地域資源の一つと言うことができます。
東川町のまちづくりの取組に共通するのは、「他の地域がやっていない、新しいことをやろう」という発想です。このように開拓精神に基づいて、自然の恵みを生かしながら、住民の生活の質を高める取組が、その他の様々な地域においても進むことが期待されます。

持続可能な地域づくりを行っていく上で、市民・住民により構成され、その地域を支える地域コミュニティの存在は重要です。しかし、第1章第1節でも見てきたとおり、我が国では人口減少等に伴い、自治会や町内会といった地縁型の地域コミュニティが衰退してきていると言われています。
一方、千葉大学の研究で、平成19年に全国の市区町村を対象にコミュニティ政策に関するアンケートを実施したところ、「地域コミュニティづくりの主体として今後特に重要なもの」として、「自治会・町内会」、「住民一般」が多く挙げられており、人口30万人以上の都市では、それらに加え「NPO」の割合が高いとの結果が得られています(図3-2-13)。また、公益財団法人北海道市町村振興協会が道内の市町村に対して平成18年に実施したアンケート結果では、「これまで地域活性化を担ってきた主体」として「行政」を挙げる割合が高い一方で、「今後、地域活性化を担っていくことを期待する主体」については、「行政」の割合が大きく低下し、「森林組合等の組合・連合会」、「NPO 等の市民団体」、「商工会・商工会議所」及び「事業者、企業」の割合がそれぞれ40~50%となりました(図3-2-14)。このように、行政以外の主体が地域の活性化を担うことへの期待がうかがえます。
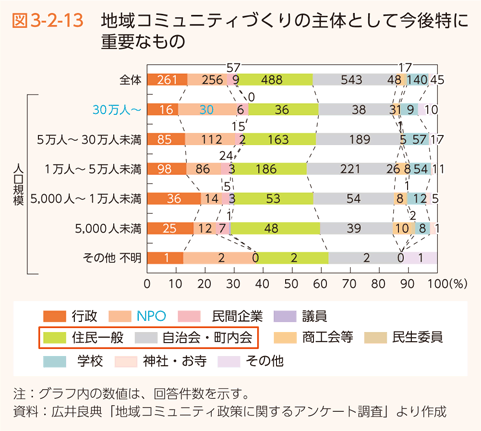
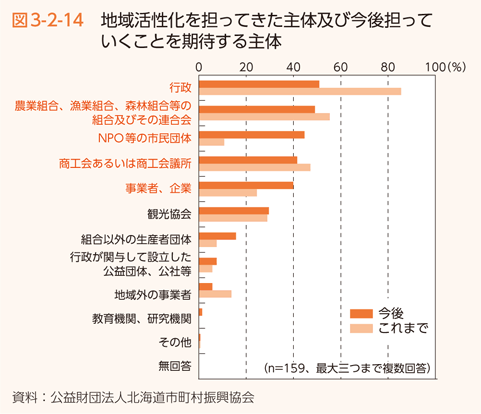
第1章第1節で述べたとおり、地方自治体の財政状況が悪化する一方、人口減少が進むことが予想される中で、地域コミュニティづくりや地域活性化を行っていくには、行政だけでなく、こうした地域の多様な主体の参加・参画が、より一層重要になると考えられます。
以下では、そうした地域の様々な主体が、「環境」を切り口とした活動を通じて、地域の活性化に貢献している事例を紹介します。
ア 食品残さの循環による地域の循環型社会づくり
我が国は、1年間に約1,728万トンの食品廃棄物を排出しています(平成23年度推計)。これは、国内及び海外から調達された食用の農林水産物計約8,400万トンの2割に相当します。この食品廃棄物のうち、約77%に当たる約1,331万トンが焼却・埋立て処理されています。このため、環境負荷の軽減のみならず資源の有効活用という観点からも、食品廃棄物の削減と有効活用は大きな課題です。こうした課題を解決するためには、各地域の消費者が食品廃棄物の現状を知り、それを減らそうと意識し行動していくことが重要です。しかし、環境省の調査によれば、調査対象者のうち、環境問題の中でも廃棄物関係の問題に関心があると回答した人は2割程度となっており、地球温暖化(約68%)、大気汚染(約49%)よりも低い水準にとどまっています(図3-2-15)。
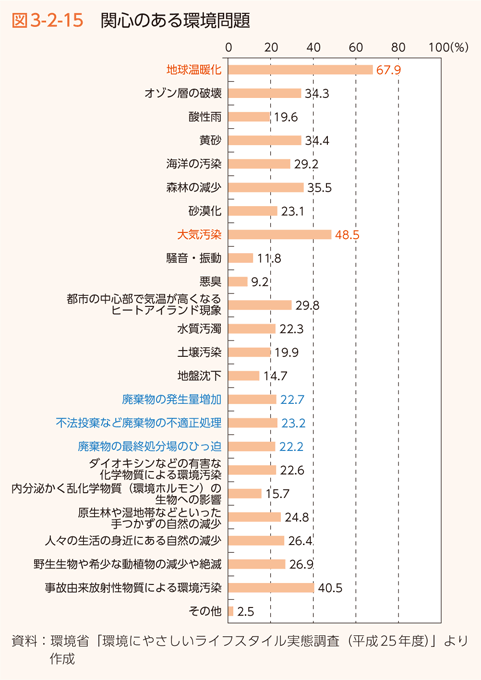
こうした中、愛知県名古屋市では、消費者である市民に食品廃棄物の資源循環について啓発し、その発生を抑制するための意識を醸成する「おかえりやさいプロジェクト」という取組が行われています(図3-2-16及び写真3-2-6)。200万人を超える人口を擁する名古屋市では、かつて市民が出すごみの量が年々増加しており、平成10年度には年間100万トンに迫っていました。同市は当時、名古屋港内にある藤前(ふじまえ)干潟を新たな埋立地とすることを検討していましたが、藤前干潟は渡り鳥の飛来地として重要であったことから、市民から反対運動が起こり、その結果、埋立計画は中止に至りました。そこで、名古屋市は「ごみ非常事態宣言」を発表し、「2年間で20%、20万トンのごみを減らす」ことを呼び掛けました。市民がごみの分別を徹底するなどした結果、平成12年度には、ごみの量を約3/4の76.5万トンに減らすことができました。
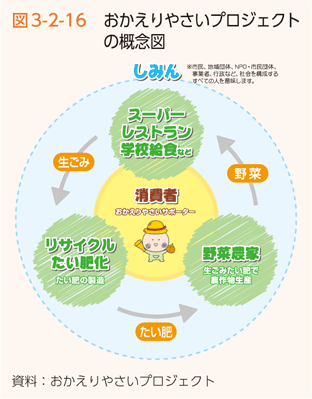

こうした経緯を踏まえ、市民等が参加する「なごや循環型社会・しみん提案会議」を始め多様な主体が議論を行い、その提案を受けて、名古屋市はごみの減量化をより明確な目標に据えた一般廃棄物処理基本計画を策定しました。その計画の策定会議に参加した市民を母体として、NPO法人、主婦や会社員といった地域住民、小売業者・ホテル等の企業、ごみ収集運搬業者、堆肥化事業者、生産農家、大学、名古屋市といった地域の産学官民の協働によっておかえりやさいプロジェクトが平成20年に発足しました。
このプロジェクトでは、スーパーマーケットやレストラン、ホテル、学校等から発生する生ごみを収集運搬業者が回収し、堆肥化事業者の施設で堆肥にします。その堆肥を使って愛知県及び近隣県の農家が野菜を作り、その野菜を「おかえりやさい」というブランド名でスーパーやレストラン、ホテル、学校に卸します。生ごみ循環の輪をつなげて可視化することで、消費者による食品資源循環のプロセスへの理解と食品廃棄物を減らそうという意識の醸成が促進されます。また、年2回、学校給食でおかえりやさいを「みんなで食べるなごや産の日」のメニューとして提供するとともに、生ごみ資源化の意義についての説明を献立表にも記載して、大人のみならず子供に対しても食品資源循環や地産地消等の食育を行うなど、本プロジェクトでは様々な活動を実施しています。
このような多様な主体の活動による食品残さの減量化及び循環の取組は、第3章第2節の冒頭で説明した地域資源を有効に活用している事例です。その地域の地域資源である人的資源(人材)を活用し、付随的資源(中間生産物)である廃棄物を生かして、地域の循環型社会形成に役立っています。今後、おかえりやさいプロジェクトに参加する市民や企業、行政、大学といった地域の多様な主体により、地域ブランドの確立による地域活性化、地産地消(フードマイレージの削減効果)や旬産旬消(生産・流通に関する環境負荷低減)が進むことが期待されるとともに、他の地域でも同様の取組が行われることにより、各地域での地域循環圏の構築が期待されます。
イ 「市民・地域共同発電所」による地域の活性化
本章第2節でも触れたとおり、我が国では、防災・減災の観点から再生可能エネルギー等によりエネルギーを自立・分散的に確保できる体制を整えようとする地域の取組があります。こうした取組の一つに、太陽光等の再生可能エネルギーを使った「市民・地域共同発電所」の取組があります。この取組は、市民から募った出資金や寄付金等を元に、民間企業等が発電事業を行うものであり、海外でも、デンマークやドイツ等においてこうした取組が見られます。近年、我が国でも増加しており、平成25年8月現在、全国に458基、総出力は5万1,641.4kWとなっています(図3-2-17)。
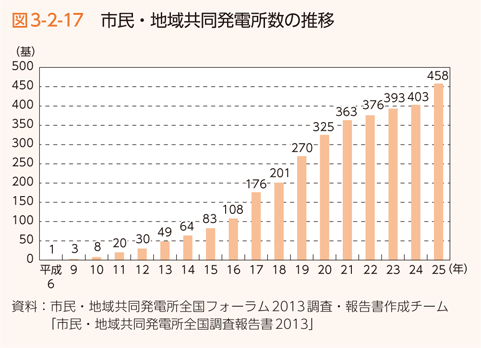
近年では、再生可能エネルギーを生産して得られた利益をその地域に還元することで、地域の活性化を図る市民・地域共同発電所もあります。その一つとして、滋賀県の東近江市において、八日市商工会議所と東近江商工会が地域の商店街を始めとするコミュニティと連携して実施している「東近江市Sun讃(さんさん)プロジェクト」が挙げられます。
本プロジェクトでは、八日市商工会議所と東近江商工会が共同出資して設立した株式会社Sun讃PJ東近江が、市民に対し私募債を発行します。その資金を元に太陽光パネルを設置し、そこで発電した電気を売電して、得られた利益を地域商品券の形で私募債購入者に還元します。地域で生み出された利益をその地域に還元することで、地域経済を活性化させる枠組みとなっています(図3-2-18)。
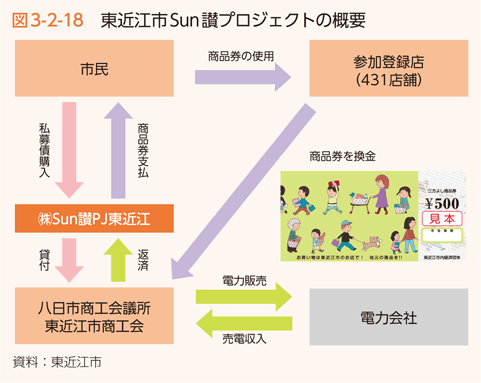
平成25年に運用を開始した「ひがしおうみ市民共同発電所3号機」は、発電容量約40kWの太陽光発電システムであり、太陽光パネルを公共施設である滋賀県平和祈念館の屋上に設置しています(写真3-2-7)。設置費用計1,620万円については、1口15万円で3期にわたり募集し、85名の市民が私募債を購入しました。年間発電量は約4万5,000kWhで、毎日の発電量は、民間企業が提供するインターネットサービスを利用して、誰でもパソコンやスマートフォン等から確認できるシステムを平成27年4月から運用しています。また、災害時にはこの施設自体が独立した電源となるなど、非常時の防災拠点としても機能します。

一方、これまで行われてきた市民・地域共同発電所事業では、分配金が現金であったために使途が限定されず、その地域以外で消費されてしまう可能性がありました。しかし、本取組では、分配金を地域・使用期間限定の地域商品券として市民に還元しているため、市外には流出しないようになっています。この商品券は、地域の参加協力店431店舗で利用できるようになっています。これにより、東近江市内での消費を促し、資金を地域内に循環させて地域経済の活性化を図っています。
このプロジェクトでは、今後も市民・地域共同発電所の増設や住宅の屋根への太陽光パネル設置等を推進することで、再生可能エネルギーの普及を通じた市民参加型の地域振興を進めていく予定です。太陽光という自然資源を生かして、地域の循環型経済モデルを構築するとともに、地球温暖化の防止、防災拠点の整備、地域住民への普及啓発にもつながる「東近江市Sun讃プロジェクト」は、市民・地域共同発電所が地域活性化を促すという好事例です。
ウ 十津川(とつかわ)村の自然を生かした住民主体型の地域の活性化
持続可能な地域づくりの担い手は、市民一人一人です。個人一人一人が持続可能な地域づくりに参画していくことはもちろん、普段の生活でも、様々な行動を環境に配慮したものに変えていくことが、結果的に地域の活性化及び持続可能な地域づくりにつながります。ここでは、そうした個人一人一人の意識を変えることにより、地域が活性化した一例として、奈良県吉野郡十津川村の事例を紹介します。
十津川村は奈良県の最南端に位置する人口約3,700人の村であり、吉野熊野国立公園の一部を成しています。その面積は東京23区全体の面積(約622km2)よりも大きい約672.4km2であり、その約96%が森林です。近隣の街から車で約2時間を要する山深い村であり、林業、建設業及び観光業が主たる産業となっています。近年、我が国には安価な外国産の木材が大量に輸入されています。その影響を受けて国産材の価格は低迷を続けており、我が国の林業経営を取り巻く情勢は大変厳しくなってきています。これは十津川村でも同じ状況であり、地域の方々にとって、「山はそこにあるもの」、「木材は売れないもの」という意識がありました。しかし、地域コミュニティの主体である村民が地元の廃校となった校舎の活用を巡って議論を重ねていくうちに、村民自身に地域の自然を活用した地域活性化を考える意識が醸成されていきました。そこで、村民が村や奈良県と話し合った結果、木造の廃校と民家を活用し、都市部生活者を過疎地に呼び込んで、大自然の中でゆっくりと流れる時間や、人と交流することによる癒しを提供することとしました。また、非常に広大な村内の森林そのものを地域資源とするべく、十津川村は「日本一酸素供給の村」というキャッチコピーを用いた広報を行いました。
これらを平成21年度に実施した結果、村を訪れ宿泊した観光客数が、広報の前には500人から多くても2,000人程度であったところ、平成22年度には約4,500人に増加しました(図3-2-19)。その翌年は大型台風により村が被害を受け、3,000人ほどに減少したものの、その後は4,000人前後で推移しています。こうした取組を通じて、今日では、当たり前のように目の前にある山林やそこから得られる木材を始めとした地域の自然資源に対し、都市部の人が価値を見いだしていることが地域住民の間でも共有されています。現在では、森林組合、木材・製材加工業者、森林所有者、村役場等の公共団体などの多様な主体が協働して林業の6次産業化を進めており、都市部のビルダー(建築家)と連携して木材生産から製材品の加工流通まで行う産直住宅ネットワーク「十津川郷土の家ネットワーク」を構築し、村内の森林保全活動と林業の活性化が進められています。また、自然に密着した地産地消・旬産旬消の暮らしそのものを観光資源としており、例えば、都市生活を送る消費者向けの農家民宿での体験型のホームステイも、地域住民主導で実施しています(写真3-2-8)。この結果、「暗い天体も観察可能な星空」という地域条件や自然資源、「地元限定で栽培する野菜」という特産的資源等の価値を地域住民が再認識するなど、個々の村民に意識の変化が見られます(図3-2-20)。
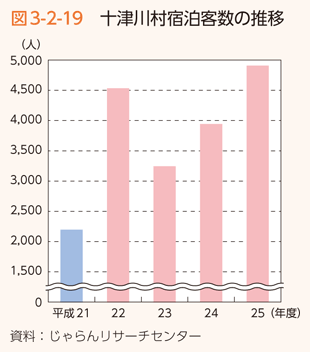

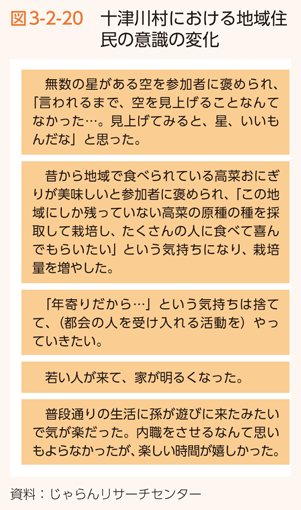
このように、地域コミュニティの担い手である住民自身が、地域の自然資源の保全と活用に対する意識を高く持ち、地域の活性化を地域住民自身が考えて、地元自治体を含む多様な主体と協働することで、地理などの地域特性資源、自然資源、文化・社会資源、人的資源及び情報資源を有効活用していくことは、持続可能な地域社会を構築していく上で重要と考えられます。
ア 鳥獣被害に対する若手ハンターの活躍
近年その数が増加し、日本の自然環境や農林業に大きな被害を与えているシカやイノシシといった野生鳥獣への対策の一つとして、捕獲の強化は重要です。しかし、第1章第2節でも述べたとおり、我が国で狩猟免許を受けた狩猟者は、平成24年現在延べ約18万人であり、昭和50年と比べると約1/3になっています。また、50代以上がその8割超を占めているなど、高齢化も深刻であり、新たな捕獲の担い手の確保・育成は大きな課題となっています。
そこで、鳥獣捕獲の担い手確保等へ向け、平成26年5月に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)を改正しました。この改正により、狩猟免許(網(あみ)猟及びわな猟のみ)の取得年齢が緩和され、新たに18歳以上20歳未満の人も網猟免許及びわな猟免許を取得できるようになりました。また、この法改正により、安全かつ効果的に捕獲事業等を行う事業者を都道府県知事が認定する「認定鳥獣捕獲等事業者」制度が創設されました。従来はボランティアに近い形で鳥獣捕獲に従事していた人も、こうした事業者による仕事として鳥獣捕獲に携わるようになることで、若者を含む狩猟者の増加につながり、結果的に、地域における獣害の低減や地域の観光資源である高山植生の保全等に資することが期待されます。
また、環境省では、現代において狩猟が自然環境保全や地域社会に必要とされていることを啓発し、狩猟を始めるきっかけを提供するため、平成24年度から「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」を開催しています(写真3-2-9)。平成26年度までに21都道府県で計22回開催し、約4,900人の参加がありました。さらに、最近では、狩猟を始めるまでの解説や実際の狩猟体験に基づく漫画・書籍が多数出版され、狩猟をテーマにしたテレビドラマが制作されるなど、狩猟への注目度が増しており、新たに狩猟を始める人も増加しています。

こうした背景に加え、自分が食べる肉がどうやって自分の手元に来ているのかを考えたことをきっかけに狩猟を始めた20代女性の書籍の出版や、女性狩猟者を主人公としたウェブマガジンの連載等が行われるなど、近年は、女性の狩猟に対する関心の高まりも見られ、免許所持者数が増加傾向にあります(図3-2-21)。
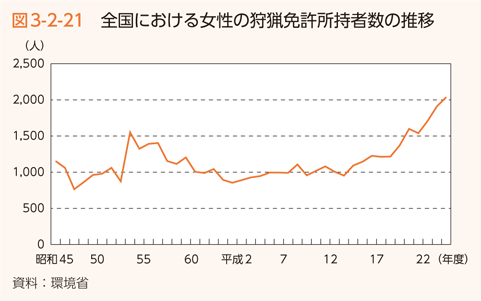
日本各地の農林業被害の防止や自然環境の保全のため、増え過ぎた鳥獣を適正な個体数にまで減少させることが、社会的に求められています。この社会的課題を解決していくため、こうした若者や女性を含めた市民の参画がますます重要になっています。
イ 自然環境保全活動における高齢者の活躍
高齢化が急速に進む中、グループ活動への参加意欲が高い高齢者が増えています。内閣府の調査(平成25年)によると、60歳以上の高齢者のうち「参加したい」という意欲を持つ方は72.8%となっており、実際の参加率は57.9%となっています。ここでの参加したいグループ活動は環境活動に限るものではありませんが、グループ活動への参加意欲の高い高齢者が多いことが分かります。また、こうしたグループ活動に参加している人の方が、活動に参加していない人よりも生きがい(喜びや楽しみ)を感じているという結果もあります(図3-2-22)。
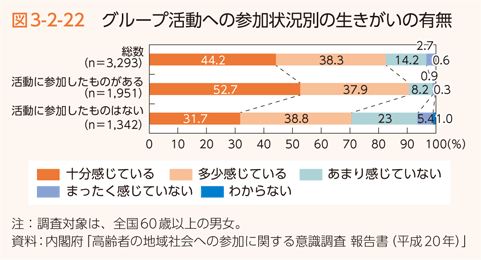
さらに、「過去1年間に参加した地域・ボランティア活動」については、「地域の環境を美化する活動」や「環境保全・自然保護などの活動」など環境関連の活動に参加している人が占める割合が比較的高いことが分かります(図3-2-23)。環境省の調査でも、60歳以上の高齢者は他の世代に比べ、地域における環境保全活動に参加している割合が高くなっており、地域の環境保全について、高齢者の意識が高いことが分かります(図3-2-24)。これは、職業生活からの引退過程を通じて、これまで属していた企業内のコミュニティから離れることで社会とのつながりが希薄になるとともに、自由に使える時間が増えたことで、地域コミュニティへ関与するインセンティブが高まったことが背景にあると考えられます。
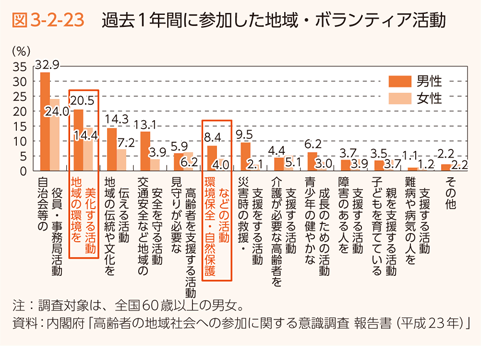
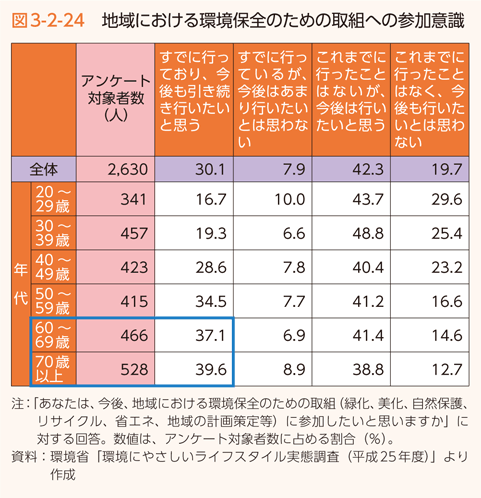
こうした高齢者による環境保全活動の一例として、パークボランティアが挙げられます。全国の国立公園では、自然観察会等の解説活動や美化清掃、利用施設の簡単な維持修理などの各種活動に自発的に協力可能な方々を、パークボランティアとして登録しています。平成26年4月現在、全国の25国立公園の37地区において、1,524名が自然解説活動や利用施設の維持修理等、その地区の特性に応じた活動を実施していますが、そのうち約45%に当たる689名が65歳以上です。こうした方々は、これまでに培ってきたその国立公園地域に関する深い知識と経験を生かし、熱意を持って活動しています。また、活動そのものが国立公園地域に関する知識や技術、熱意を新規加入者に共有する人材育成の場となることで、地域資源である国立公園を通じた地域活性化の担い手が育ち、将来にわたって国立公園の持続可能な利用と保護にも資することが期待されます。
また、東京都環境局が都内で自然観察・体験活動や緑地保全活動を行う指導者を育成するために審査・認定している「緑のボランティア指導者」制度では、1級指導者に認定されている145名(自然観察・体験活動65名、緑地保全活動80名)のうち約81%に当たる117名が65歳以上です。こうした方々は、都内に残された里地里山や都自然環境保全地域等の豊かな自然環境の保全と、環境の保全に貢献する人材育成活動に、ボランティアで指導者として関わっています。
このように、意欲の高い高齢者が、自身の知識と経験を活用して地域の自然環境保全に積極的に貢献しています。自然環境の保全という環境の観点のみならず、高齢化が進む社会において高齢者の生きがいや社会参加の機会をつくるという社会的課題の解決の視点からも、高齢者がこうした活動を行うことの意義は非常に大きいものと考えられます。
ウ リサイクル活動における障害者の活躍
第1章第1節で見てきたとおり、特に地方圏では様々な経済・社会的課題を抱えています。こうした地方圏において、企業が障害者に対して積極的に雇用の場を提供し、また、障害者が就労を通じて職業において自立をしていくことは、重要な課題です。障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)では、民間企業における障害者の法定雇用率を2.0%と定めています(障害者雇用率={身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数+失業している身体障害者及び知的障害者の数}÷{常用労働者数+失業者数})。雇用障害者数、実雇用率は共に毎年増加しており、平成26年6月現在の実雇用率は1.82%となっています(図3-2-25)。また、法定雇用率達成企業の割合は、44.7%(前年比2.0ポイント上昇)となっています。今後、障害者の雇用を更に促進し、その地域で働く方々を増やしていくことは、その地域の社会経済に貢献していくことにもつながります。
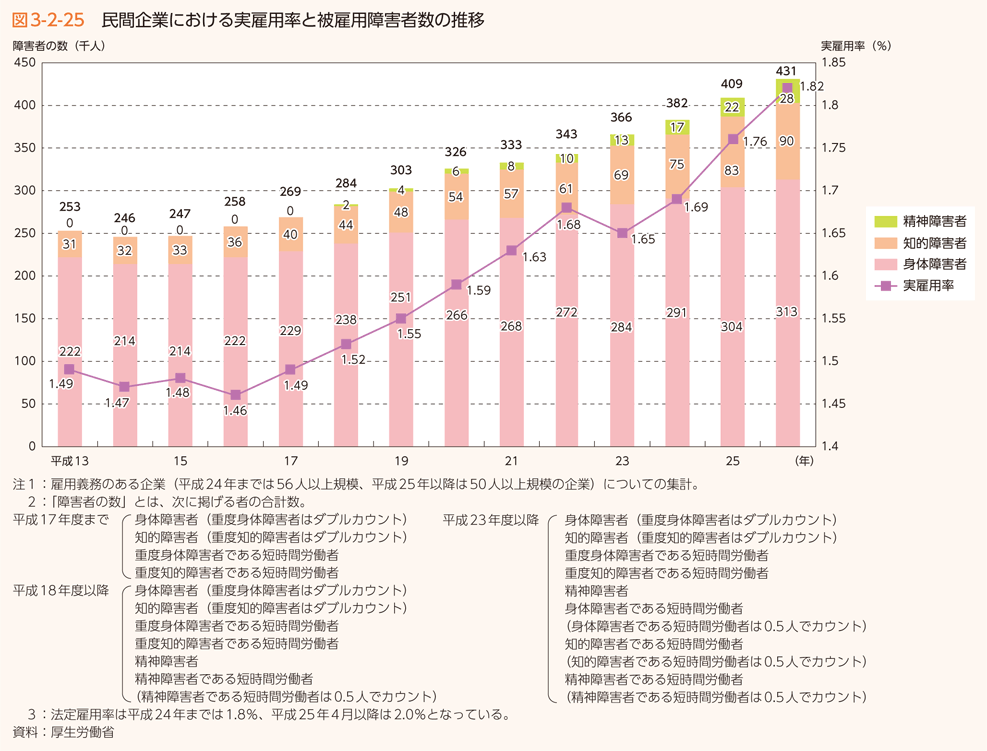
一方、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)の施行後、小型家電リサイクル事業に関する各地での取組が本格化しており、こうした背景を基に、リサイクル企業において雇用された障害者が解体・分別作業を担当する例が見られます。回収されたパソコン等の小型家電の分別・解体は手作業が基本となっており、障害者が手作業で丁寧に作業を行うことで、小さなネジ1本までリユースやリサイクルが可能となります。例えば、愛知県の木村メタル産業株式会社では、「ハート雇用」という障害者雇用を進めています。同社では、障害者が産業機器、情報機器等を丁寧に解体し、きめ細やかな解体・分別を行うことで、資源のリユース率やリサイクル率の向上に寄与しています(写真3-2-10)。例えば、パソコンを例に挙げると、1日に一人当たり約20台を解体・分別しています。中には、ハードディスク部分のような精密な分解作業に能力を発揮される方もいます。

同社の3工場の障害者雇用数の合計は52名(平成27年3月現在)となっており、障害者雇用率は50.0%となっています。こうした企業の取組は、障害者の雇用促進に寄与するとともに、その地域の循環型社会構築のための重要な作業を障害者が担うことで、障害者自身の職業的自立と環境保全にも役立っています。
このように、地域の循環型社会構築の一環であるリサイクル活動が、地域の障害者の社会参画と職業的自立を促進し、地域の活性化にもつながるような取組が今後全国に広まっていくことが期待されます。
第1章第1節で述べたとおり、地方圏では「自然減少」、若者の転出による「社会減少」及び「高齢化」が同時に生じており、結果的に地方圏の方が、国全体で見たときよりも人口減少・高齢化がより急速に進んでいます。そして、人口規模が小さい地域ほど、地方自治体の財政力が脆(ぜい)弱な傾向があります。こうした中、各地方の様々な主体同士が連携し、その地域の人材、資金、地域の自然資源等を有効に活用しあって相乗効果を得ることで、地域の活性化を図っていくことが重要です。そして、それは都市圏と地方圏の間にも同じことが言えます。都市圏には、地方圏に比して人材と資金が集まりやすい一方で、食料、水、木材といった物質や電力エネルギーの多くを地方圏を含む地域外から得ています。このため、都市圏と地方圏が持続可能なまちづくりを行うためには、それらの地域の間で、自然的つながり(森・里・川・海の連環)や経済的つながり(資金等)、さらには人的なつながりを始めとしたつながり(ネットワーク)を強化し、地域の活性化につなげていくことが必要です。ここでは、こうした地域間の連携について述べていきます。
我が国は海に囲まれた島国であり、急峻(しゅん)な山岳地帯から流れ出す河川に沿って里地里山や都市が発達し、文化や産業等が形づくられてきました。これらの森・里・川・海のつながりの中で、物質等が循環することにより、多くの生態系サービスが育まれています。
例えば、我々の日々の暮らしに密接に関わっている生態系サービスに「水」があります。雨は断続的にしか降りませんが、河川には水が絶えることなく流れています。森林では土壌が雨を吸い込み、その水が土壌の中をゆっくり移動して少しずつ河川へと流れ出すことで、河川の水量が安定します。平成13年の日本学術会議答申「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について」に示されている試算例によれば、森林は水が滞留することで生み出される洪水緩和、水資源貯留、水質浄化といった一定の水源涵(かん)養機能を有するとされており、その貨幣評価額は、年間29兆8,454億円とされています。そして、その水を育む森林は、人が生きるために必要な基盤として、古来より同じ流域内の人々によって守られ、その森林の価値を分かち合うことで、安全で豊かな暮らしが維持されてきました。また、「食料」、「資材」などの生態系サービスを守り供給してきた地方と、そのサービスを享受してきた都会による地域間の連携という観点も重要です。地方と都市との連携により、資源、資金及び人が循環することで、互いに必要としているものを補完し、支え合うことができます。例えば、地方にとっては遊休農地の活用や地域資源の販路の開拓、都市にとっては自然との触れ合いの場や良質の資源の確保につながるなど、それぞれがメリットのある関係を築くことが可能です。
森・里・川・海から得られる生態系サービスを適切に利用し、将来にわたって恵みを享受し続けるためには、その地域だけの視点で取り組むのではなく、生態系サービスの受け手となっている地域も含めた広域的な連携が必要です。
本項では、地域間で連携し、支え合いながら、生態系サービスを適切に利用するための取組を進めている事例を紹介します。
ア 矢作(やはぎ)川水源の森 分収育林事業
「水」という生態系サービスを供給するとともに、地域の人々の安全で豊かな暮らしの基盤となる森林を広域で連携して維持している事例として、長野県下伊那(しもいなぐん)郡根羽(ねば)村の「矢作川水源の森 分収育林事業」があります。矢作川は三河湾に注ぐ全長約117kmの河川で、その流域面積は約1,800km2にもなります。上流部には長野県の2村と岐阜県の2市、中・下流部には愛知県の18市町村があります(図3-2-26)。その水資源は、流域約134万人の飲み水を始め、農業、工業、発電等に利用されています。
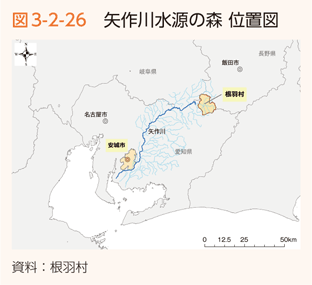
最上流部に位置する根羽村では、大正時代から営林署等による造林が行われ、伐期に入った昭和30年代から営林署等による伐採が始まりました。昭和40年代半ばまでは伐採が盛んに行われ、木材の販売により、村の財政も大きく潤ってきました。しかし、平成3年に伐採を行う予定であった村内の官行造林地(公有地に国が造林し、国が管理を行う分収林)について、水源涵(かん)養の機能を有する貴重な水源の森として立木を残したいと考えた根羽村は、材木を得るための皆伐を取りやめ、営林署からその土地の権利分を買い取って、水源涵(かん)養や砂防などの機能を重視した森林づくりを進めることとしました。
買取りに必要な資金を確保するため、根羽村は、以前から野外活動の受入れ等で交流があった下流部の愛知県安城市に、「矢作川水源の森(写真3-2-11)」として分収林を共同経営することを提案しました。安城市は、同市での農業の発展を、矢作川を水源とする明治用水のおかげであると考え、水源地としての保全の必要性を重視して、立木取得費約1億5,000万円を負担することとしました。平成3年、両自治体において協定を締結し、48haの森林を対象に、立木の買取りや今後30年間の森林管理を行うこととなりました。

根羽村と安城市の間では、このほかにも環境教育、両自治体共同による交流フォーラム、トラスト活動等の交流も行われており、共通の流域を通じた連携による地域づくりが進められています。
イ 空と土プロジェクト
三菱地所グループは、平成20年から山梨県北杜(ほくと)市で活動を行うNPO法人「えがおつなげて」と連携し、都市と農山村が共に支え合う活動「空と土プロジェクト」を開始しました。プロジェクトでは、荒地を開墾し棚田を再生するプログラムや間伐ツアー等を、三菱地所グループの社員と家族、東京都丸の内エリアの就業者、同社のマンション契約者等を対象に実施するとともに、そこで得られた農作物や間伐材等の地域資源を都市で活用していく取組が進められています。
プロジェクトにより、5,600m2の棚田と1,400m2の畑の再生が行われました(写真3-2-12)。そのうち、棚田ではうるち米、もち米及び酒米を栽培しており、社員や丸の内エリアの就業者が田植え・稲刈りを行って(日常管理はNPO法人「えがおつなげて」が実施)、地元の酒蔵と共同で、収穫された酒米を用いた純米酒「丸の内」を商品化しました。商品は、丸の内エリアのレストランやショップで販売しており、その販売本数も増加しています(図3-2-27)。さらに、平成25年からはその収益の一部を同NPO法人に寄付し、地域の活動へと還元しています。

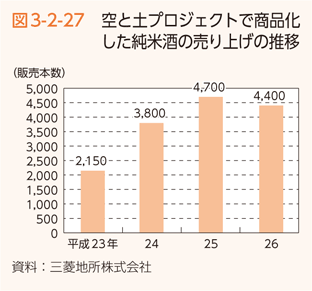
また、平成23年8月には山梨県、三菱地所株式会社、三菱地所ホーム株式会社及びNPO法人「えがおつなげて」の間で、「山梨県産材の利用拡大の推進に関する協定」が締結されました。これを受け、三菱地所ホームでは、FSC認証(森林管理の国際認証)の山梨県産カラマツの間伐材等を使用した単板積層材(LVL)や、山梨県産材であることの認証を受けた家屋の骨組み材木(構造材)を注文住宅の建材の一部として標準採用するなど、山梨県産材のブランド力の向上、利用拡大を図る取組が進められています。その結果、平成23年には、同社の注文住宅の国産材使用比率が前年の35%から50%超へと拡大しています。
川場村と世田谷区との地域間連携
群馬県の川場村は、群馬県の北部地域の中心地、沼田市の北約10kmに位置している自然豊かな農山村です。村の総面積約85km2のうち、約83%が森林で占められています。平成22年国勢調査によれば、人口は3,898人ですが、我が国の他の地方と同様に若年層の減少と高齢者の増加が見られ、川場村の高齢化率は平成27年3月現在で30.6%となっています。
昭和50年代以降、こうした高齢化が顕在化する中で、農業の衰退による里地里山風景の荒廃を懸念し、「農業プラス観光」の取組を進めたいと考えた川場村は、「第二のふるさと」を探す東京都世田谷区との間で、農山村と都市の交流による村の活性化と、自然環境の保全を図ることを目的として、昭和56年に世田谷区と「区民健康村相互協力に関する協定(縁組協定)」を締結しました。この協定により、村に「世田谷区民健康村」という、世田谷区民がふるさと感を味わい、健康的な余暇時間を過ごせる大規模な施設が建設されています。ここでは、世田谷区の小学校5年生全員が宿泊して農業体験や環境活動体験を行う「移動教室」を実施しているほか、一般区民・村民向けのプログラムも実施されており、豊かな自然の恵みに触れながら、両地域の方々が相互に協力して都市と山村の交流を深めています。さらに、村では村民・区民の共通の財産である川場村の自然を協働で守り、育て、後世に住みよい環境を残すことを目的として、「健康村里山自然学校」を開校しています。この取組の一環である「里山塾」では、村民と区民の連携による森林作業の体験や技術の養成教室、里地里山風景の一つである茅場づくりや茅葺屋根の補修等が実施されています。
こうした取組により川場村の優れた里地里山の風景が維持されており、都市と地方が連携して、その地域の人材や地域の自然資源等が有効に活用されることで、地域の活性化が図られています。

我が国は、地球温暖化対策を進めていくために「長期的な目標として、2050年(平成62年)までに80%の温室効果ガスの排出削減を目指す」ことを第四次環境基本計画(平成24年4月27日策定)で定め、その推進を図っています。そのためには、大幅な省エネルギーと再生可能エネルギーの最大限の導入に加え、革新的な技術開発が重要と考えられます。他方で、全国の全ての地域がその地域から生み出される再生可能エネルギーのみを活用したとしても、温室効果ガスの大幅な削減は困難と考えられます。それは、エネルギー需要が大きい「三大都市圏」とそれ以外の「地方」、また同じ都道府県内であっても「人口の集中する都市」と「少ない地方」といったように、エネルギーの需要の程度は様々で、エネルギーの需要の多い地域は、地域内の再生可能エネルギーでその需要を賄うことが難しいためです。そこで、こうした地域間が連携し、エネルギー需要の少ない地域(エネルギーの需要密度が低い地域)からエネルギー需要の多い地域(エネルギーの需要密度が高い地域)へ再生可能エネルギーを供給することで、国全体で温室効果ガスの大幅削減につながると考えられます。
第1節でも述べたとおり、地域の域際収支を見ると、各地域内総生産(GRP)の1割弱(平均値)の資金が、エネルギーの使用に伴って地域外に流出しています。そのうち、海外への化石燃料への支払い額が約5.9%(約28兆円)となっています。そのため、再生可能エネルギーのポテンシャルの高い地域が、その地域のエネルギー消費を化石燃料エネルギーから再生可能エネルギーにシフトしていくことで、域際収支を改善することができると考えられます。
再生可能エネルギーのエネルギー源は、太陽光、風力、水力、地熱といった具合に、基本的にその土地に帰属する地域条件や自然資源、いわゆる「自然の力」であるため、自然エネルギーのポテンシャルは、地域によって偏りがあります。一方で、市区町村ごとの面積当たりのCO2排出量を見ると、おおむね都市圏でCO2排出量が多くなっています(図3-2-28)。エネルギーの需要量を現在のままとした上で、仮に、全市区町村でその地域の自然エネルギーのポテンシャルを全て活用し再生可能エネルギーを導入した場合、図3-2-29のとおりとなります。赤・オレンジ色で示した市区町村は、エネルギーの需要密度が高く、その土地から生み出される再生可能エネルギーのみでは必要な供給量を満たすことができません。一方、緑色・黄緑色で示した市区町村では、再生可能エネルギーのみで必要な供給量を満たすことができます。また、青~水色で示した市区町村は、エネルギーの供給量が需要量を大きく上回り、域外にエネルギーを移出(販売)できる能力があります。このように、再生可能エネルギーの供給ポテンシャルが高い地域(青~水色)は、自身のエネルギー需要を十分に賄って自立した上で、エネルギー需要の高い地域(赤・オレンジ)に再生可能エネルギーを移出することで、地域外から資金を獲得できる可能性があります。
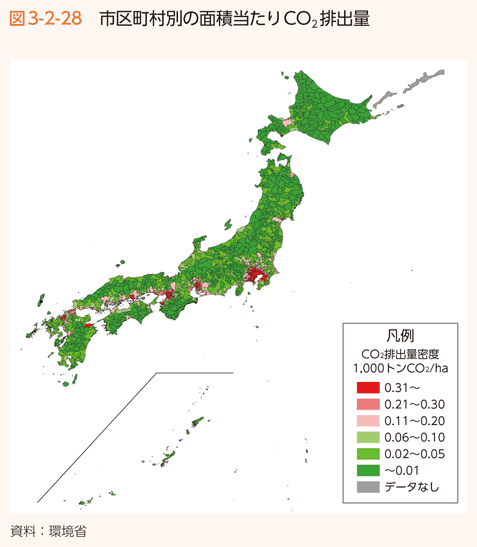
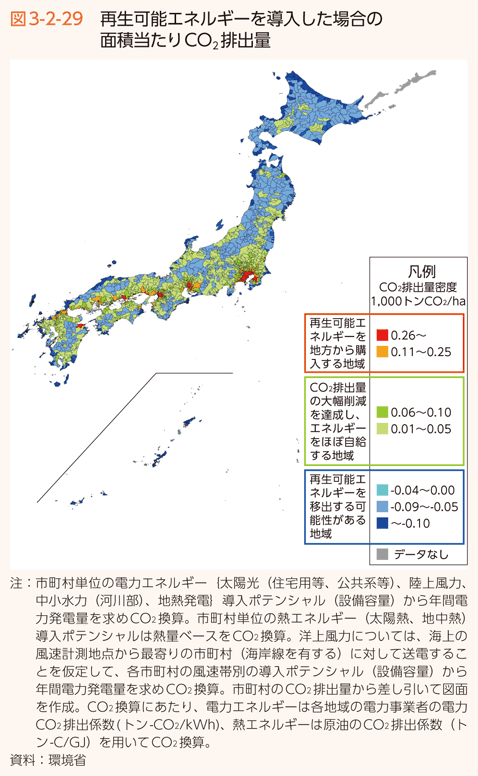
前述のように三大都市圏や人口の集中する都市を始めとするエネルギー需要の高い地域と、潜在供給能力が高い地域との地域間連携を進めていくためには、具体的な施策を実施することが重要です。例えば、地域間の送電網の強化を図るほか、ポテンシャルが高い地域において再生可能エネルギーによる電気分解により水から水素を作り、エネルギー需要の高い地域へ輸送して使用するといった方法が挙げられます。ただし、地域間連系線の強化には多額の費用が生じるほか、水素エネルギーを輸送する場合には、輸送コストや輸送に伴うCO2の排出、水素と電気の変換ロスも考慮に入れる必要があります。
さらに、前述のとおり化石燃料への支払額約28兆円は海外に流出しています。再生可能エネルギーの徹底的な導入と大幅な省エネ等を併用することで、海外に流出している資金を国内で再分配することが可能となり、地域経済を含めた我が国の経済にも資することになります。
規格統一リユースびんによる地域循環圏の構築
私たちの暮らしは、物質の循環によって成り立っています。例えば、私たちの食べているものは、主に他の地域から運ばれてきたものです。それは、都市部に限った話ではありません。地方圏であっても、その地方内で物質循環が完結していることはまれであり、他の都市や地方から運ばれてくるものもたくさんあります。しかも、食べ物のような資源だけではなく、ごみやエネルギーも他の地方から運ばれてきたり、他の地方に運んだりという循環が行われています。しかし、物質を地域内で循環させたり、それが困難なものを広域的に循環させることで資源の使用量を抑えたり、廃棄物の発生を抑制するという取組は、まだ十分実施されているとは言えません。そこで、資源を有効活用するためには、地域で循環可能な資源はなるべく地域で循環させ、それが困難なものについては循環の環を広域化させていく「地域循環圏」を重層的に構築することが必要です。「地域循環圏」という概念・仕組みが、地域の資源を有効に循環させることになります。こうした地域循環圏を構築している一例として、「リターナブルびん」があります。
リターナブルびんは、再使用(リユース)を前提としない使い切りの「ワンウェイびん」とは異なり、原型のまま洗浄され、繰り返しリユースされるため、環境負荷がワンウェイびんよりも低いという特徴があります。
五つの生協団体のネットワークである「びん再使用ネットワーク」では、容量の異なる7種類の「規格統一リユースびん」を使用しています。それぞれ商品の中身は異なりますが、五つの生協合計で、規格統一リユースびんを使用した約200アイテムの商品を扱っています。一つのびんが何度も洗浄されて使用されるため、例えばジュースに使われた容器が、次はお酢の容器として使われることもあります。北海道や九州までの広域的な地域内において、五つの生協団体に加盟する合計約210万世帯が、県や地域を限定せずにびんのリユースを行っています。
規格統一リユースびんの底や肩部には、リターナブルびんの頭文字である「Rマーク」が刻印されており、「Rびん」と呼ばれています。規格を統一したびんを使うことで、リユースに不可欠な回収、洗浄、選別といった作業の効率性を高めています。さらに、生協組合員が共同購入する際の配達ルートを活用して、使用済みのびんの回収を行っています。こうした取組は、びんを作るメーカー、内容物を充填する提携生産者、回収や洗びんの事業者と生協といった複数の関係者が協働することで実現しています。「びん再使用ネットワーク」は、平成6年の設立以来、約1億8,335万本のびんを回収してきており(回収率約67%)、回収したRびんの累積量をCO2の削減量に換算すると、約6万655トン(東京ドーム約25個分)となります。

加えて、使用本数の多い900mlと500mlのびんについては、びんの外側表面に樹脂を薄くコーティングし、ガラスを薄くしても強度を保つ加工を行うことで、従来のリユースびんに比べびんの重量を約40%軽くした「超軽量リユースびん」を採用しています。従来のリターナブルびんと超軽量Rびんを比較してみると、重量、CO2の削減効果、強度、洗びんロス率(洗浄による破損発生率)が改善されており、より環境負荷が低いことから、長距離輸送を伴う広域での再使用に適しています。
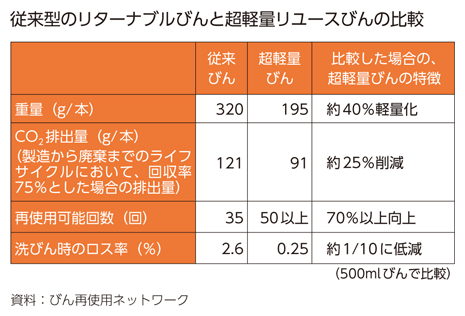
「びん再使用ネットワーク」に加盟する五つの生協団体により、北海道や九州までの広域的な地域内で同じ規格のびんが効率的にリユースされることで、生協ごとの地域循環圏が構築されており、環境負荷の低い資源循環を実現しています。
2020年東京大会が開催される平成32年(2020年)は、我が国の温室効果ガスの削減目標年であり、かつ、2020年以降の新たな国際的枠組みの開始年になる予定の年であるとともに、平成22年に名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)において採択された「愛知目標」の短期目標(生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する)の目標年でもあります。このような大きな節目の年に開催される2020年東京大会は、我が国の環境配慮への姿勢が世界中から注目される大会になると考えられます。そのため、オリンピックを通じ、我が国が環境問題の解決に向けた道筋を世界に先駆けて示していくことが重要です。また、これらの解決のためには、技術やインフラを導入するだけでなく、本大会を契機として、環境に係る諸課題を抱える東京をより住みよい都市にすることで、社会の仕組みや人々の価値観を変え、「循環共生型社会」を実現していくことが必要です。
このような考え方に基づき、環境省では、平成26年8月に「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を契機とした環境配慮の推進について」を取りまとめるとともに、これに基づく取組を推進することとしています。そうした地方の環境、経済、社会の統合的向上に向けた動きとして、以下ではオリンピックを契機とした環境配慮に関する都市づくりの取組を紹介していきます。
東京都市圏(ここでは、東京都、千葉県、埼玉県及び神奈川県とする。)について、その経済規模を見てみると、平成22年度(2010年度)の域内総生産額が合計1兆8340億ドル(平成22年度支出官レート:1ドル=94円で換算して、172兆3,960億円)と、日本全体のGDPの約1/3、G7諸国のイタリア、カナダのGDPに匹敵する世界最大の都市圏です。また、一人当たり総生産も米国やカナダより多い5万1,510ドル(同484万1,940円)となっています(図3-2-30)。このように、東京都市圏での様々な取組は、金額ベースで主要国一国の取組に相当するものであり、東京都市圏における「循環共生型社会」の構築に向けた取組を内外に示すことで、世界の取組を加速させることが期待されます。
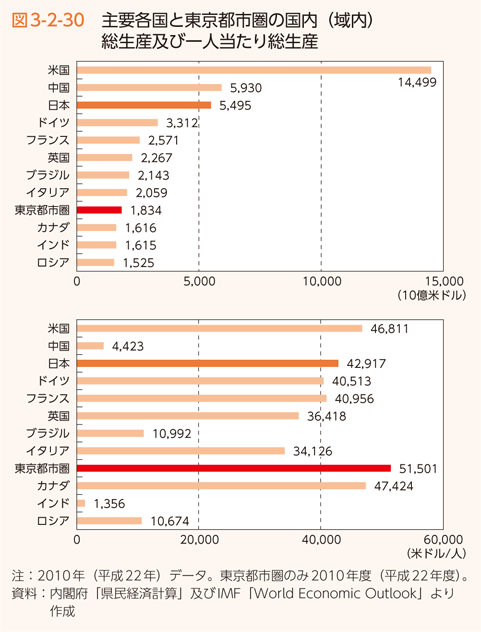
2020年東京大会の立候補ファイルでは、廃棄物抑制、環境負荷の少ない輸送の実施等、環境面での積極的な対応が公約されています。こうした点も踏まえ、大会自体の環境負荷の低減と、大会を契機とした我が国の環境配慮の推進に向けて、東京都・民間事業者、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「大会組織委員会」という。)等の大会関係者の取組を推進するため、政府が当面取り組んでいくべき事項として、低炭素化の推進、ヒートアイランド対策の推進、良好な大気・水環境の実現、リデュース・リユース・リサイクル(3R)の徹底、環境情報の発信等があります。
ア 低炭素化の推進
2020年東京大会が開催される平成32年は、既述のとおり温室効果ガスの削減目標年(平成17年度比3.8%減)であることから、大会関連施設の建設から廃棄に至るまでの全プロセスでの低炭素化、大会開催時の選手・観客の移動手段の低炭素化等について、大会組織委員会等に積極的に促していく必要があります。
また、大会会場である東京都市圏の低炭素化を特に図ることが重要であることから、国は、低炭素化技術の普及・波及効果に関する東京都市圏全体での予測シミュレーションの実施、電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)とその充電ステーションや水素ステーションの普及及びこれらに係る技術開発、高効率の熱供給システム等の省エネルギーに関する技術の活用支援等を行うことが必要です。
さらに、オリンピックを契機に地方の活性化を促すため、今後開発されるオリンピック・パラリンピック関連商品・サービスについて、全国各地で創出されるカーボン・オフセットの活用を促進することも重要です。
加えて、ロンドンオリンピックでは、環境負荷の低い物品を調達する「グリーン購入」が徹底されなかったと評価されたことも踏まえ、2020年東京大会では、グリーン購入について一層の展開を図るため、事業者等の関係者による現行基準よりも厳しい購入基準の自主的採用を促すとともに、国が技術的支援等を行う必要があります。
また、東京のエネルギーの需要密度は現在、北海道や東北等の約50~60倍となっており、将来においても、東京に存在する再生可能エネルギーによって東京のエネルギーを賄うことは難しいと考えられます。そのため、前項で示したように、大会を契機として、再生可能エネルギーのポテンシャルが多い地域から再生可能エネルギーを調達していくことも考えられます。東京の代表的な街区に全国各地から再生可能エネルギーが供給されるといった地域間連携を行うことで、資金が都市から地方に流れるとともに、東日本大震災の被災地を始めとする地方における雇用創出や経済活性化につなげることが期待できます。
イ ヒートアイランド対策の推進、良好な大気・水環境の実現
(ア)ヒートアイランド対策
過去100年で、東京の平均気温は約3℃、第18回東京大会が開催された昭和39年頃と比べても平均で1℃以上の上昇となっています。中小都市の過去100年の平均気温の上昇が約1℃であることを鑑みると、ヒートアイランド現象による東京の平均気温の上昇幅は極めて大きいと言えます。ヒートアイランド現象の発生要因としては、主にエアコンや自動車等の人工排熱の増加、緑地や水面の減少、地表面の舗装等による人工被覆(ひふく)の増加、高層建築物による天空(てんくう)率の低下(図3-2-31)などが挙げられます。
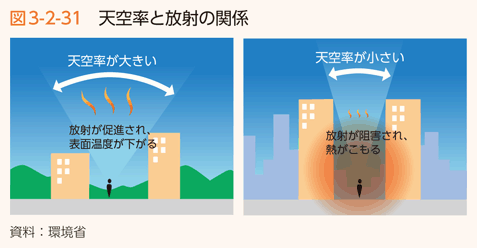
2020年東京大会が真夏に開催されることを鑑みると、選手が最大限の力を発揮できるよう、ヒートアイランド現象への対策を推進していく必要があります。具体的には、大会後の対策の継続も見据え、大会会場やコース周辺等の保水性・透水性舗装等の設置(図3-2-32)、低炭素化の取組も兼ねた、高効率の空調機器等の導入による人工排熱の低減、緑地や水面の確保など、選手や観客等への暑さによるストレス(以下「暑熱(しょねつ)ストレス」という。)の軽減策を講じていく必要があります。
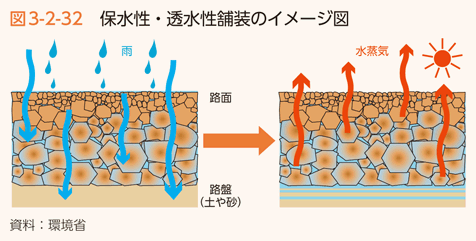
(イ)熱中症対策
前述のヒートアイランド対策に併せて、今後増加が見込まれる日本の夏の暑さに慣れていない外国人観光客に対して、暑熱ストレスを軽減するための情報提供も必要です。具体的には、大会会場ごとの暑さ情報等の発信やリーフレット等の多言語化による普及啓発により、日中の炎天下の暑さの度合いや熱中症の知識に関する情報の提供を行っていくこと等が考えられます。
(ウ)大気汚染対策
2020年東京大会の開催に当たっては、良好な大気環境が市民のみならず選手や観客に対し提供されることが重要です。そのため、東京都及び周辺地方公共団体と連携して、光化学オキシダントの原因物質であるNOxの排出規制等、濃度低減対策を進めていく必要があります。
(エ)東京湾等の水質改善
2020年東京大会は、閉鎖性の内湾である東京湾岸の臨海部が主要会場であり、トライアスロン等、東京湾そのものを利用する競技も予定されています。また、都心の貴重な水辺空間である皇居外苑濠(がいえんぼり)(内濠(うちぼり))の周辺等では、マラソン競技など多数の競技が予定されているものの、水の滞留と継続的な汚濁物質の流入等によってアオコが大量発生するなど、悪臭や景観面での悪影響が懸念されます。水質環境の改善に向け、関係省庁や地方公共団体と連携し、水質浄化に向けた取組を進める必要があります。
ウ 3Rの徹底等
2020年東京大会では、大会関連施設において、3Rに関する技術開発や実証事業を実施するとともに、食品ロスの削減やドーピング検査に使用する注射針等の円滑な処理等を含めた各種の対策を進めていく必要があります。また、東京都市圏における取組として、2R(リデュース及びリユース)を推進するとともに、その上で発生する廃棄物については、リサイクル促進のために統一分別ラベルを導入し、外国人も含む観客等の自発的な分別行動を促進することが必要です。
エ 我が国からの環境情報の発信等
我が国が環境先進国であることを国内外に広くPRするため、日本の環境技術や制度の紹介を始め、参加型のESDイベント等の開催等、2020年東京大会に向けての取組を効果的に発信していく必要があります。
また、大会を契機に、日本を訪れる観光客や海外メディアに対し、東日本大震災から復興した姿を積極的に発信していくことも重要です。加えて、開催地である東京都が擁する多摩地域西部や伊豆諸島、小笠原諸島等国立公園や世界自然遺産地域等はもとより、全国各地の国立公園についての海外への積極的な情報発信を行うとともに、東京大会を機に日本を訪れる外国人旅行者の地方への誘客を図ることで、大会を契機とした地方の活性化を図っていくことが期待されます。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |