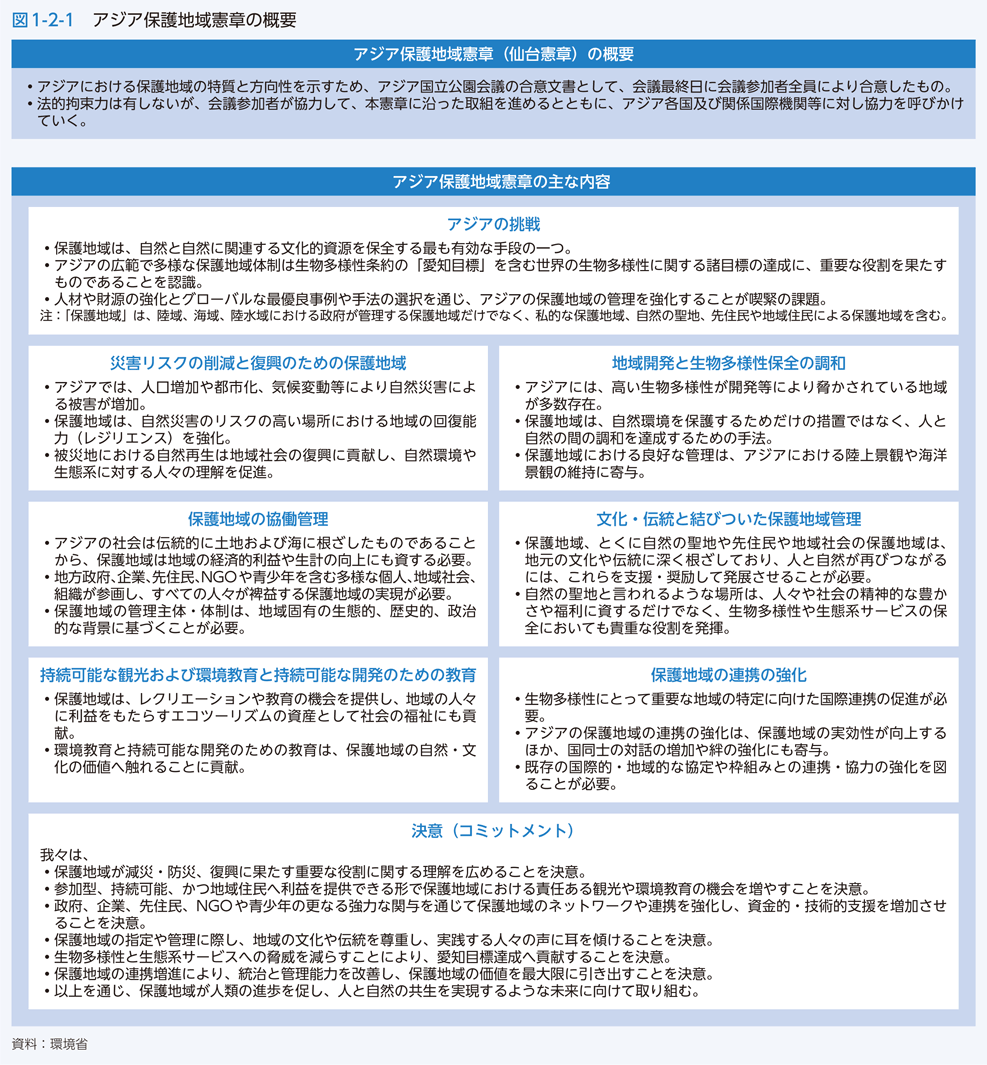
現在、地球上には3,000万種とも推定される生物が存在し、私達は生物の多様性がもたらす恵みを享受することにより生存しています。生物多様性が人類の生存基盤であることを認識した上で、自然のことわりに沿った自然と人とのバランスのとれた健全な関わりを社会の隅々に広げ、将来にわたり自然の恵みを得られるよう、自然の仕組みを基礎とする真に豊かな社会を実現することは、持続可能な社会の形成に必要不可欠といえます。
本節では、我が国における自然環境の現状や自然共生社会の実現に向けた取組を紹介するとともに、生態系のさまざまな機能に着目しながら、生物多様性保全の維持・向上に寄与している国内外の取組について紹介します。
平成22年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(以下「COP10」という。)において、新たな世界目標として採択された「戦略計画2011-2020」(愛知目標)では、長期目標として、2050年(平成62年)までに「自然と共生する社会」を実現することを掲げています。これを踏まえ、平成24年9月に閣議決定した「生物多様性国家戦略2012-2020」では「豊かな自然共生社会の実現に向けたロードマップ」を副題としています。
自然共生社会を実現するためには、食料や水、気候の安定など、多様な生物がかかわりあう生態系から得ることのできる恵み(生態系サービス)を将来にわたり受け続けることができるように、自然を守り、賢く利用していかなければなりません。
ここでは、我が国における自然環境の現状と愛知目標の達成に向けた取組の進捗状況について紹介します。
我が国の既知の生物種数は約9万種、まだ知られていないものも含めると30万種を超えると推定されており、約38万km2の国土面積(陸域)の中に豊かな生物相が見られます。また、固有種の比率が高いことも特徴で、陸棲哺乳類、維管束植物の約4割、爬虫類の約6割、両生類の約9割が固有種です。先進国で唯一野生のサルが生息していることをはじめ、クマ類やニホンジカなど数多くの中・大型野生動物が生息する豊かな自然環境を有しています。こうしたことから我が国は、世界的にも生物多様性の保全上重要な地域として認識されています。
我が国の生物相の特徴は、国土の大部分が大陸縁辺に位置し、複数のプレートの境界を有する島弧であることを背景に、およそ北緯20度から北緯45度の中緯度地域において南北約3,000kmにわたる長い国土であること、海岸から山岳までの大きな標高差や縦断勾配が大きい急流河川が多いこと、大小さまざまな数千の島しょを有すること、複雑で多様な地質を有すること、季節風の影響によりはっきりとした四季の変化があることや梅雨・台風による雨期があり雨の多い気候であること、大陸との接続・分断という地史的過程、動物相・植物相のいずれから見ても複数の地理区に属していることなどに由来するほか、火山の噴火や地震・津波、河川の氾濫、台風などのさまざまなかく乱によって、多様な生息・生育環境がつくりだされてきたことによるものです。
国土の約3分の2を占める森林のうち、自然林は国土の17.9%で、自然草原を加えた自然植生は19.0%となっています。これらの自然植生は主として急峻な山岳地、半島部、島しょなどの人間活動の影響を受けにくい地域に分布しており、平地や小起伏の山地では二次林や二次草原などの代償植生や植林地、耕作地の占める割合が高くなっています。豊かな降水量と比較的温暖な気候に恵まれ自然の遷移が進みやすい環境である我が国では、明るい環境を好む多くの植物や昆虫類が生育・生息していくために、人が手を入れることなどによって湿原、二次草原を含む草原、氾濫原、二次林などの明るい状態が保たれていることが重要です。こうした二次的な自然環境は、我が国の気候や地史、自然と共生した生活によって残されてきたものといえますが、現在では広い範囲で失われてきています。
また、世界第6位の広さの排他的経済水域(EEZ)などを含む我が国の海洋は、黒潮、親潮、対馬暖流などの多くの寒暖流が流れるとともに、列島が南北に長く広がっていることから、多様な環境が形成されています。
我が国の生物相は、アジア地域とのつながりが特に大きいといえます。氷河期と間氷期の繰り返しなどで大陸との接続と分断が繰り返されてきたことにより、氷河期に大陸から移動してきた種が高山帯や島しょに隔離されて遺存種として生き残るなど、特有の生物相を形成してきました。例えば、奄美・琉球には、温暖・多湿な亜熱帯林が広がる中に、国際自然保護連合(IUCN)レッドリストに掲載されている国際的な希少種やイリオモテヤマネコやアマミノクロウサギ、ヤンバルクイナなど奄美・琉球にだけ分布する固有種をはじめとする多様な動植物が生息・生育しており、生物多様性を保全する上で重要な地域です。
さらに、渡り鳥やウミガメ、一部の海棲哺乳類などはアジアを中心とする環太平洋諸国の国々の国境を越えて行き来しています。アジア地域全体でこうした野生生物を保全していくためには、このようなつながりを考慮することが重要です。
愛知目標は生物多様性条約全体の取組を進めるための柔軟な枠組みとして位置付けられており、締約国は、各国の生物多様性の状況やニーズ、優先度等に応じて国別目標を設定し、各国の生物多様性戦略の中に組み込んでいくことが求められています。そのため、「生物多様性国家戦略2012-2020」においては、愛知目標の20の個別目標の達成に向けて、5つの戦略目標の下に13の国別目標を設定しています。
愛知目標については、2014年(平成26年)10月に開催される生物多様性条約第12回締約国会議(COP12)において、その達成状況に関する中間評価が実施されることを踏まえ、生物多様性国家戦略2012-2020の進捗状況の点検作業の一環として、これらの国別目標の進捗状況の点検を実施しました(生物多様性国家戦略2012-2020の点検については第2部第2章第1節を参照)。
点検の結果、例えば「生物多様性の社会における主流化」に係る国別目標A-1については、関係府省における取組に加え、有識者や経済界、非営利組織(以下「NPO」という。)・非政府組織(以下「NGO」という。)自治体、政府などの多様な主体の参画を得て平成23年9月に設立された「国連生物多様性の10年日本委員会」(UNDB-J)をはじめとする各種団体において生物多様性の普及啓発等の取組が進んでいることが分かりました。特に、経済界においては平成22年に自発的なプログラムとして「生物多様性民間参画パートナーシップ」が設立され、参加事業者等の間でウェブを通じた情報共有等が行われています。その結果、経営理念・方針や環境方針などに生物多様性の概念が盛り込まれている参加事業者の割合は平成22年の50%から平成24年には85%に上昇するなど、事業者の意識・取組の向上が見られます。また、事業者による取組が消費者から認識され評価されるための仕組みとして、民間主導の認証制度があります。単に「生物多様性」という言葉の認知度を高めるだけでなく、生物多様性の保全と持続可能な利用の重要性が社会の常識となり、それを各主体が意思決定や行動に自主的に結びつけていくためには、このような社会経済的な仕組みの拡大とともに、生物多様性や生態系サービスの価値を可視化するための定量化等の取組をさらに進めていく必要があります。
また、国別目標C-1においては「陸域及び内陸水域の17%、沿岸域及び海域の10%を適切に保全・管理する」ことを掲げていますが、点検の結果、平成25年9月末時点で、陸域及び内陸水域の約20.3%、沿岸域及び海域の約8.3%が法令等により生物多様性の保全及び生態系サービスの持続可能な利用を目的とした保護地域として指定されていることが明らかになりました。引き続き、これらの地域の適切な保全・管理の取組を進めていくとともに、特に沿岸域及び海域において保護地域の新規指定や拡充に向けた取組を進めていく必要があります。
国別目標D-1においては「生物多様性及び生態系サービスから得られる恩恵を強化する」ことを掲げていますが、点検の結果、生物多様性及び生態系サービスと人間の福利の向上を図る取組であるSATOYAMAイニシアティブが国内外で推進されているほか、持続可能な森林経営や農業振興、里海づくりなどが全国で進められていることが明らかになりました。また、東日本大震災からの復興に向けた「グリーン復興プロジェクト」や生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)の仕組みの活用など、さまざまな形で生物多様性及び生態系サービスから得られる恩恵の強化が図られていることが分かりました。
しかし、国別目標B-5に掲げる「気候変動に脆弱な生態系の健全性と機能の維持に向けた人為的圧力の最小化に向けた取組」のように、現時点では取組が十分に進展していない国別目標も見受けられることから、愛知目標の達成に向けて、引き続き、我が国における国別目標の達成を目指した取組を進め、自然共生社会の構築を目指していきます。
近年、生物多様性に関連する国際会議では、気候変動や持続可能な開発など他の環境問題や経済社会との関係を議題として取り上げることが多くなっています。湿地や森林など生態系の有する防災・減災機能や、ツーリズムの経済的利益、科学研究における保護地域の役割など、生物多様性が人類の生存基盤であることを認識した上で、生物多様性と生態系サービスが持続可能な社会の形成にいかに寄与するか、世界的に注目されています。また、我が国が古くから培ってきた自然との共生のあり方や知恵・文化の価値を再評価し、国際社会に情報発信することも求められています。
ここでは、生態系のさまざまな機能に着目しながら、生物多様性保全の維持・向上に寄与した国際的な取組について紹介します。
保護地域は、生物多様性、景観などを開発・乱獲などの人間活動から保護することを目的として、法律等に基づき設定されています。そのため、保護地域については、途上国を中心として、主な役割である自然保護をいかに実現するか、強化していくかが主要な論点となっていました。しかし近年、保護地域のもつ防災・減災機能などの生態系サービスが世界的に注目され、持続可能な利用や自然共生社会の実現の観点からの保護地域の役割が見直され始めています。
ア 第1回アジア国立公園会議
平成25年11月13日から17日にかけて、「第1回アジア国立公園会議」が、仙台市で開催されました。会議は、アジア地域における保護地域関係者が一堂に会する初めての機会として環境省とIUCNが主催したもので、アジアを中心に世界40の国及び地域から約800名の参加がありました。会議のテーマである「国立公園がつなぐ」は、アジアの保護地域は人々の生活や文化とのつながりが深いことや、三陸復興国立公園が人と人をつなぐことにより復興に寄与することを目指していることなどを踏まえて設定されたものです。保護地域がアジアの自然をつなぐということに加えて、人と自然をつなぐ、さらには人と人を、国と国をつなぐことを通じ、生物多様性の保全や自然保護だけでなく、人々の生活と密着した形での保護地域の役割を模索していくというメッセージが込められています。
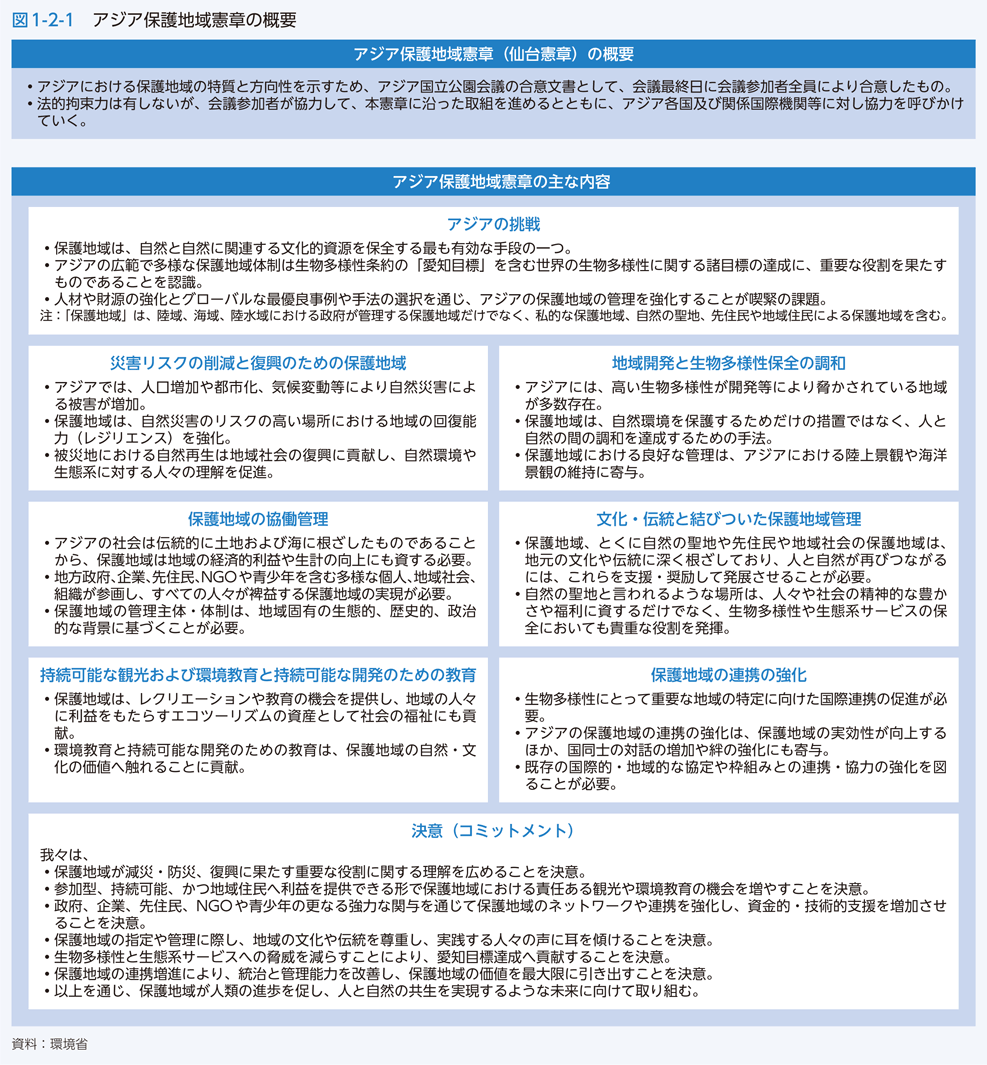
会議では、[1]自然災害と保護地域、[2]保護地域における観光・環境教育、[3]文化・伝統と保護地域、[4]保護地域の協働管理、[5]保護地域に関する国際連携、[6]生物多様性と保護地域、の6つのサブテーマが設定され、サブテーマに沿って、アジアの先進的な取組事例を中心に、300を超える発表が行われました。また、会議の参加者は、三陸復興国立公園を視察し、自然災害からの復興に貢献するという保護地域の役割について確認しました。
会議の成果文書としては、アジアにおける保護地域の基本理念ともいえる「アジア保護地域憲章(仙台憲章)」を参加者の合意により取りまとめたほか、6つのワーキンググループの議論を踏まえた「第6回世界国立公園会議への第1回アジア国立公園会議からのメッセージ」と、会議に参加した若手の研究者などが取りまとめた「アジア国立公園会議ユース宣言」が作成されました。
会議の最終日には、会議の成果を2014年(平成26年)11月開催予定の第6回世界国立公園会議の主催者であるIUCNとオーストラリア政府に受け渡す式典が行われました。
グリーンインフラストラクチャーの活用に係る世界の動向について
グリーンインフラストラクチャー(以下「グリーンインフラ」という。)とは、土地利用において自然環境の有する防災や水質浄化等の機能を人工的なインフラの代替手段や補足の手段として有効に活用し、自然環境、経済、社会にとって有益な対策を社会資本整備の一環として進めようという考え方であり、近年欧米を中心にこの考え方に基づく取組が進められようとしています。グリーンインフラに関する統一的な定義はありませんが、2013年(平成25年)5月に欧州連合(EU)で策定された「EUグリーンインフラストラクチャー戦略」によると、「生態系サービスの提供のために管理された自然・半自然地域の戦略的に計画されたネットワーク」と定義されています。また、同戦略では、主要政策へのグリーンインフラの組み込み、自然環境の再生等の事業の実施、調査研究の推進、資金の動員等が明記されています。こうした動きを踏まえ、ドナウ川流域では、生物多様性保全と災害対策を目的として約20万haの氾濫原湿地の自然再生が予定されています。
また、米国では、2008年(平成20年)に環境保護庁が州政府と協力して、洪水や下水処理の包括的な対策として、「グリーンインフラストラクチャー行動戦略」を策定しました。この戦略では、自然環境に加え、屋上緑化や雨水浸透道路等もグリーンインフラの対象とし、水処理やヒートアイランド対策などの主に都市域におけるグリーンインフラの活用方策をまとめています。ニューヨーク市では、合流式下水道の越流水対策にかかる負担を削減するために、より経済的な対策として、2.4億ドルをグリーンインフラに投資することを決定し、屋上緑化、透水性舗装、緑地や湿地の確保といった取組等を進めることにより、従前の公共事業のみの対策と比較して1.4億ドルの経費の削減を見込んでいます。
国際的には、2008年(平成20年)に国連環境計画(UNEP)、IUCN等の国際機関により設立された「環境と災害リスク削減に関する国際パートナーシップ(PEDRR)」により、生態系を活用した防災・減災(Eco-DRR)に関する能力養成、事例収集や政策提言等が進められています。
イ 第6回世界国立公園会議
世界国立公園会議は、世界の保護地域の関係者が集まる機会として、IUCNが中心となって1962年(昭和37年)からおおむね10年おきに開催している会議です。会議では、国立公園をはじめとする保護地域に関する最新の知見が共有され、その後10年間の保護地域の取組の方向性が提案されます。
第1回(1962年(昭和37年))、第2回(1972年(昭和47年))には、国立公園を世界中に広めることや、自然保護の強化を図ることが主要なテーマでしたが、第3回、第4回では、国立公園内や周辺に住む人達との連携の重要性も大きなテーマとなってきました。そして、2003年(平成15年)にダーバン(南アフリカ)で開催された第5回の会議では、保護地域がその外部にもたらす幅広い利益とそれを保全するために多様な関係者が協力していくための方策などが議論されました。
2014年(平成26年)11月にシドニー(オーストラリア)で開催される第6回の会議では、自然環境の保全や地域の関係者との連携に加えて、気候変動、食料や水の供給、健康、健全な経済発展などのさまざまな地球規模の課題に対して保護地域を活用した解決策を見いだすことが目指されています。我が国は分科会の一つを国連食糧農業機関(FAO)及び世界保護地域委員会(WCPA)とともに担当し、「復興や減災に対する保護地域の役割」というテーマについて議論を主導し、自然がもつ防災機能を維持するために保護地域を活用している事例の収集を行い、提言を取りまとめる予定です。また、第6回世界国立公園会議における議論を踏まえ、平成27年3月に仙台市で開催される国連防災世界会議の場などを活用し、生態系のもつ防災・減災機能について、情報発信を行います。
ラムサール条約は湿地の保全を目的とした条約であり、この条約で定義される「湿地」とは湿原のみを指すのではなく、干潟やサンゴ礁、マングローブ林のような原生自然的な生態系や、田や遊水池のような人工的なものまで、非常に幅の広いものです。これらの湿地環境は一般に、じめじめしていて不気味な印象であったり、不毛な土地であるととらえられがちです。そして不毛で生産性のない場所と認識されると干拓や埋立てなどの対象となりやすくなり、湿地はこうしたことからも世界的に損失や劣化が著しい環境となっています。一方で、湿地環境は水鳥や魚類などさまざまな動植物の生息地として非常に重要であるとともに、私達が生きていくのに欠かせない飲料水や食料の供給機能、保水・遊水機能といったさまざまな恵みをもたらしてくれる大切な環境です。このような特徴を有する「湿地」という環境を保全するためには、湿地が、我々の健全な暮らしやそのほかの動植物が生息していくためには欠かせない場所であることを、その湿地にかかわる人々が認識できていることが大切です。そして、湿地が多くの恵みをもたらしていることを認識するためには、人々の生活が湿地と密接にかかわっていることが見える状態になっていることが重要になります。
そのため、ラムサール条約では、湿地を保全するために湿地からもたらされる恵みを賢明に(持続可能な形で)利用していく「ワイズユース」という考え方が重要な柱に据えられています。我が国でもこの「ワイズユース」の考え方を踏まえ、さまざまな取組が行われています。例えば、環境保全型の水田稲作の推進や、そうした取組をより多くの方々に伝えていくために地域の農家の方々が中心となったツアーなどが行われています。また、湿地に生える植物であるヨシの管理と活用の促進に資する「ヨシ焼き」や「葦簀(よしず)づくり」といった、地域ごとの風土にあわせて育まれてきた伝統的な技術が湿地の利用を持続可能にしてきたという側面を再評価しながら、賢明な利用を促進し、そうした賢明な利用を通じた湿地の保全管理を行う、といった取組が行われています。さらに、平成25年度には、沿岸漁業の営みによって干潟の生物多様性が向上しているという観点に注目し、この点も重要視したワイズユース基本計画の策定を、荒尾干潟において地域の関係者とともに進めました。さらに、平成26年2月2日の「世界湿地の日」には、水田という湿地生態系を取り上げ、稲作による生物多様性向上の取組や、それらを支援する取組を紹介し、議論するためのシンポジウムを開催しました。

国際的にも、「ワイズユース」の理念に基づき、平成25年に本条約の下にラムサール文化ネットワークが誕生し、我が国もそのメンバーとなりました。
また、我が国は東南アジアの湿地の保全のための適正な管理等にも貢献を続けています。平成25年度にはミャンマーを対象として適切な沿岸漁業の推進支援を含むこれまでの湿地管理等への貢献の整理を行うとともに、湿地の現在の状況についての調査・分析等を実施し、今後の湿地管理の取組の進め方を検討する際の基礎資料づくりを実施しました。
我が国では、農耕などを通じ、人間が自然環境に長年かかわることによって里地里山が形成・維持されていますが、こうした里地里山と類似の二次的自然地域は世界中に存在します。しかし近年、人口増加や過疎化・高齢化、経済のグローバル化、都市化、貧困、あるいは伝統的知識や管理システムの消失・変質などさまざまな要因により、多くの二次的自然地域が危機に瀕しています。生物多様性保全と人間の福利向上のためには、地域の特異性に配慮しながら、里地里山といった二次的自然地域における人間と自然の健全な関係の維持・再構築を進めていくことが必要です。これは、資源枯渇などの環境リスクを軽減しつつ、人々の生活向上や社会的公正を担保する「グリーン経済」の考え方とも一致します。
このため我が国は、里地里山を例として、我が国の自然観や社会・行政のシステムに根づく自然共生の智慧と伝統を活かしつつ、現代の科学や技術を統合した自然共生社会づくりを世界に発信するため、「SATOYAMAイニシアティブ」の考え方を国連大学と共同で提唱してきました。
SATOYAMAイニシアティブを国際的に推進するため、2010年(平成22年)10月のCOP10において、世界中から政府、NGO、コミュニティ団体、学術研究機関、国際機関等多岐にわたる51団体が集い、SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ(IPSI)が創設されました。平成26年3月現在、IPSIの会員は16か国の政府機関を含む158団体となり、定例会合、協力活動、SATOYAMAイニシアティブ推進プログラム等により、SATOYAMAイニシアティブの活動を国際的に推進しています。
平成25年9月に福井県福井市において、「SATOYAMA イニシアティブ国際パートナーシップ第四回定例会合」が開催されました。2012年(平成24年)10月の第三回定例会合でのIPSI戦略の合意を受けて、「生物多様性の保全と人間の豊かな暮らしの実現に向けたIPSI戦略の実施」をテーマにIPSI 総会と公開フォーラムが行われ、IPSI戦略を実施するためのIPSI行動計画が承認されました。また、第四回定例会合にあわせて、SATOYAMAイニシアティブの理念を国内において推進するための組織である「SATOYAMAイニシアティブ推進ネットワーク」が設立されました。(SATOYAMAイニシアティブ推進ネットワークについては3(3)イ参照)
また、IPSIパートナーシップの繋がりを活かし、会員が他会員に対して広く協力を求めるプロポーザル公表の機会の提供や複数の会員が協力して行う里山保全に資する活動として、IPSIの定例会合等において「IPSI協力活動」の認証を行っています。2013年(平成25年)9月までに29件の協力活動が認証され、IPSIホームページ上で発信されています。
SATOYAMAイニシアティブ推進プログラム(COMDEKS)は、国連開発計画を実施機関として、環境省、生物多様性条約事務局、国連大学とが連携して進められている協力活動の一つです。地域コミュニティによる二次的自然環境の維持・再構築のための現地活動を支援するとともにその現地活動の成果に関する知見を集積し発信していくことを目的として進められています。2011年(平成23年)に世界10か国を対象に活動が開始し、2013年(平成25年)6月には新たに10か国が支援対象となり、世界20か国でSATOYAMAイニシアティブ推進プログラムが実施されています。
「SATOYAMA国際会議2013inふくい」を契機とした福井県の里山里海湖の保全再生、振興
平成25年9月にSATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ第四回定例会合(IPSI-4)が福井県で開催されました。福井県ではIPSI-4を含む1週間を「SATOYAMA国際会議2013inふくい」と位置付け、市町や自然再生団体等の協力のもと、小学生が活動成果を発表しあうフォーラムの開催や、参加外国人メンバー・全国の先進地活動団体との交流、県内の里山先進地の視察など、福井の里山の魅力発信と里山保全・活用の意識醸成に向けたさまざまな関連行事を実施しました。
10月には、国際会議の成果を活かし、里山里海湖(さとうみ)の魅力をさらに知ってもらうとともに生物多様性の確保と豊かな暮らしの承継につなげるため、「福井県里山里海湖研究所」を開所しました。同研究所では「地域を元気にする実学研究」の拠点として、研究、教育、実践の3つを柱に、生物多様性の保全・再生のほか、里に伝わる伝統・文化を活かした地域づくり等を行います。同研究所は、福井県を代表する里海湖でありラムサール条約登録湿地でもある三方五湖の湖畔に立地しています。三方五湖の一つ水月湖からは、地質学的年代測定の世界基準として認定された「年縞」(約7万年にわたり湖底に堆積した層)が採取されており、研究所ではこの「年縞」についても研究と活用を行い、福井県の里山里海湖を元気にする取組を行っていきます。
人と自然が共生した社会を実現していくためには、将来にわたり自然の恵みを得られるよう、国土全体にわたって自然環境の質を向上させていくことが必要です。我が国は豊かな自然環境に恵まれており、古くから人々の暮らしの中に自然の恵みを取り入れ、その恵みを絶やさないように手入れをしたり、利用を制限したりしながら自然と共生してきました。人々のライフスタイルが変化する中で、地域固有の自然やそれがもたらす恵みが地域社会に果たす役割も変化しています。
本項では、地域の人々と協力して自然の魅力や恵みを活用した地域づくりに取り組んでいる事例や、自然との良好な関係を取り戻し自然と上手に付きあうための取組について紹介します。
ア 地域に守られる国立公園の自然風景
日本は、亜熱帯から冷温帯まで広がる南北に細長い島しょであり、また起伏に富んだ多様な地形・地質等を有していることから、豊かな生物相、海岸地形や山岳地形まで広がる変化に富んだ風景地が形成されています。このような優れた風景地や豊かな生態系の多様性を保護し、かつその利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資することを目的として、国立公園が指定されています。
日本では、昭和9年3月に初の国立公園として、瀬戸内海、雲仙、霧島の3国立公園が誕生し、同年11月には、阿寒、大雪山、日光、中部山岳、阿蘇の5国立公園が指定されました。平成26年はこれらの国立公園が指定されて80周年を迎えます。また、本年3月には釧路湿原国立公園以来の27年ぶりに慶良間諸島国立公園が31番目の国立公園として新規指定されました。日本の国立公園の特徴は、その土地の大部分を国立公園担当部局が所有する米国、カナダとは異なり、土地の所有形態に関係なく指定されることです。このため国立公園の区域の中には、民有地も多く含まれており、集落や住宅地等の居住地、農林業や水産業等の産業が行われているところもあります。日本の国立公園は、80年も前から地域の人々の暮らしや産業との調和を図りながら、互いに連携し、地域に愛される宝として、現在にいたるまで優れた自然環境を継承してきました。我が国が世界に誇る風景地として豊かな自然を保全するとともに、地域のくらしの維持や農林水産業等の活性化とも調和する形で、さまざまな主体が協働し国立公園の魅力をより一層向上する取組が進められています。
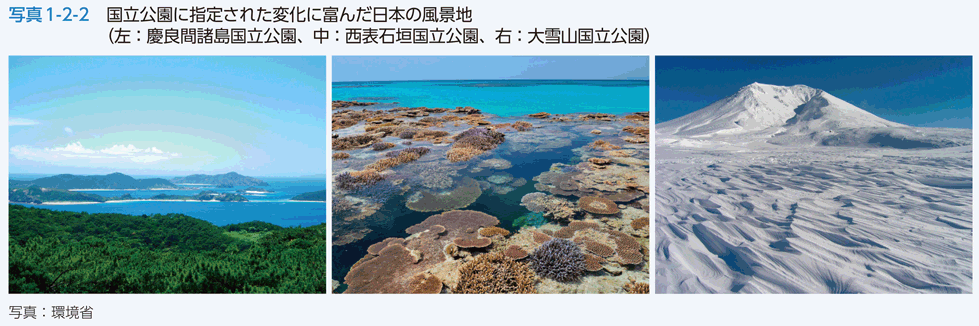
一例として、農畜産業を核に地域のくらしによって守られてきた「阿蘇くじゅう国立公園・阿蘇の草原再生」についてご紹介します。阿蘇くじゅう国立公園阿蘇地域は、周囲約100kmに及ぶ世界最大級のカルデラ地形をもつ阿蘇山の火山景観と、裾野に広がる広大で優美な草原景観が評価され、昭和9年に国立公園に指定されました。これらの阿蘇の草原は、火山活動の影響により森林が発達しにくい影響下で、古くから人々が牛や馬を飼うための「放牧」「採草」「野焼き」を繰り返し行ってきたことにより維持されてきました。つまり、阿蘇の草原景観は、地域のくらしと農畜産業と自然との共生の産物です。

しかし、生活様式や社会経済状況の変化により、野草利用の減少、農畜産業の後継者不足等が生じ、これまでどおり草原を維持・管理することが困難になっています。そこで、かけがえのない阿蘇の草原を未来へ引き継ぐことを目指し、国、自治体、地元牧野組合、NPO法人、専門家、地域住民が参加した「阿蘇草原再生協議会」を設置し、共通の目標の下、草原再生に向けた取組を行っています。例えば、都会からのボランティアも参加して行う野焼き活動、草原の野草によって育てられた野菜の生産者の集まり「阿蘇再生シール生産者の会」の結成、阿蘇の草原で育つ「あか牛」を提供する「阿蘇あか牛肉料理認定店」制度の創設、多くの企業・団体や一般市民の皆様からの阿蘇草原再生募金による助成活動等が行われており、各主体が野草の活用の促進や草原再生のPR等に取り組んでいます。まさに、国立公園の優れた自然を地域の宝として、地域とともにその保全や活用を進めている事例といえます。
イ 国立公園の観光振興・地域づくりへの貢献
国立公園は現在日本の国土面積の約5.6%を占め、普段のくらしの中では出会えない自然や風景を誰もが楽しめる場所として、年間約3億人を超える人々が訪れています。自然環境とふれあい、自然の大切さについて理解を深める場所として、自然を紹介・解説するビジターセンター、歩道、山小屋、キャンプ場、休憩所等の施設整備が進められてきました。国立公園におけるより質の高い利用を提供するため、これまでの登山・ハイキング・風景鑑賞だけでなく、自然に実際にふれ・学び・体験するエコツーリズム等も推進しています。国立公園はこのように、豊かな自然環境を保全すると同時に、その自然資源を持続的に活用する場となっており、地域における観光施策、地域づくり、地域社会の活性化へと資するものです。この機能をさらに効果的なものとするためにも、国立公園と地域における人々とが共通した目標をもち、連携しつつそれぞれの特徴を活かした取組を協働で進めることが重要です。
地域の取組であるジオパークと国立公園が連携している事例として、雲仙天草国立公園雲仙地域における取組を紹介します。雲仙は、昭和9年に日本で最初の国立公園の一つとして指定され、高度経済成長期には、国内有数の温泉地として賑わいました。しかし、平成2年からの普賢岳噴火や旅行ニーズの変化への対応の遅れから、観光客が半減しています。そのような中、地元自治体を中心に世界ジオパーク認定を機に地域の再活性化の気運が高まっており、国立公園としても、ジオパークと連携して自然資源を活かした利用の促進に取り組んできました。平成24年には、環境省において噴火以降規制されてきた登山道を、平成新山の火山活動を感じられるよう工夫を凝らしたルートとして再整備しました。そのほか、雲仙地域に整備された2か所のビジターセンターを中心に、ジオパークにかかわる展示やジオツアーの開催を行っています。
現在国内では、33地域が日本ジオパーク(そのうち6地域が世界ジオパークに登録)として認定されていますが、そのうち21地域が国立公園と重複しています。国立公園に指定されている地域は、優れた自然風景地の構成要素として重要な地形・地質が評価されており、国立公園の指定を受けることにより、これらの地形・地質の改変が制限されることは、ジオパークの保護担保措置にもなっています。また同時に、これらの自然資源にふれて、楽しんでもらうという観点は、ジオパークと国立公園の共通する理念にもなっており、互いに連携することで、より質の高い利用をより多くの人々へ提供することが可能となり、地域の観光振興にも貢献しています。



一方で、国立公園の利用者数は、平成3年をピークに減少傾向にあります。平成25年の世論調査によると、国立公園に「行きたい」「どちらかといえば行きたい」を選んだ国民は、全体の85.4%を占めます。その回答者に国立公園に行く理由を尋ねたところ(複数回答可)、「風景を楽しむ」が最も多く86.0%、「温泉に入ってくつろぐ」が63.8%、「お寺や神社などを見物する」が45.7%、「地域の食材を使った食事を楽しむ」が44.9%となり、「登山やハイキング等を楽しむ」、「動植物を観察する」を上回る結果となりました。国民が、文化、食、やすらぎ等地域の自然の恵みを求めていることがわかります。これらの自然の恵みを最大限に活かすことは、国立公園の利用を通じて地域経済に貢献し、さらには地域の文化や産業を活性化することにもつながっているのです。
さらに、海外へ目を向けてみると、訪日外国人旅行者を対象にした質問では、「訪日旅行中にしたこと」及び「次回の訪日旅行中に実施したいこと」の両者の第4位として「自然・景勝地観光」が入りました(平成25年観光庁 訪日外国人消費動向調査)。また、訪日外国人向けの主要なガイドブックを分析したところ、「National Park」が観光ポイントの一つとして詳しく紹介されていることが分かっています。
このようなことから、「National Park」のブランドは、外国人にとって日本を訪れるきっかけになり得るほど魅力あるものであり、観光立国を目指す日本にとって、「国立公園」が重要な国際観光資源となっていることがわかります。標識やビジターセンターの多言語化や外国人向け利用プログラムの開発等、今後、これらの訪日外国人の受入れ体制の強化を図り、観光面から我が国の経済活動に貢献すること、そこを訪れた訪日外国人に豊かな日本の自然と人との共生によって形づくられた日本独特の風土等にふれ、理解を深めてもらうことは、国立公園が果たすべき重要な役割の一つといえます。
ア 世界自然遺産における地域社会との協働による保全管理
我が国では、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づき、屋久島、白神山地、知床及び小笠原諸島の4地域が自然遺産として世界遺産一覧表に記載されています。世界遺産は、「顕著で普遍的な価値」、すなわち世界で唯一無二の価値を有するとして認められた重要な地域等であり、その価値を将来にわたって維持するため、それぞれの地域に応じた適正な保全管理が求められます。


これらの遺産地域では、関係省庁・地方公共団体・地元関係者からなる地域連絡会議を設置し、自然科学や社会科学の専門家による科学委員会(遺産地域ごとに設置)からの助言を踏まえて、それぞれの遺産地域の管理についての合意形成や連絡調整を行っています。このように、行政と地域、学識者等が連携し一体となることで、遺産地域における観光利用や豊かな自然資源を活用した産業と自然環境保全との両立など、地域ごとに異なる課題への対応が進められています。
自然遺産として我が国で初めて世界遺産一覧表へ記載された屋久島では、平成5年に記載されて以降、来島者が増加し、平成24年には30.5万人(平成5年比で約1.5倍)が訪れています。産業別人口をみると、第一次・第二次産業の就業人口の落ち込みを第三次産業の就業人口増加が吸収しており、産業別純生産でも第三次産業は大きな伸びを見せています。また、全国の離島人口が減少傾向を見せる中で屋久島は現状維持を続けており、利用者の増加は屋久島の地域振興に大きく寄与しているといえます。一方で、遺産地域にある縄文杉については、約10年前に年間4万人程度だった利用者が、平成20年には年間9万人まで増加し、その後年間8~9万人で維持されています。遺産地域を訪れる利用者数の増加に伴い遭難件数の増加、利用施設のオーバーユース、登山道や避難小屋周辺の植生の荒廃等の課題が生じていますが、自然環境の保全とその利用を両立させ、貴重な資源である自然環境の魅力を維持するため、関係機関や地元関係者が連携し、環境保全及び適正利用対策として登山道やトイレなどの施設整備、携帯トイレの導入、マイカー規制の実施と登山バスの運行などを行っています。平成21年には、屋久島町エコツーリズム推進協議会が発足し、山岳部に集中する利用の分散化を進める策として、島内の各集落に今も残る昔ながらの生活様式や伝統を体験するエコツアーの導入を推進するとともに、屋久島でエコツーリズムを実施する際の心得やルールをまとめた「屋久島ルール」の作成を進めています。
また、海と陸の生態系の豊かな繋がりが評価され平成17年に世界遺産一覧表へ記載された知床では、海域の生物多様性の維持と漁業活動の両立を図るため、環境省と北海道によって平成19年に「多利用型統合的海域管理計画」が策定されました。この管理計画には、漁業に関する公的な規制のほか、漁業者による自主的な資源管理の取組が組み込まれ、知床の海の生物多様性を維持しながら地域の生業である漁業を両立させる管理方式が実現されています。この管理方式は、遺産地域の新しい管理手法のモデル「知床方式」として世界的にも高く評価されています。
イ 地域コミュニティを主体とした生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)の取組
生物圏保存地域(BR: Biosphere Reserves)は、ユネスコの「人間と生物圏(MAB:Man and Biosphere)計画」の一環として実施している、生物多様性の保全と持続可能な発展との調和を図る地域の登録事業で、我が国ではその通称としてユネスコエコパークと呼んでいます。
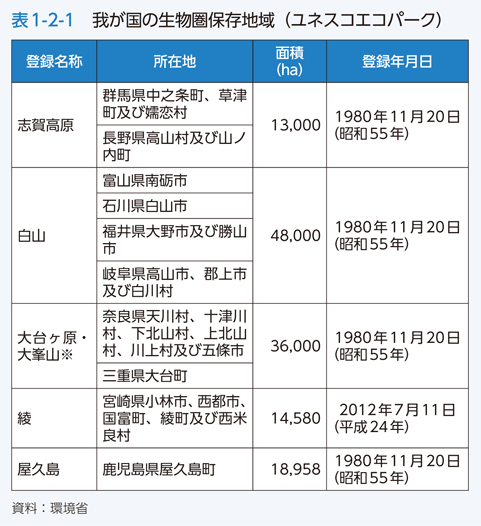
世界自然遺産が、顕著な普遍的価値を有する自然地域の保護を目的とする一方、生物圏保存地域は、生態系の保全と持続可能な利活用の調和(自然と人間社会の共生)を目的としており、「保存(生物多様性の保全)」、「経済と社会の発展」及び「学術的研究支援」の3つの機能を発揮するため、生物圏保存地域には、ゾーニングとして「核心地域」と「緩衝地域」のほか、社会と経済の発展を図る地域である「移行地域」の設定が求められています。登録総数は、117か国、621地域(平成25年5月現在)で、国内では、昭和55年に登録された「志賀高原」、「白山」、「大台ヶ原・大峯山」※及び「屋久島」、平成24年に登録された「綾」の5件が登録されています。
このうち「綾」では、日本最大規模で残る原生的な照葉樹林の厳正な保護のほか、林野庁等の関係行政機関、保護団体及び地域住民の協働による照葉樹林の復元等を目指す取組とともに、有機農業やエコツーリズムの推進など、自然と人間社会の共生に配慮した地域振興が行われています。
平成25年9月には、日本ユネスコ国内委員会第26回人間と生物圏(MAB)計画分科会において、「只見」(福島県)及び「南アルプス」(山梨県、長野県及び静岡県)の新規登録と「志賀高原」の拡張について、ユネスコに推薦することが決定されました。今後、2014年(平成26年)6月にスウェーデンにて開催される第26回ユネスコ人間と生物圏(MAB)計画国際調整理事会において、登録・拡張の可否が決定される予定です。
今回、推薦が決定したそれぞれの地域においても、豊かな自然を保全するとともに、自然や文化の特徴を活かした地域づくりが積極的に進められています。我が国においても、地域コミュニティを主体とする自然と調和した持続可能な地域づくりを後押しする国際的な枠組みとして、生物圏保存地域への注目が高まりつつあります。
※従来使用されていた「大台ヶ原・大峰山」の表記については、関係自治体(協議会)からの名称変更の申請を受けて、日本ユネスコ国内委員会第28回MAB計画分科会にて、「大台ヶ原・大峯山」に変更することが決定。(平成26年3月25日)
ア 里地里山保全活用の促進に向けた取組
里地里山は、集落を取り巻く農地、ため池、二次林と人工林、草原などで構成される地域であり、相対的に自然性の高い奥山自然地域と人間活動が集中する都市地域との中間に位置しています。里地里山の環境は、農業、林業などの人間の活動が、地域で培われてきた知識や技術を生かしながら風土に根ざした形で繰り返し持続的かつ安定的に行われてきた結果として形成され、維持されてきたものです。
このような里地里山は、かつては主に、農林業生産や生活の場として認識されてきましたが、今日では、これらに加え、絶滅のおそれのある野生動植物など生物多様性の保全、バイオマス資源、伝統的景観や生活文化の維持、環境教育や自然体験の場、地球温暖化の防止等、多様な意義や機能が注目されるようになっている重要な地域です。
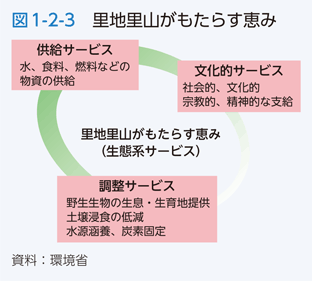
しかしながら、昭和30年代以降の燃料革命や営農形態の変化などに伴う森林や農地の利用の低下に加え、人口の減少や高齢化の進行により里地里山における人間活動が減少し、里地里山の生物多様性は劣化の進行が懸念されています。また、狩猟者の減少・高齢化にともなう狩猟圧の不足などによる人と野生鳥獣との軋轢の増大、耕作放棄地や手入れが十分に行き届かない森林による景観・国土保全機能の低下などの懸念が高まっています。
こうした背景を踏まえ、環境省では里山管理の担い手として都市住民などのボランティア活動への参加を促進しています。具体的には、ホームページなどにより活動場所や専門家の紹介などを行うとともに、研修会などを開催し里地里山の保全・活用に向けた活動の継続・促進のための助言などの支援を実施しています。これに加え、地域や活動団体の参考となる特徴的な取組事例の情報発信や、多様な主体が里地里山を共有資源として利用・管理する枠組みの構築に向けた自治体向けの手引書の策定なども行っています。
二次的自然の管理によって生じたバイオマス資源の再生可能エネルギーとしての活用~神奈川県秦野市の事例~
温室効果ガスの増加などによる地球温暖化の進行が世界的に懸念される中、従来多用されてきた石油や石炭などの再生不可能な化石燃料に代わり、バイオマスや太陽光、風力など再生可能なエネルギー資源への期待が高まりつつあります。
こうした中、里地里山などの二次的自然の管理を進め、その過程において発生する伐採木や刈り草などの植物系バイオマスをエネルギー資源として活用し、自然共生社会、低炭素社会の構築に同時に寄与する取組が進んでいます。
神奈川県央の西部に位置する秦野市は、丹沢山塊の大山などの山々に三方が囲まれ、豊かな里地里山が広がっています。秦野市内では各地で里山整備が活発に行われており、平成19年には、里山保全団体の活動拠点や青少年の野外学習の場として「表丹沢野外活動センター」を市が設立しました。この施設では、市内の里山保全団体の里山整備活動によって生じた間伐材や剪定木などの提供を受けており、それをチップ化してバイオマスボイラーで燃焼させることで、収容人数140人の宿泊棟や200名のホールを含め、施設全体の給湯・暖房を賄っています。1日当たり2~4m3のチップを用いており、年間で約19.5~39m3分の石油の消費を抑えています。
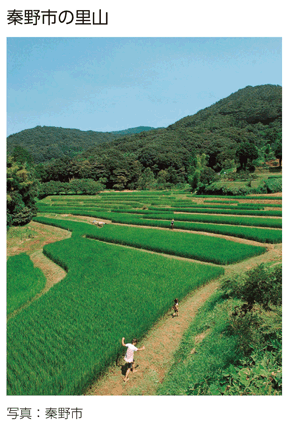

施設では、間伐材を提供した里山保全団体に対し、施設の利用券を交付し、団体による施設利用を促進しています。
このような取組によって里山の管理が進み、生物多様性の保全が図られるとともに化石燃料の消費が抑えられ、自然共生社会と低炭素社会の構築に貢献すると期待されます。
イ 多様な主体がつながるプラットホームの構築(SATOYAMAイニシアティブ推進ネットワーク)
平成25年9月、SATOYAMAイニシアティブの理念に賛同する多様な主体の連携を促進するための国内組織として「SATOYAMAイニシアティブ推進ネットワーク」が、企業、NGOなど民間団体、研究機関、行政機関等国内101団体の参加の下、発足しました。
本ネットワークでは、国内における多様な主体がその垣根を越え、さまざまな交流、連携、情報交換等を図るためのプラットホームの構築を通じて、生物多様性の保全はもとより、元気な里地里山などを創出する生業づくりや地域資源を活用した地域振興を推進し、里地里山などにおける生物多様性の保全や利用の取組を国民的取組へと展開していくことを目的としています。
本ネットワークの実効的な運用により、国内における意識醸成、取組の裾野拡大や質の向上が期待されます。
世界農業遺産―未来へ引き継ぐ、ふるさとの宝―
地球上には、人類共通の遺産である地域固有の伝統的な農業システムが数多く存在しています。農業システムとは、食料生産のための農業・農法だけではなく、生物多様性が保全された土地利用、伝統知識、農村文化、景観等も含む概念です。農業システムは人々の生活に不可欠な食料とともに生態系サービスを提供しています。
世界農業遺産は、近代化が進む中で失われつつある伝統的な農業システムを次世代へ継承していくことを目的に、食料の安定供給を目指すFAOによって2002年(平成14年)に認定が開始されました。ユネスコの世界遺産が遺跡や歴史的建造物等の「不動産」を保護することが目的であるのに対し、世界農業遺産は次世代に継承すべき伝統的な農業・農法を「システム」として一体的に認定し、これを持続的に活用しながらシステム全体を維持・保全していく「動的保全(dynamic conservation)」を目指しています。
現在、世界11か国25地域が世界農業遺産に認定されていますが、先進国で認定を受けているのは日本だけです。まず、平成23年に佐渡市「トキと共生する佐渡の里山」と石川県能登地域「能登の里山里海」が認定されました。平成25年5月には、FAO、農林水産省、石川県の共催により、能登地域において世界農業遺産国際会議が開催され、静岡県掛川地域「静岡の茶草場農法」、熊本県阿蘇地域「草原の維持と持続的農業」、大分県国東半島・宇佐地域「クヌギ林とため池がつなぐ農林水産循環」が新たに認定を受け、国内の世界農業遺産認定は5地域となりました。

認定地域では、生物多様性や農村景観の保全の取組はもとより、農産物のブランド化や観光との連携によるグリーンツーリズム等、農業振興・地域活性化の取組が活発化しています。例えば、トキをはじめとする多様な生きものが棲む水田環境から生産された佐渡のお米や、茶草場の草を刈り取り、茶園の畝間に敷くことで生物多様性保全と良質な茶を生産する茶草場農法による掛川のお茶等、それぞれの地域で世界農業遺産認定をテコにブランド化が進められ、付加価値の高い農産物として、競争力を高めてきています。さらに、棚田等の優れた農村景観や農業文化を観光資源とするグリーンツーリズムの取組も各地域で展開されてきています。
世界農業遺産は、このような農業振興・地域活性化を通じて、地域コミュニティを強化することにもつながっています。また、世界的に重要であることを証明する世界農業遺産の認定を受けることで、地域の人々は自分達の実践してきた農業・農法に自信と誇りを取り戻しています。地域で人々が集まり、生物多様性や農村景観の保全、農業文化の継承のための知恵を出し合いながら、次世代に継承すべき重要な農業システムの動的保全に向けた取組が各地で広がっています。
自然資源を利用した自立する地域づくり
私達の暮らしは食料をはじめとして自然からの恵みによって支えられています。便利で快適な生活を求めた結果、自然資源の利用は増えていく一方ですが、果たして地球はこれから先いつまでもそれに応え続けることができるのでしょうか。社会の持続可能性を測る物差しの一つに、環境への負荷を総合的に測る指標である「エコロジカル・フットプリント」があります。この考えでは、人間による自然資源の消費と排出が、地球が生産し排出物を吸収できる容量(バイオキャパシティ)の範囲内であれば持続可能ということになります。ところが、現在の世界中の人々の生活には地球1.5個が必要であり、日本はその世界平均のさらに約1.5倍の負荷を与えているとされています。また、日本の地域別のエコロジカル・フットプリントを調べると、東京都の一人当たりの値は全国平均より約9%高くなっています。
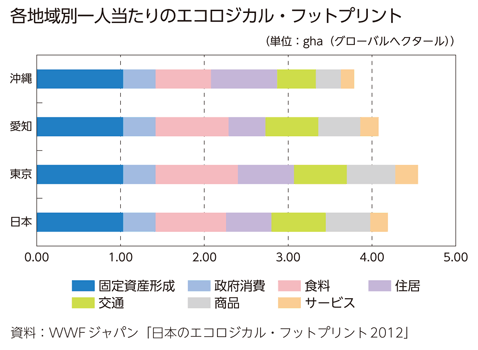
自然資源の利用量、供給量には地域差があり、例えば水源の涵(かん)養など、都市は大きな負担をすることなく地方が供給する生態系サービスの提供を受けています。このような関係を見直し、都市に存在する資金や人材、情報等を地方に提供し、都市と地方がお互いに支え合うことが必要となっています。平成24年9月に閣議決定した生物多様性国家戦略2012-2020では、生物多様性の保全と持続可能な利用に向け、生態系サービスの需給でつながる地域を「自然共生圏」とし、連携や交流を深めていく仕組みの構築を課題としていますが、すでにいくつかの自治体では、都市と地方との新たな関係の構築に向けた取組がなされています。
山口県の周防大島は瀬戸内海の島々の中で三番目に大きな島で、かつてはみかん栽培が盛んでしたが、過疎と高齢化が進んでいます。しかし、島外からの移住者が地元の原料を使い「土地とつくり手の魂が感じられる」ジャムづくりをはじめたところ、これが評判になり島外からのお客さんで賑わいが生まれ、それに触発される形で移住者が集まりつつあります。
また、岡山県真庭市の建材メーカーでは地場産の木材も使いながら集成材などを製造していますが、工場で出る木くずを利用し自家発電を行うことで電気代の支出をなくしただけでなく余った電気を売電しています。このことは、余剰のバイオマス資源を利用して自立するとともに、都市に電気を供給する代わりに売電代として収入を得ることによる支え合いを実現し、さらには化石燃料の使用や調達にかかるエネルギーの節約にもつながり、地球温暖化防止に貢献しています。
このような、地元の原料を使い、地元の人を雇用し、地元の知恵も取り入れながら進める物づくりは、高い付加価値により都会の人から支持され、地域づくりに貢献する「自然共生圏」の一つの姿といえます。
ア 一次産業の発展や自然との共生に不可欠な鳥獣被害対策
近年、一部の野生鳥獣が急速に個体数を増加させ、また、人里周辺や高山帯等へと生息域を拡大させています。その結果、これらの鳥獣が全国各地で農林水産業や生活環境、自然環境に深刻な被害を与え、地域の社会経済に大きな影響を及ぼしています。
ニホンジカやイノシシ、カワウ等による農林水産業への被害は極めて大きく、例えば農作物被害は年間200億円前後で推移しています。被害を受けた農家が営農意欲を失う等の被害も深刻な状況です。また、優れた自然環境を有する国立公園の3分の2の地域において、ニホンジカが地表植物や樹木の皮を食べることにより、高山の希少植物が消失したり、森林の衰退を招いたりする生態系被害が確認されています。さらには、人里や街中に現れた鳥獣が住民へ危害を加えたり、列車や自動車への衝突事故を起こす等、国民生活に与える被害も大きくなっています。


このような鳥獣被害への対策として、農作物等を守るための防護柵の設置、人里への出没を抑制するための耕作地周辺の藪の刈り払い、鳥獣の個体数や生息密度を一定水準まで抑制するための捕獲等、各地でさまざまな取組が実施されていますが、被害の大幅な減少には至っていない状況であり、今後もさらなる対策の推進・拡充が求められています。
特に今後も個体数や生息域が拡大していくと考えられているニホンジカ等の鳥獣に対しては、捕獲対策を一層強化していくことが重要ですが、捕獲の担い手である狩猟者は減少と高齢化が著しく、将来の担い手の確保及び育成が大きな課題となっています。
このため、餌付けにより誘引された複数個体を囲いわなにより一斉に捕獲するなどの効率的な捕獲手法の開発・実証や、被害農家を含めた地域ぐるみでの捕獲を推進するための体制づくりを進めています。さらに、若い世代への狩猟免許の取得促進や狩猟がもつ社会的意義の啓発を目的としたフォーラムも開催しています。

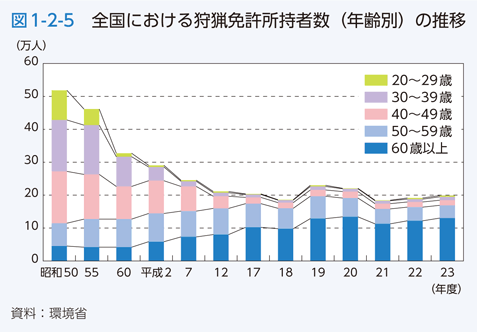
鳥獣被害対策を効果的に進めるため、平成25年12月に農林水産省が共同で「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」を取りまとめ、ニホンジカとイノシシの個体数を平成35年度までに半減させることを目指すこととして、捕獲の強化を図ることとしました。また、ニホンジカ等の積極的な管理を推進するため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置に関する中央環境審議会の答申(平成26年1月)を踏まえ、都道府県等により集中的かつ広域的に管理を図る必要がある鳥獣の捕獲等をする事業の創設や、捕獲等をする事業の認定制度の導入等を盛り込んだ鳥獣保護法の一部を改正する法律案を第186回国会に提出しました。
さまざまな被害を及ぼす鳥獣の適切な管理は、自然環境や生物多様性の保全及び農林水産業の発展のために欠かせないものです。このような鳥獣被害対策の意義や重要性について国民各層の理解を深めつつ、引き続き各種取組を推進していかなければなりません。
イ 絶滅危惧種の保全と地域活性化の両立を目指した取組について
近年、絶滅危惧種の生息地の保全と地域経済の活性化を両立させ、共生を目指す取組が、各地で行われています。例えば、新潟県佐渡市のトキの野生復帰の取組の推進では、トキのエサ場づくりなどの生息環境整備や島外との交流などトキとの共生を目指した地域づくりを進めてきた中、平成20年のトキ放鳥を機に「朱鷺(とき)と暮らす郷(さと)づくり認証米」制度を開始しています。環境への負荷の少ない生きものを育む農法によって生産されたお米に付加価値を付けて販売することで、この農法に取り組む生産者の支援を兼ね備えた制度が特徴です。認証制度は平成20年から始められ、これに取り組む農地面積(農家数)は平成24年には1,367ha(684戸)にまで拡大し、佐渡市全体の作付け面積5,500haの25%までになっています。
また、長崎県対馬市佐護地区では、ツシマヤマネコの生息環境を改善するため、環境省とともに米づくり勉強会や生きもの調査等を実施する中、平成23年に有志による佐護ヤマネコ稲作研究会が発足し、ツシマヤマネコと共生する稲作を目指した認定田で栽培された「佐護ツシマヤマネコ米」の販売を開始しています。
両地区とも、販売代金の一部が生息地環境整備や保護活動に活用され、実際に米づくりや生息環境整備に取り組む人達だけではなく、それを応援したい地域内外の消費者を含め、生きものをシンボルとした活性化を目指す地域全体によってトキやツシマヤマネコとの共生を目指す地域づくりを支える取組が広がっています。
なお、絶滅危惧種の保全に関しては、絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律について、平成25年3月に中央環境審議会より「絶滅のおそれのある野生生物の保全につき、今後講ずべき措置について」の答申を得たことを受け、第183回国会において罰則の強化等を図る改正がなされ、同年6月に公布されました。(詳細は第2部2章1節参照)
ウ 外来種対策の実施による効果
我が国は、野生生物の分布は複雑な地形的条件等により制限され、それゆえに亜種・変種レベルも含めて固有種の比率が高いなど、地域固有の多様な生態系が形成されています。その一方で、戦後急速に進んだ経済・社会のグローバル化を背景として、人と物資の移動が活発化し、国外又は国内の他地域から、本来有する移動能力を超えて、人為によって意図的・非意図的に自然分布域外に導入され、野生化する外来種が増加しています。こうした外来種の中には侵略的外来種が含まれており、それらによる在来種の捕食や交雑による在来種の遺伝的かく乱、寄生生物や感染症の媒介等の生態系への被害が問題となっています。さらには咬傷(こうしょう)等の人の生命や身体への被害、食害等による農林水産業への被害に加え、文化財の汚損、悪臭の発生、景観・構造物の汚損等、さまざまな被害が及ぶ事例がみられます。
例えば、ハブや農作物を荒らすネズミを駆除する目的で明治43年に沖縄島、昭和54年頃に奄美大島に導入されたマングースは、近年まで年々生息地を拡大し、ヤンバルクイナやアマミノクロウサギなどの希少な野生生物を捕食し、その存続に大きな脅威となっています。平成24年度に仮想評価法を用いて両地域のマングース駆除に対する国民全体の年間の支払意志額を算出したところ、沖縄島北部(やんばる)地域、奄美大島ともに1,319億円となりました。これは実際にマングース防除に要した平成25年度予算の約700倍から1,300倍に当たるものでした。
また、アライグマの全国の農業被害は年々増加傾向にあり、平成23年度に約3億8千万円になりました。
さらに、経済的な視点からの評価はされていないものの、小笠原のグリーンアノールによる希少昆虫類の捕食による自然環境の価値の低下、ヌートリアによる農産物の食害や畦の破壊、カワヒバリガイによる用水路等の通水阻害、オオクチバスやブルーギルの捕食等による琵琶湖固有種のニゴロブナの減少に伴う地域の伝統的食文化(鮒寿司)への影響等さまざまな被害が確認されており、これらの防除実施にはそれぞれ多大な費用が発生しています。
加えて、侵略的外来種による被害は生物多様性に対してだけでなく、人の生命・身体への被害など、社会経済活動に対しても深刻な影響を与えています。例としては、セアカゴケグモ、タイワンハブ等による咬傷(こうしょう)被害が確認されていたり、カミツキガメやヒアリ等による咬傷(こうしょう)被害等のおそれが指摘されています。現在、空港など外来種が持ち込まれる可能性が高い場所において、定期的なモニタリングを実施するなどの水際対策を実施しています。
このように外来種対策の実施は、生態系への影響の防止のみならず、農林水産業、人の生命・身体への影響の防止に貢献するものであることが分かります。
現在、沖縄島北部及び奄美大島では平成34年度を目標に防除地域でのマングース根絶に向けた取組を推進しています。その結果、これまで希少鳥類などの個体数が回復している傾向が確認されています。また小笠原諸島では、平成23年に世界自然遺産に登録されましたが、グリーンアノール等の外来種対策の実施により、固有の生態系の維持回復を図ってきた成果が認められたものでもあり、今後ともその価値を維持するための取組が求められています。
なお、外来種対策としては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律について、平成24年12月に中央環境審議会から同法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置についての意見具申がなされたことも踏まえ、第183回国会において外来生物法について外来生物が交雑することにより生じた生物も規制対象とできるようにする等の改正が行われ、平成25年6月に公布されました。(詳細は第2部2章1節参照)
いきものログ
環境省生物多様性センターでは、平成25年10月に全国の生物多様性データを統合的に共有化して提供する新たなウェブシステム「いきものログ」の運用を開始しました。
「いきものログ」には、自然環境保全基礎調査やモニタリングサイト1000など、生物多様性センターが実施した調査結果のデータが登録されているほか、環境省をはじめとする国の機関・都道府県・市区町村・研究機関・専門家・市民等が管理する生物多様性データを登録し、共有することができます。これらのデータはデータベースに一元的に管理されており、ウェブサイトで検索し、閲覧ダウンロードすることができます。また、地図表示機能を利用することによって、生物の分布情報を分かりやすく表示することが可能です。生物多様性データの登録は、インターネットに接続可能なパソコンからだけでなく、「いきものログ」専用アプリをスマートフォンにダウンロードすることで、スマートフォンからも簡単に行うことが可能です。
「いきものログ」運用の目的の一つは、さまざまな団体や個人が別々に管理している生物多様性データの共有化です。例えば、都道府県には質の高い膨大な生物多様性データが別々に蓄積されていますが、「いきものログ」を活用してこれらの情報を共有化して一元的に運用することにより、各都道府県は都道府県境を越えたシームレスなデータを得ることができ、ひいては全国の生物多様性データを共有化する効果が期待されます。一方、「いきものログ」には団体が独自の調査を実施する機能を備えています。この機能では、団体を登録することで環境省だけでなく、そのほかの国の機関・都道府県・市区町村・研究機関・専門家・市民グループ等が、「いきものログ」を利用して独自に団体主催の市民参加型調査を企画し、「いきものログ」の利用者を対象に調査を実施することができるほか、調査の実施者は独自にカスタマイズできる調査ページを「いきものログ」上に設置することができます。また、調査により収集されたデータは実施者が調査報告として「いきものログ」上で取りまとめ、一般に公開することができます。
環境省では、今後「いきものログ」を我が国の生物多様性データを総合的に管理する基幹システムとして位置付けていきます。
「いきものログ」 http://ikilog.biodic.go.jp/(別ウィンドウ)
| 前ページ | 目次 | 次ページ |