
私たちのいのちと暮らしは、生物多様性によって支えられています。その生物多様性が、驚くべきスピードで失われつつあります。生物多様性を守り、持続的に利用していくための取組が、いま世界中で大きなうねりとなりつつあり、その中心に日本が立とうとしています。
この章では、生物多様性をめぐるこれまでの経緯と、2010年(平成22年)のわが国での生物多様性条約第10回締約国会議に向けた取組などについて述べていきます。
(1)生物多様性とは
生物の多様性に関する条約(以下「生物多様性条約」という。)では、「すべての生物(陸上生態系、海洋その他の水界生態系、これらが複合した生態系その他生息又は生育の場のいかんを問わない。)の間の変異性をいうものとし、種内の多様性、種間の多様性及び生態系の多様性を含む。」と生物多様性を定義しています。極寒の極地から熱帯の赤道直下まで、乾燥地帯から湿地・水域まで、深海から高山までなど、地球上のあらゆる環境に、長い生命進化の歴史を経て、さまざまな生物が適応し、それぞれの場所において、昆虫が蛙に、蛙が蛇に食べられるといった食物連鎖や、クマノミ類とイソギンチャク類がともに暮らす共生関係のように、生物同士がさまざまなつながりを持って存在している状態と言い換えることもできます。
長い時間をかけた自然界の試行錯誤の結果として、さまざまな環境に見合った種類や量の生物が本来あるべき姿で存在する状態が生物多様性の良好な姿であると考えられます。したがって、必ずしも熱帯林のように種や個体の数が多い場所の方が、砂漠のように少ない場所よりも優れているというわけではありませんし、種数が多い方が良いといって、他の場所から色々な生物を持ち込むことが良いというわけではありません。また、気候の変化や病原菌の蔓延などのさまざまな外的要因を受けても全滅しないよう、さまざまな環境変化に適応できる遺伝的多様性に富んだ個体群が存在していることも、生物の種が生き残る上で重要です。種が同じであるからといっても、個体数が減少した場所に、十分な検討もせずに、他の地域から個体を持ち込むことには、交配によって地域間の遺伝的変異を減らしてしまう危険性も考えられるのです。
(2)生物多様性の恵み
我々の生存に不可欠な酸素は植物が作り出します。野菜や日本人の主食であるお米は野生の植物を改良してできた作物です。サンマや甘エビなど食卓を飾るさまざまな海産物は海から得られます。本や新聞などの紙製品も植物を元に作られています。さまざまな医薬品の多くも生物の働きを利用して開発されたものです。各地で身近に得られる食材を使った郷土料理のような伝統的な地域文化の多様性も地域の生物多様性に支えられています。森林や緑地は我々に憩いの場を提供するとともに、水源のかん養、土砂崩れの防止、気候の安定やヒートアイランド現象の緩和にも役立ちます。以上のように我々は当たり前と思い享受している事柄の多くを生物多様性のもたらす恵みに依存しています。人間は生物多様性のもたらす恵みなくしては日々の生活を送ることはできません。これら生物多様性の恵みの多くは、生物や生態系を適切に使うことで再生産が期待でき、将来にわたり持続的に利用が可能なものです(図5-1-1)。

人間も生物多様性を構成する生物の一種として地球上に誕生しました。今日、人間は科学技術を発達させ、地球上のさまざまな資源を活用し、便利で豊かな生活を求め続けています。その一方で、あまりにも大きくなった人間活動が、生物や生態系の再生産能力を超えた略奪的な利用を発生させ、地球規模で生物多様性に不可逆的な影響を与えています。その結果、現代は「第6の大量絶滅時代」ともいわれ、この数百年で過去の平均的な絶滅スピードのおよそ1,000倍という速さで生物種の絶滅が進んでいるとも言われています。
平成19年11月に閣議決定された「第三次生物多様性国家戦略」では、わが国の生物多様性の危機の構造を次の4つに分類しています。「第1の危機」から「第3の危機」は平成14年に策定された「新・生物多様性国家戦略」で整理されたもので、「地球温暖化による危機」は第三次生物多様性国家戦略で新たに追加されたものです(図5-1-2)。
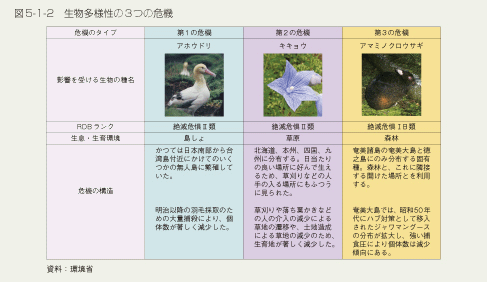
第1の危機は、人間活動ないし開発が直接的にもたらす生物種の減少、絶滅、あるいは生態系の破壊、分断、劣化を通じた生息・生育環境の破壊です。いわゆる自然破壊がこれに当たります。
社会的に生物多様性に対する認識が浅く、経済発展が優先されていた時代には、生物多様性の状況の把握や配慮もなされないままに開発が進み、またさまざまな生物が食料やペット・園芸目的などで採集され個体数を大きく減らしました。自然保護に代表される生物多様性への配慮の認識の広まりと各種の取組の推進、社会状況の変化により、現在では、かつてのような急激かつ大規模な破壊は少なくなってきていますが、人間が生活するためにはある程度の開発や採取が必要であることに変わりはなく、生物多様性に与える負荷を回避・低減できるよう努めていかなければなりません。また、過去の開発や多量の捕獲などが今日でも影響を与えている場合もあり、生息・生育地の環境の再生や個体数の回復のための取組も必要です。
第2の危機は、里地里山など自然に対する人間の継続的な一定の働きかけによって維持されてきた環境が、生活様式・産業構造の変化、高齢化の進行など社会・経済状況の変化に伴って変化し、その環境に依存していた種の生息・生育環境が失われつつあることです。
秋の季語として俳句に詠まれ、家紋に用いられるなど日本人に古くから親しまれてきたキキョウを例に挙げます。今日でも切り花や鉢植えとしては普通に見られますが、これらは生産されたもので、野生のものは絶滅の危機にあります。キキョウは日当たりの良い草原を好んで生育します。日本は湿潤温暖なため、草原は放っておくと次第に木が侵入し、森林に変わってしまいます。そのため、自然の状況下では、風当たりが強くて木が生えにくい場所や、山火事や土砂崩れなどにより森林が失われた場所に一時的に成立するのが普通であり、本来、キキョウはそのような草原に生えていたと想像されます。一方、日本には、古くから堆肥の原料、牛や馬の飼料、茅葺屋根の材料などを得る目的で、定期的に草を採取し、管理することで木を侵入させずに安定的に保ってきた草原が存在しています。このような定期的な草刈りが、結果的にキキョウの生育に適した環境を安定的に確保することになり、キキョウは、里地里山の草刈り場や土手などに普通に見られる種として存続してきたのです。ところが今日では、化学肥料や輸入飼料の普及、茅に代わる屋根葺き材の普及などにより、草原の利用価値が低下して放置され、木々が侵入し、あるいは他の用途に使われて、キキョウの生育できる環境が減少しています。このように、第2の危機では、持続可能な自然資源の利用形態自体が失われることにより、生物多様性の低下を招いています。
第3の危機は、人間により持ち込まれたものによる生態系のかく乱です。オオクチバス(ブラックバス)やアライグマなど外来種だけでなく、人間が作り出した化学物質などによる影響も含まれます。
外来種が生物多様性に及ぼす影響はさまざまで、北米原産のオオクチバスのように日本在来の水生生物を捕食することや、台湾原産のタイワンザルのように、日本固有で近縁のニホンザルと交配して雑種の子孫をつくることなどにより、日本の固有種や在来種の存続が危ぶまれています。外来種による生物多様性への悪影響を取り除く目的で駆除活動も行われていますが、多大な労力、時間、経費が必要となる上、完全な排除は極めて難しく、駆除活動を止めると、すぐに元の状態に戻ってしまうというやっかいな問題が起こっています。元々人間が海外から持ち込んだものが、野外へ逃げたり、意図的に放たれたりすることや、貨物に紛れて入り込んでしまうことが原因なので、外来種の導入やそれにつながる行動については、一人ひとりが十分注意していく必要があります。
地球温暖化による危機は、気温上昇による生息・生育環境の変化で、地球規模で生物多様性に影響を与える大きな課題です。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が平成19年にまとめた第4次評価報告書では、気候システムに温暖化が起こっており、温暖化の原因が人間活動による温室効果ガスの増加によるものであることをほぼ断定しています。同報告書では、全球平均気温の上昇が1.5~2.5℃を超えた場合、これまでに評価対象となった動植物の約20~30%で絶滅リスクが高まる可能性が高く、4℃以上の上昇があった場合は地球規模での重大な(40%以上の種の)絶滅につながると予測されています。生物季節や種の分布域の変化などが報告されているものの、地球温暖化を含む気候変動によりわが国の生物多様性にどのような影響が生じるかについて科学的知見が十分ではありませんが、島嶼、沿岸、高山帯など環境の変化に弱い場所を中心に生物多様性に深刻な影響が生じるものと考えられます(図5-1-3)。
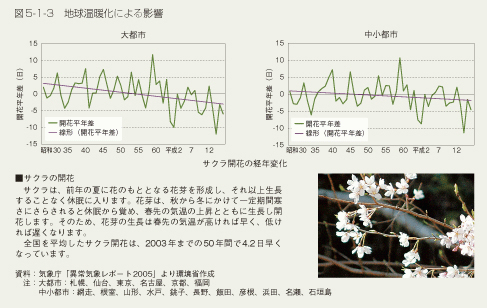
これら4つの危機は、単独で生物多様性に影響を与えるだけではありません。例えば、田園地帯では、社会経済の変化などにより離農が進み、里地里山が手入れされなくなる(第2の危機)とともに、経済的価値の低下などにより里地里山が売却され、宅地造成などの開発が進む(第1の危機)など、複数の危機が複合的に進行することもあります。
さらに、物流や経済のグローバル化に伴い、これらの危機は国内だけで完結するものではなくなってきました。ペットの無秩序な大量輸入は、原産国では野生生物の個体数の減少や種の絶滅といった第1の危機につながる可能性があるだけでなく、わが国でも逸出などによる外来種の増加と生態系への影響といった第3の危機につながる可能性があります。生物多様性の危機も国際的な視野に立って考えていかなければなりません。
(1)生物多様性条約発効にいたる背景と経緯
1980年代には、熱帯林の急激な減少や絶滅のおそれのある生物種の増加など、世界規模の深刻な自然環境の悪化が報告され、絶滅のおそれのある種の国際取引を規制するワシントン条約や、価値ある自然・文化遺産を保護する世界遺産条約のように、特定の場所や生物を守るだけでなく、人間活動のあらゆる局面で生物多様性に配慮する国際的なルールづくりの必要性が次第に認識されるようになりました。昭和59年に開催された国際自然保護連合(IUCN)の総会で、生物多様性を保全する条約の成立を目指すことが決定され、62年の国連環境計画(UNEP)管理理事会の決定に従い設置された専門家会合で検討が開始されました。その後、平成2年から政府間条約交渉会議が開始され、4年5月、ケニアのナイロビで開催された合意テキスト採択会議において生物多様性条約は採択されました。交渉の過程において、開発途上国に多く残された手付かずの自然環境の保護を訴える先進国と、開発を進めて経済発展を望む開発途上国、経済的価値を内在する豊かな遺伝資源を持つが技術力のない開発途上国と、遺伝資源を持ち出し高い技術力により製品化して利益を上げたい先進国や企業といった具合に、立場の違いを反映したさまざまな議論が行われました。本条約は、同年6月にブラジルのリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(UNCED)における主要な成果として、「気候変動に関する国際連合枠組条約」とともに、会議中に署名のため開放され、わが国をはじめ168か国が署名し、翌5年12月に発効しました。現在では、日本(5年に締結)を含め世界中のほとんどの国(21年3月末現在、190ヶ国及びEC。アメリカなどは不参加)が締結しています。条約の目的は、[1]生物多様性の保全、[2]生物多様性の構成要素の持続可能な利用、[3]遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分の3つからなります。[3]は、例えば、ある国に生育する植物を利用して外国資本が革新的な医薬品を開発し利益を上げた場合、その利益の一部を植物の採取された国にも公平に配分するという考え方を示しています。さらに、条項には、開発途上締約国に対する資金供与制度(資金メカニズム)や、技術協力なども含まれており、交渉時の開発途上国の主張が強く取り入れられたものとなっています。生物多様性条約を単に自然保護や生物多様性の保全に関する条約と理解する人もいますが、それだけではなく、日常生活や社会経済活動にもつながりの深い持続可能な利用や、遺伝資源と知的所有権といった国家間の利害関係をも含んだ条約となっています。
(2)生物多様性条約発効後の主な流れ
締約国会議(COP)は締約国全体の意思決定機関であり、条約に関するさまざまな議論がなされ、決議などの形で方針が決定されます。平成12年にケニアのナイロビで開催されたCOP5では、土地、水資源及び生物資源の統合的管理のための戦略であるエコシステム・アプローチが採択されました。条約の採択10年目にあたる14年にオランダのハーグで「対話から行動へ」をテーマに開催されたCOP6では、条約の3つめの目的である遺伝資源に関し「ボン・ガイドライン(遺伝資源へのアクセスとその利用から生じる利益配分の公正かつ衡平な配分に関するボン・ガイドライン)」が採択されました。締約国に義務を課すものではないとはいえ、条約交渉の論点の一つであった遺伝資源について一定の指針が採択されたことは重要です。また、生物多様性条約戦略計画が採択され、「現在の生物多様性の損失速度を、2010年までに顕著に減少させる」という「2010年目標」が示され、定性的ではあるものの、明確な目標が示されました。さらに、COP6の閣僚級会合でも「生物多様性が現在驚くべきスピードで失われている傾向を2010年までに止めるための措置を強化する」という内容を含む「ハーグ宣言」が採択されました。16年にマレーシアのクアラルンプールで開催されたCOP7で、保護地域の設定、管理、モニタリングなどの締約国及び条約事務局などが取り組むべき活動等を示した保護地域に関する作業計画が採択されました。また、政府、資源管理者、先住民及び地域社会、民間部門などによる生物多様性の利用が長期的な生物多様性の減少につながらないよう支援するための14の原則と実施上のガイドラインからなる「生物多様性の持続可能な利用に関するアジスアベバ原則およびガイドライン」が採択され、条約の2つめの目的である生物多様性の持続可能な利用について基本的な考え方がまとめられました。18年にブラジルのクリチバで開催されたCOP8では、生物多様性に与える影響が大きい企業などの民間部門が、条約の目的達成に貢献すべきという民間部門の参画についての決議が採択されました。決議では、企業に求められることとして、[1]企業の経営方針や企業行動を条約の3つの目的に適合させること、[2]2010年目標の達成に貢献するような自主的な活動について締約国会議に報告すること、[3]締約国会議や科学上及び技術上の助言に関する補助機関会合(SBSTTA)、専門会合などへの参加を奨励することとしています。このように、条約の2つめの目的である持続可能な利用に関し、それを利用し利益を得ている主体の一つである企業などの民間部門について参画を求めたことは重要です。また、2010年目標の達成状況を評価するため、COP8で世界の生物多様性の状況を15の指標から評価した「地球規模生物多様性概況第2版(GBO2)」が生物多様性条約事務局によって公表されました(第1版は平成11年に公表)。
(3)カルタヘナ議定書採択の経緯
条約交渉時には、遺伝子組換え生物等の影響についても議論されましたが、意見が対立し、条約19条第3項に、「締約国は、生物多様性の保全や持続可能な利用に悪影響を及ぼす可能性のある遺伝子組換え生物等の安全な移送や取扱などの手続を定める議定書の必要性及び態様について検討する。」と規定されるにとどまりました。この規定を受け、平成7年に開催されたCOP2で、議定書作成のためのバイオセーフティー作業部会の設置が決議され、11年まで6回にわたり議論がなされました。同年には、コロンビアのカルタヘナで特別締約国会合が開催され、議定書の作成について議論されましたが、合意に至りませんでした。12年にカナダのモントリオールで開催された特別締約国会合再開会合でようやく合意に達し、遺伝子組換え生物等の国境を越える移動に先立ち、輸入国が、遺伝子組換え生物等による生物多様性の保全と持続可能な利用への影響を評価し、輸出入の可否を決定するための手続など、国際的な枠組みを定めた「バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書」(以下「カルタヘナ議定書」という。)が採択され、15年9月に発効しました。21年3月末現在、日本(15年締結)を含め152ヶ国及びECが締結しています(アメリカ、カナダ、オーストラリアなどは不参加)。
(4)G8と生物多様性
条約以外の国際的な動きとしてG8における取組が挙げられます。平成19年にドイツのポツダムで開催されたG8環境大臣会合では、生物多様性が初めて主要議題として取り上げられ、気候変動とともに大きなテーマとして議論されました。その結果は、議長総括にまとめられ、付属文書として「ポツダム・イニシアティブ-生物多様性2010及び10の行動」が基本的に支持されました。イニシアティブには、生物多様性の地球規模の損失における経済的重要性(生物多様性の地球規模の経済的価値、生物多様性の損失に伴うコスト等の分析に着手する)、科学(科学と政策の間の接点向上に取り組む)、生産と消費のパターン(政府、産業界、消費者などを巻き込む政策の統合強化など)、侵略的外来種(種の特定、阻止及び統制管理における取組の拡大)などが盛り込まれました。
(5)生物多様性をめぐる最近の国際的な動向
平成20年は生物多様性をめぐり国際的にさまざまな動きがありました。5月にドイツのボンでカルタヘナ議定書第4回締約国会議(MOP4)(5月12日~16日)と生物多様性条約COP9(19日~30日)が開催されました。MOP4では、遺伝子組換え生物等の国境を越える移動から生じる「損害」についての「責任と救済」に関する国際的な規則の検討について議論が行われ、今後作業グループを開催し、MOP5で何らかの法的拘束力のある文書として作成する方向で検討し、報告することが決議されました。COP9には、締約国のほか、国際機関やNGOなどのオブザーバーを含め約7,000人が参加し、約200のサイドイベントが開催されました。2010年目標の達成に向け、各課題の進捗状況や今後の取組強化の方向性について議論されたほか、2010年目標を含む条約戦略計画の見直しプロセス、遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する国際的枠組みの2010年までの検討プロセス、バイオ燃料を含む農業と生物多様性、海洋及び沿岸の生物多様性、気候変動と生物多様性などが議題として議論されました。またドイツ銀行のスクデフ氏より生物多様性の喪失による経済影響を分析する「生態系と生物多様性の経済学(TEEB)」の中間報告が行われました。さらに、ドイツ政府による「ビジネスと生物多様性イニシアティブ」の「リーダーシップ宣言」が行われ、日本企業9社を含む全34社が参加、署名しました。これは、同イニシアティブに賛同する企業は、条約の3つの目的に同意し、これを支持するとともに、経営目標に生物多様性への配慮を組み込み、企業活動に反映させることを宣言するものです。また、最終日にはCOP10が22年10月18日~29日に愛知県名古屋市で開催されることが満場一致で決定されました(MOP5は10月11日~15日に名古屋市で開催)(図5-1-4)。
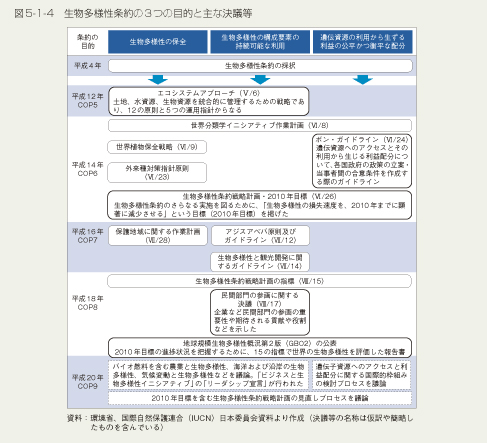
COP9開催期間中にあたる5月24日~26日には、兵庫県神戸市でG8環境大臣会合が開催され、「神戸・生物多様性のための行動の呼びかけ」が合意されました。同呼びかけでは、[1]2010年目標の達成とフォローアップ、[2]生物多様性の持続可能な利用、[3]生物多様性と保護地域、[4]民間参画、[5]生物多様性のモニタリングのための科学の強化、の5項目が生物多様性に関するG8各国に共通の重要課題として確認されるとともに、世界の国々に対し行動を促すよう呼びかけています。また、開催国であるわが国は、「『神戸・生物多様性のための行動の呼びかけ』の実施のための日本の取組」として、自然と共生する社会づくりを世界に発信する「SATOYAMAイニシアティブ」、東アジアを中心としたサンゴ礁保護区ネットワーク化、ビジネス・研究者・NGOなどのさまざまな利害関係者間の情報交換・対話などを促進する「神戸生物多様性対話」、「地球規模生物多様性モニタリング・ネットワーキング・イニシアティブ」などに取り組むことを世界に向けて表明しました。
平成20年9月には、日本が主催するアジア太平洋地域の非公式環境大臣会合である第16回アジア太平洋環境会議(エコアジア2008)が愛知県名古屋市で開催され、日本を含む11ヶ国、生物多様性条約事務局やUNEPなどの国際機関の代表などが出席しました。「生物多様性」をテーマに「生物多様性-2010年への道程」及び「生物多様性のための具体的な取組」に関して、アジア太平洋地域がとるべきスタンスや協力のあり方などについて議論が行われ、「生物多様性国家戦略の重要性」、「SATOYAMAイニシアティブの推進」、「生物多様性に対する認識の社会における主流化」などを議長総括としてとりまとめ、地域の共通認識の醸成を図りました。
平成20年10月には、スペインのバルセロナでIUCNの第4回世界自然保護会議が「多様で持続可能な世界」をテーマに開催され、日本政府は、(財)日本自然保護協会と共催で、SATOYAMAイニシアティブに関するシンポジウムを開催しました。また、日本がIUCNに資金提供を行っている東アジア保護地域プロジェクトの一環として行った「東アジア保護地域行動計画(英語)」の改訂・翻訳(日本語・中国語・韓国語)を記念したイベントが行われました。さらに、展示ブースを設置し、わが国の生物多様性施策やSATOYAMAイニシアティブなどを紹介したほか、(財)日本自然保護協会主催のイベントが行われ、COP10におけるNGOの役割をテーマに意見交換が行われました。
平成20年10月から11月に韓国の昌原(チャンウォン)でラムサール条約第10回締約国会議が開催され、日韓共同で提案した決議「湿地システムとしての水田における生物多様性の向上」(水田決議)が採択されました。この決議は、水田が多様な生物の生息地として重要であることを認識し、生物相調査や情報交換を行うこと、生物多様性を高めるような農法や水管理方法を特定し、実践することを締約国に求めています。
(6)生物多様性をめぐる最近の国内の動向
COP9開催などの国際的な流れに並行して、日本国内でも大きな動きがありました。平成19年11月には、二度の見直しを経た第三次生物多様性国家戦略が閣議決定されました。同戦略は二部構成となっています。第1部は戦略そのものに相当し、日本の生物多様性の現状とそれを脅かす危機を明らかにするとともに、日本の生物多様性のあるべき姿を、100年先を見据えた国土のグランドデザインとして示し、地方や企業による地域レベルの取組の必要性を強調しています。また、今後5年程度の間に重点的に取り組むべき施策の方向性を4つの基本戦略([1]生物多様性を社会に浸透させる、[2]地域における人と自然の関係を再構築する、[3]森・里・川・海のつながりを確保する、[4]地球規模の視野を持って行動する)にまとめています。第2部は実践的な行動計画として、政府全体の具体的な施策約660を、実施主体を明らかにした上で、可能なものには数値目標を入れ、体系的に記述しています。
平成20年5月には与野党の共同提案による生物多様性基本法(平成20年法律第58号)が、国会に提案され全会一致で可決・成立し、6月に施行されました。基本法は、生物多様性の保全と持続可能な利用を推進することで、生物多様性の恵みを将来にわたり享受できる自然と共生する社会を実現することを目的としています。保全や利用に関する基本原則、白書の作成、生物多様性国家戦略の法定化、国が講ずべき13の基本的施策など、わが国の生物多様性施策を進める上での基本的な考え方が示されました。また、国だけでなく地方自治体、事業者、国民や民間団体の責務が盛り込まれたほか、都道府県や市町村が生物多様性地域戦略を策定するよう努めることも規定されています(図5-1-5)。
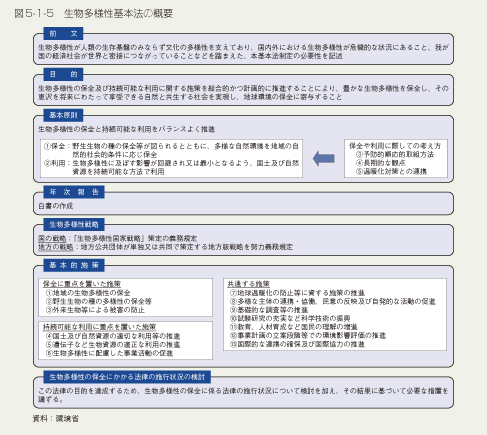
国内でも従来からさまざまな主体が生物多様性に関する取組を進めていますが、近年の国内外の動向を踏まえ一層活発化しています。
(1)地方公共団体
都道府県では、従来から、保護地域や鳥獣の保護管理、希少な野生生物の保護増殖、外来種対策など生物多様性の保全にかかわるさまざまな取組を進めています。希少な野生生物を例にとると、平成17年までにすべての都道府県でレッドデータブックやレッドリストが作成されており、20年までに27都道府県で希少な野生生物の保護のための条例が制定されています。また、森林や水源の保全等を目的とした森林環境税制が、20年までに29県で導入され、これらを財源に森林や水源の保全のための施策が進められています。
以上のような個別の取組を超えて、最近では生物多様性に関する地域計画づくりが進んでいます。平成21年3月末現在、埼玉県、千葉県、愛知県、兵庫県、長崎県などが策定済みのほか、石川県、名古屋市などが策定に向けた準備を進めています。
(2)事業者
従来、企業の生物多様性に対する取組は、社会貢献のほか、義務やリスク回避の視点からの配慮が中心でした。しかし、生物多様性に対する取組を前向きなビジネスチャンスとしてとらえ、企業活動とwin-win(どちらにとっても有利)となるような取組を目指す企業が現れつつあります。日本経団連自然保護協議会では、平成20年2月に生物多様性ワーキング・グループを設置し、生物多様性に関する企業活動の方向性を示すための議論などが進められ、21年3月には、ワーキング・グループの成果を踏まえ、(社)日本経済団体連合会が「日本経団連生物多様性宣言」を発表しました。また、20年4月には、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する学習などを目的とした日本企業による「企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB)」が設立されました。COP9や第4回世界自然保護会議にさまざまな企業や日本経団連自然保護協議会が参加し、ビジネスと生物多様性イニシアティブや各種企画への参加、展示などを行いました。
また、生産段階から加工流通段階にいたる事業者が参画することで、実際に生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用を促進する取組も進んでいます。「森林管理協議会(FSC)」や「海洋管理協議会(MSC)」といった国際的な認証制度のみならず、森林認証制度「『緑の循環』認証会議(SGEC)」(平成15年設立)や水産エコラベル制度「マリン・エコラベル・ジャパン(MELジャパン)」(19年設立)といったわが国独自の認証制度も設立され、認証された林産物や水産物が市場に流通しています。
(3)民間団体(NGO・NPO)
NGOなどの市民団体は、生物多様性上重要な地域での保全活動、市民参加型のモニタリング、子どもたちを対象とした自然環境教育など、従来から生物多様性の保全に向けた幅広い活動を行っています。こうした活動は、行政では十分にできないものを市民のニーズをとらえて地域に密着して行っているものが多く、地域の特性に応じた生物多様性の保全を進めるうえで重要です。
また、多くの団体がCOP9や第4回世界自然保護会議に参加するなど、活発に活動しています。COP10・MOP5日本開催決定を受け、国内では生物多様性保全に取り組むNGO・NPOが主体となり、生物多様性条約の目的に賛同し、その目的の実現に向けて地球市民の立場から活動を行うことを目的とした「生物多様性条約市民ネットワーク」が平成21年1月に愛知県名古屋市で設立されました。
(4)民間団体(学術団体)
日本学術会議では、環境学委員会自然環境保全再生分科会が中心となって、生物多様性国家戦略の改定に向けた提言の取りまとめや、生物多様性に関するシンポジウムやヒアリングを行ってきたほか、COP10に向けた取組について検討を行っています。また、平成21年3月の日本生態学会大会では、保全生態学、外来生物、自然再生、地球温暖化、企業活動、持続可能科学といった生物多様性の保全や持続可能な利用に関する各種のシンポジウムや自由集会が開催され、さまざまな分野の研究者による発表や討論が行われました。
また、COP9の開催前に、ドイツのボンで、科学者によるプレコンファレンスが開催され、地球規模での生物多様性の動向をいかに観測するかといった問題などが討議されました。その流れを受けて、平成20年12月には日本生態学会の呼びかけで、国内の関連学術団体や関連機関によるCOP10プレコンファレンス準備委員会設立のための会合が行われました。
(5)主体間連携
各主体同士が有機的に結びついた取組も進んでいます。COP10が開催される地元では、平成20年9月に、愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、(社)中部経済連合会などからなる「生物多様性条約第10回締約国会議支援実行委員会」が設立され、COP10開催準備のための取組が開始されました。
また、平成21年2月に設置された「生物多様性条約第10回締約国会議及びカルタヘナ議定書第5回締約国会議に関する円卓会議」(以下、「円卓会議」という。)には、多様な主体が参加し、COP10に向けた多様な各主体間の情報の共有、意見交換、連携の促進などが図られています。
COP10の開催される2010年(平成22年)は、「2010年目標」の達成年にあたり、2010年目標の達成状況の評価とその後の目標を含む生物多様性条約戦略計画が議論されます。また、条約の目的の一つであるABSに関する国際的な枠組みについての検討作業を終了させるとされています。COP10に先立ち開催されるカルタヘナ議定書MOP5では、「責任と救済」に関する国際的な取り決めについて議論が行われ、何らかの法的拘束力のある文書の採択に向けた作業が行われることとされています。以上のように、COP10やMOP5は、条約や議定書に関する今後の方向性や国際的なルールづくりに関する重要な議論が行われる節目の会議となり、国連は、COP10の開催される平成22年を国際生物多様性年に定めています。それ以外にも、COP10では、保護地域、持続可能な利用、資金メカニズム、科学的基盤の強化、気候変動と生物多様性、民間参画など、さまざまな議題が予定されています。
わが国は議長国として、国際的にも極めて重要なこれらの会議を円滑に運営するだけでなく、主催国として、日本の取組や経験をさまざまな議題に反映させるとともに、実効性があり、実現可能な決定が行われるよう会議を取りまとめ、成功に導く重要な役割を果たさなければなりません。そのためには、会議に向けて、条約事務局、各締約国などとも情報共有や意見交換をしながら議論を重ねていくことが必要です。
一方、COP10・MOP5はわが国で開催される生物多様性分野で初めての大規模な国際会議となることから、国内での生物多様性に関する認識を深めるとともに、国際的な動向を反映させつつ各種施策を飛躍的に進める契機にもなります。COP10・MOP5とその後を見通して、すでに国際交渉や国内施策も進められていますが、COP10・MOP5までの限られた時間の中、国際貢献も含めしっかりと対応してゆく必要があります。
COP10・MOP5を効果的かつ円滑に開催するには、国内外の体制整備や連携強化を進める必要があります。国内の体制整備として、平成20年9月に、COP10・MOP5の円滑な開催と関係省庁相互の緊密な連携を図るため、関連9省庁の局長級からなる「生物多様性条約第10回締約国会議及びカルタヘナ議定書第5回締約国会議のわが国開催に関する関係省庁連絡会議」を設置しました。また、多様な各主体間の情報の共有、意見交換、連携の促進を目的として、前述の円卓会議を設置しました。これらの会議を活用しながら準備を進めていきます。国際的な連携強化としては、条約事務局との密接な連携のみならず、COP10の議題やそれに向けた会合などを議論する条約のビューロー会議、各議題の作業部会などに参加し、日本の意見を伝えていく必要があります。
また、生物多様性条約では、生物多様性の概念や内包する内容が広範であり、また各国の生物多様性の状況もさまざまであることから、生物多様性条約が締約国に義務付ける具体的な施策は乏しく、締約国全体の共通の取組を提示しにくいのが現状です。COP10に向け、条約の趣旨を体現するための具体的な行動を明確に提示し、各国にその実施を促すため、あらかじめCOP10のテーマを設定し、COP10へ向けた国内外の関連行事や活動をそのテーマに沿って実施していくことで、COP10における成果の最大化を図ります。
以下にCOP10・MOP5で予定される主要テーマに関する日本の取組の方向を示します(図5-1-6)。
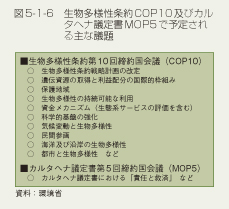
(1)生物多様性条約戦略計画
生物多様性条約戦略計画は、条約の目的を推進するために必要な目標や優先すべき活動などが定められており、2010年目標を戦略計画全体の目標としています。2010年目標を含む戦略計画の見直しには、まず2010年目標の達成状況を評価する必要があることから、条約事務局は、地球規模生物多様性概況第3版(GBO3)を作成しています(平成22年5月公表予定)。生物多様性の評価は定量的に難しい部分もありますが、計測可能で、多くの主体や人々が自らの目標と認識でき、取組の推進につながるような目標を設定することが重要です。そのためには、現行のGBO2で欠けている生態系サービスの経済的評価や、人と自然の関わり方に関する指標を取り入れることが重要と考えられます。わが国は、生物多様性の総合評価やSATOYAMAイニシアティブなどを通じて、わかりやすく計測可能な新目標や二次的自然環境における持続可能な生物多様性の利用を目指した自然資源管理モデルなどの指標を検討しています。それらの取組で得られた成果をさまざまな機会で紹介して合意形成を図り、GBO3やCOP10で提案される戦略計画案に反映させるよう努めていきます。
(2)ABSの国際的な枠組みの検討
COP10までに、遺伝資源の取得と利益配分に関する国際的な枠組みの検討作業を終了することが決議されており、条約事務局が専門家会合や作業部会を開催するなど、国際的な議論が始まっています。わが国は、国際的な利用実態を踏まえ、実質的な利用上の支障が生じないよう、また単に国家間の利害関係だけでなく、生物多様性の保全や持続可能な利用にも配慮された枠組みとなるよう、会合への参加などを通じて、関係省庁が連携して取り組んでいきます。
(3)カルタヘナ議定書の「責任と救済」
カルタヘナ議定書第27条では、遺伝子組換え生物等の国境を越える移動から生じる「損害」についての「責任と救済」に関する国際的な規則の検討について規定されており、平成17年から5回にわたり作業部会が設けられ、検討が進められてきました。20年のMOP4では、当該規定を何らかの法的拘束力のある文書として作成する方向でさらに作業グループで検討し、MOP5に報告することを決議しました。
わが国としては、作業グループなどに積極的に参加し、遺伝子組換え生物等に対してさまざまな考えを持つ各国が実行できるような内容の文書となるよう努めていきます。
(4)保護地域
保護区は、生物多様性条約の目的の1つである生物多様性の保全を進める上で非常に重要です。世界的に見ると、陸域での区域指定が進んでいる一方で、海域の保護区の指定の推進や、指定された保護区の管理の充実が課題となっています。こうした背景を踏まえ、海域の重要な生態系であるサンゴ礁などの保全とネットワーク化を目指すため、神戸・G8環境大臣会合で日本が表明した取組の一つである東アジアを中心としたサンゴ礁保護区ネットワーク戦略の策定を推進します。保護区管理の充実については、日本も資金提供を行い、改訂版が出版されたIUCNの「東アジア保護地域行動計画」の普及や東アジア地域でのワークショップの開催などを通じて、条約の保護地域作業計画の履行を推進していきます。そして、これらの取組をCOP10で発表します。国内では、わが国の生物多様性の屋台骨である国立公園・国定公園の総点検と全国的な見直し・再配置、自然公園法などの見直しや海洋基本計画に盛り込まれた海洋保護区のあり方の検討、わが国の国立公園の管理経験を生かした国際協力の推進などの施策を進めていきます。
(5)持続可能な利用
条約の目的の一つである生物多様性の持続可能な利用を進めるには、一次産業を中心とした持続可能な自然資源管理を進める必要があります。COP10で持続可能な利用の一つの方向性を示すため、持続可能な自然資源管理を全世界的に展開していくためのモデルを日本の里山の名を冠した「SATOYAMAイニシアティブ」としてCOP10で提案・発信します。COP10に向け、世界の持続可能で資源循環的な自然資源の伝統的利用の事例や専門的な知見を収集するとともに、国際ワークショップなどにおいて合意形成を図りつつ、現代社会の実情と各国の自然資源の質に即した自然資源管理モデルを検討していきます。国内の里地里山は、社会経済の変化によりその自然環境が劣化しつつあることから、自然資源の管理・利活用方策や多様な主体の参画を促進するための検討を行うことによって保全再生に取り組んでいきます。
(6)資金メカニズム
条約の目的を履行するためには、さまざまな方法により資金供与や技術移転を行う仕組み(資金メカニズム)が必要とされています。COP9で生物多様性の地球規模での損失による経済的な影響を取りまとめた「生態系と生物多様性の経済学(TEEB)」の中間報告書が公表されました。また、条約の作業部会では、革新的な資金メカニズム(生態系サービスへの支払い、環境保険、緑基金など)の検討を行うことが決定されました。COP10では、生態系サービスの評価を含む資金メカニズムが議題として予定されていることから、これらの動きに貢献できるよう、国内における生態系サービスの経済評価の試算や、生態系サービスの経済評価を踏まえた施策の検討を行っていきます。
(7)科学的基盤の強化
未解明な部分の多い生物多様性分野で施策を効果的に推進していくためには、科学的基盤の強化が必要不可欠です。特に、近年顕在化しつつある気候変動による影響を視野に入れ、生物多様性の状態とその推移を的確に把握し、科学的な対応に努める必要があります。科学的基盤の強化を効率的に進めるには、「全球地球観測システム(GEOSS)」や「長期生態系研究ネットワーク(ILTER)」などの既存の活動間の協力や情報共有が重要です。そのための取組を、神戸・G8環境大臣会合で日本が表明した「地球規模生物多様性モニタリング・ネットワーキング・イニシアティブ」として実現するため、国際ワークショップや専門家会合を行っていきます。また、科学的基盤の強化には、基礎的な関連情報の整備や調査を行う人材育成が不可欠です。そのため、「世界分類学イニシアティブ(GTI)」の枠組みの下、「地球規模生物多様性情報機構(GBIF)」の活動とも連携しながら、アジア地域の分類学に関する情報や標本の整備及び分類同定能力を有する人材を育成するイニシアティブ(アジア地域生物多様性インベントリー・イニシアティブ)をCOP10で立ち上げることを目指します。さらに、生物多様性に関する科学及び政策の連携の強化を目的とする「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)」の創設に向けた国際的な議論にも積極的に参画していきます。
(8)気候変動と生物多様性
気候変動枠組条約における各種検討作業への生物多様性条約の視点を取り入れるため、COP10までに2回の専門家会合を開催し、気候変動に対する緩和方策と適応方策について検討することがCOP9で決定されました。わが国から専門家会合などに出席するほか、科学的基盤の強化を通じて気候変動が生物多様性に及ぼす影響についての科学的知見の蓄積に努めます。
(9)民間参画
COP8の民間参画決議を受け、COP9に合わせてドイツ政府が主導して立ち上げられた「ビジネスと生物多様性イニシアティブ」について、COP10での発表を視野に、ドイツ政府と連携して成果の取りまとめを進めます。国内では、事業者が生物多様性に配慮した活動を自主的に行うためのガイドラインの策定や、国民一人ひとりの行動を促す生物多様性に配慮した行動リストの提案を通じて、生物多様性に配慮した事業活動の促進支援や国民参画の推進などの取組を行います。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |