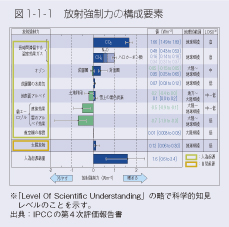
私たちの日々の暮らしやその支えとなる経済活動は、地球環境という基盤の上に始めて成り立っています。清らかな水や大気、多様な生態系や自然環境、安定した気候など、健全で恵み豊かな環境を維持しなければ、私たちは健康を保ち、文化的な生活を営むことはできません。そのような、私たち人類の生存の基盤である環境は、現在、どのような状況にあるのでしょうか。本章では、様々な環境問題の分野ごとに、具体的なデータを交えながら、地球とわが国における環境の状況を紹介します。
地球の気候は、様々な要因の影響を受けて変化します。二酸化炭素等の温室効果ガスの濃度、大気中に浮遊する微粒子等(総エーロゾル)や太陽放射等は、地球の内外に出入りするエネルギーのバランスを変化させます。このエネルギーバランスは、1平方メートル当たりのワット数の値で表され、これが正の値の場合には地表面を暖め、負の値の場合には地表面を冷やすはたらきをします。二酸化炭素等、このエネルギーバランスを変化させ気候に影響を与える各要因については、その影響力に応じて、放射強制力という数値で表されます(図1-1-1)。また、エルニーニョのような自然の内部変動によっても、地球の気候は左右されます。これらの要因を考慮しながらも、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第4次評価報告書は、「20世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは、人為起源の温室効果ガス濃度の観測された増加によってもたらされた可能性が非常に高い」と述べています。
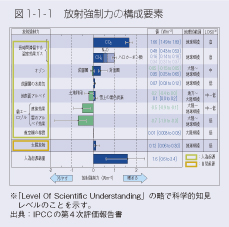
現在進行している地球温暖化の状況については、世界の年平均地上気温の平年差から見ることができます(図1-1-2)。IPCCの第4次評価報告書によれば、長期的には100年当たり0.74℃の割合で上昇しており、特に1990年代半ば以降、高温となる年が多くなっています。世界の年平均気温について、統計を開始した1891年以降の各年の気温を順位付けてみますと、21世紀になってからのすべての年は、最も気温の高かった10位までに位置付けられています(表1-1-1)。なお、2008年の年平均気温は、1990年代の多くの年に比べれば高いものの、ここ数年に比べて低くなっています。気象庁によれば、その要因の一つとして、2007年春から2008年春に発生したラニーニャ現象の影響が考えられるとしています。
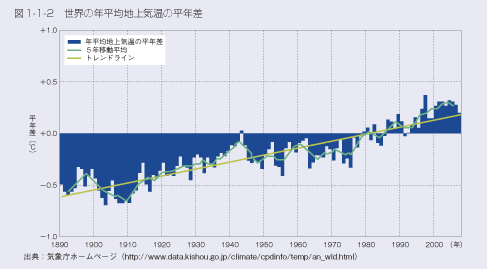

温室効果ガスの大部分を占める二酸化炭素の大気中の濃度及びその人為的排出量は、増加傾向にあります(図1-1-3)。
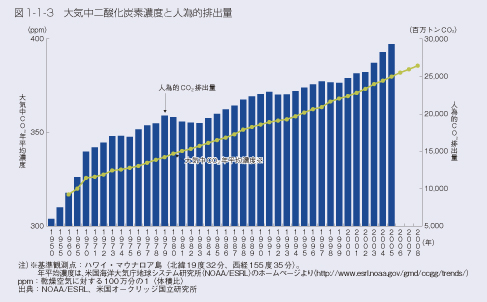
同報告書では、1993年から2003年にかけて、グリーンランドと南極の氷床の減少が海面水位の上昇に寄与した可能性が非常に高い、と指摘しています。また、グリーンランド氷床の地球温暖化に対する反応は、従来考えられていたよりも早く進むおそれが指摘されています(図1-1-4)。
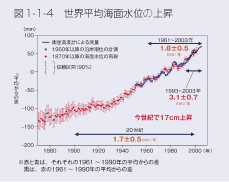
世界各地で、ハリケーンやサイクロン、集中豪雨や干ばつ、熱波等の異常気象による災害が頻繁に発生しており、また、世界中の様々な地域で、気候の変動が原因とされる生態系の異変が報告されています。これらの現象のすべてについて地球温暖化の関与を断定することはできませんが、地球温暖化が進行すれば、これらの悪影響がさらに強まることが、様々な研究によって指摘されています。
地球環境問題としては、地球温暖化に加え、オゾン層の破壊、酸性雨・黄砂、海洋汚染、森林減少、砂漠化、南極の環境問題等が挙げられます。そのうち、オゾン層の破壊の状況は、南極上空のオゾンホール面積の推移からみることができます。現在、オゾンホールに縮小の兆しは見られません(図1-2-1)。ただし、これまでの規制の成果により成層圏におけるオゾン層破壊物質の総濃度は減少傾向にあります。
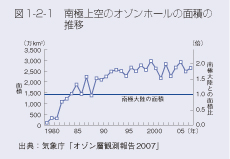
オゾン層の破壊に伴って心配されるのは有害紫外線の増加です。この点については、幸い、顕著な増加は報告されていません(図1-2-2)。
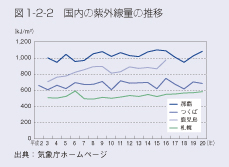
また、黄砂については、北東アジア地域で頻度と被害が大きくなる傾向にあり、関心が高まっています。近年、わが国でも観測される日数が多くなっていることがうかがえます(図1-2-3)。
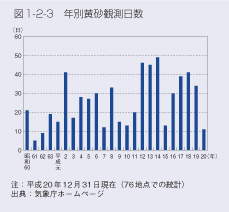
国内の状況について見ますと、大気汚染の状況については、平成19年度末現在、1,561局の一般環境大気測定局(以下「一般局」という。)及び445局の自動車排出ガス測定局(以下「自排局」という。)の全国2,006局において常時監視が行われています。
平成19年度の大気汚染状況について見ますと、大気汚染に係る環境基準が定められている物質のうち、光化学オキシダントの環境基準達成率は、一般局で0.1%、自排局で3.3%と極めて低い水準に留まっており(図1-2-4)、なお一層の対策が求められています。
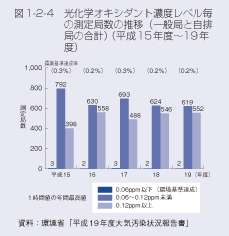
なお、環境基準より高い濃度に対応して発令される光化学オキシダント注意報等については、その全国の延べ発令日数は平成20年度に144日で、平成19年度(220日)よりは減少しました(図1-2-5)。
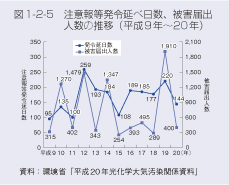
二酸化窒素は、一般局では近年ほとんどすべての測定局で環境基準を達成しており、達成率は平成18年度に続き100%となりました。また、自排局では94.4%となっています(図1-2-6)。
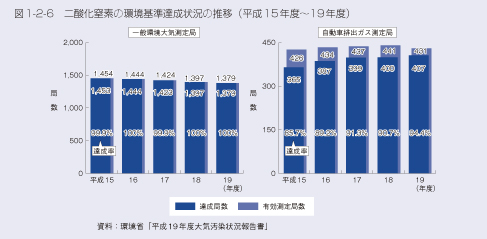
浮遊粒子状物質の環境基準達成率は、一般局で89.5%、自排局で88.6%となり、平成18年度と比べやや低下しました(図1-2-7)。
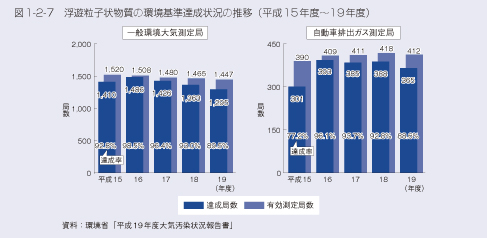
水環境では、水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)は、ほぼ問題のない状況になっていますが、生活環境の保全に関する項目(生活環境項目)では、湖沼の化学的酸素要求量(COD)の環境基準達成率が50.3%となり、有機物が多すぎる状況にあるなど、依然として達成率が低い水域が存在します(図1-2-8)。また、地下水質については、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環境基準超過率の高い状況が続いています(図1-2-9)。
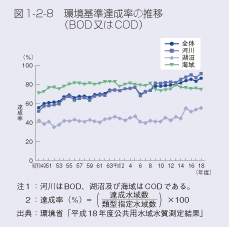
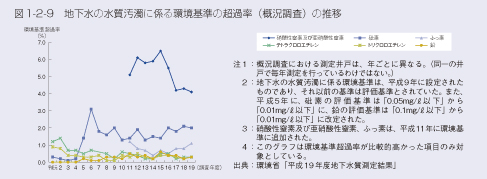
土壌環境については、近年、土壌汚染事例の判明件数が増加しており、土壌の汚染に係る環境基準又は土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の指定基準を超える汚染の判明事例を年度別に調べた結果では、平成19年度には732件となっています(図1-2-10)。
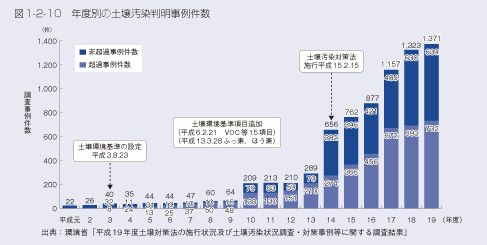
従来の大量生産・大量消費型の経済社会活動は、大量廃棄型の社会を形成し、環境保全と健全な物質循環の阻害に結び付く側面を有しています。
廃棄物に関する状況として、重要な指標である最終処分場の残余年数については、新規の最終処分場の確保が難しくなっていることに伴い、一般廃棄物が15.6年(平成18年度末時点)、産業廃棄物で7.5年(平成18年度末時点)と依然として厳しい状況が続いています(図1-3-1、1-3-2)。
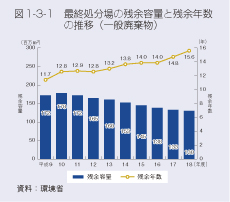
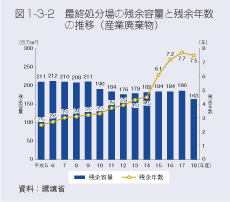
また、近年、国内の沿岸地域で問題となっている漂流・漂着ゴミの実態について、全国7県11海岸をモデル地域として調査したところ、モデル海岸で回収されたペットボトルは、対馬(長崎県)、石垣島、西表島(以上、沖縄県)などの離島では外国のものがほとんどを占め、それ以外の地域ではわが国のものが半数以上を占めるという状況でした(図1-3-3)。ゴミの種類としては、日本海側はプラスチック類が3~4割、山形県、三重県、熊本県は流木・潅木が7~9割、沖縄県は、多くの種類のゴミが混ざるなど、地域によって漂着物の種類に違いがありました。また、1年を通して行った漂流・漂着ゴミの回収・処理調査から年間の漂着量を推定したところ図1-3-4のとおりでした。
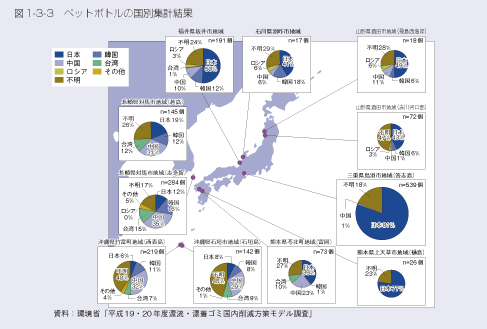
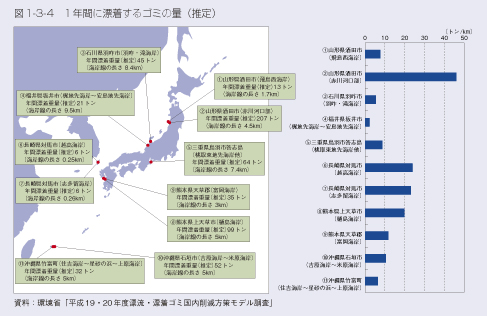
私たちの身の回りには、様々な化学物質や化学物質を利用した製品があり、私たちの暮らしを便利なものにしています。しかし、中には人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすものもあり、そのような悪影響を及ぼすおそれ(環境リスク)を評価し、その程度に応じた管理を行うことが必要です。
平成19年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査によると、環境基準が設定されている4物質についての大気中の年平均値、環境基準超過地点等については、表1-4-1のとおりです。ベンゼンは3地点(前年度:13地点)で環境基準を超過しましたが、その他の3物質は、全ての地点で環境基準を満たしていました。
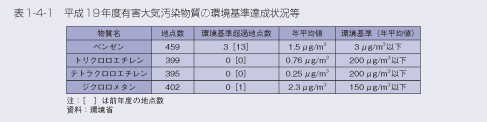
このような化学物質の環境中における状況の背景となる排出量について見ます。特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「PRTR法」という。)の対象物質のうち、環境基準又は指針値が設定されている物質等の大気への排出量の合計は、平成18年度において約29,200トンとなっており(図1-4-1)、全体として減少傾向にあります。同年の公共用水域への排出量は約7,900トンであり、全体としてはほぼ横ばいの状況です(図1-4-2)。
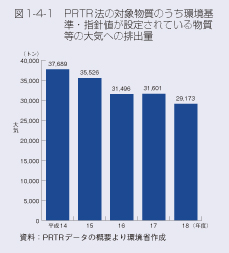
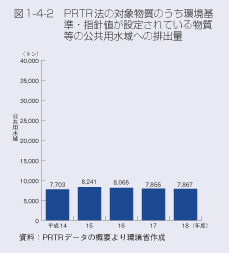
環境リスクが特に高い物質は、製造、輸入、使用が禁止されています。これらのうち、例えばPCB類について見ると、その環境中の濃度は、水質で9pg/L等となっています(表1-4-2)。
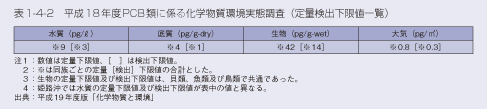
ダイオキシン類対策では、ダイオキシン類の排出量について、平成17年にダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第33条第1項の規定に基づき「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」を変更し、平成22年までに平成15年に比べて約15%削減することとしました。平成19年度の環境調査では、公共用水域を中心に、一部で環境基準の超過が見られます(表1-4-3)。平成18年に人が一日に食事及び環境中から平均的に摂取するダイオキシン類の量は、体重1kg当たり約1.06pg-TEQと推定され、年々わずかながら減少しており、耐容一日摂取量を下回っています(図1-4-3、図1-4-4)。
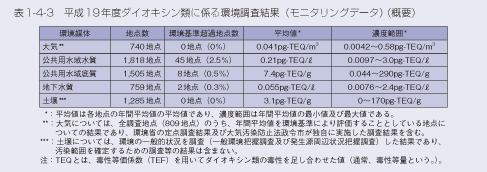
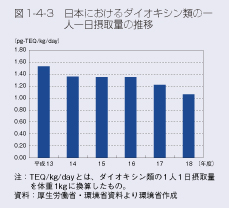
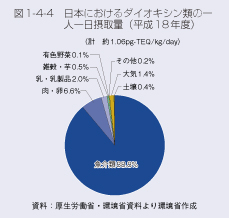
(1)世界の生物多様性の状況
地球上には、様々な生態系が存在し、これらの生態系に支えられた多様な生物が存在しています。全世界の既知の総種数は約175万種ですが、まだ知られていない生物も含めた地球上の総種数はおよそ500万~3,000万種といわれています。
国際自然保護連合(IUCN)の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト(レッドリスト)によると、評価対象種の約4割に絶滅のおそれがあるとされています。
世界の生物多様性の状況を総合的に評価する試みとして、国連の呼びかけにより平成13年から平成17年にかけて実施されたミレニアム生態系評価(MA)では、24の代表的な生態系サービス(生態系から人々が得る恵み)について地球規模での状態や変化の傾向を評価した結果、向上していると評価されたのはわずか4項目(穀物、家畜、水産養殖、気候調節)でした。他方、15項目(漁獲、木質燃料、遺伝資源、淡水、防災制御など)では低下しているか、持続できない形で利用されていることが示されました。
また、平成18年の生物の多様性に関する条約(以下、「生物多様性条約」という。)第8回締約国会議(COP8)で、生物多様性条約事務局が公表した地球規模生物多様性概況第2版(GBO2)では、15の指標により地球規模の生物多様性の状況を評価した結果、保護地域の指定範囲などを除く12の指標が悪化傾向となるなど、生物多様性が依然として失われつつあることが示されました(表1-5-1)。
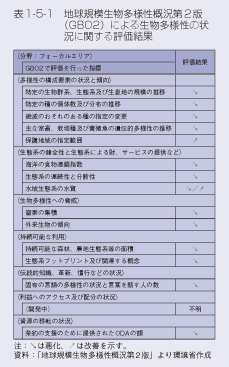
平成20年のCOP9の閣僚級会合において中間報告が行われた生態系と生物多様性の経済学(TEEB)では、早ければ2030年までにサンゴ礁の60%が漁業、汚染、気候変動などにより消滅するとされました。また、2000年から2050年までの50年間に、自然地域の11%が農地への転換や気候変動等により失われるといった深刻な結果を招くおそれがあるとされました。さらに、森林生態系の劣化による経済的な損失は2050年には1兆3,500億ユーロ(約220兆円)~3兆1,000億ユーロ(約500兆円)に及ぶ可能性が指摘されました(図1-5-1)。
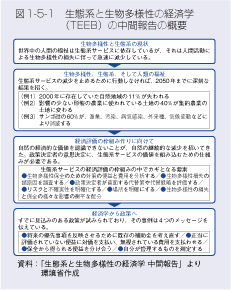
(2)日本の生物多様性の状況
わが国は四方を海に囲まれ、6,800余りといわれる多くの島々から構成されています。国土面積は約3,800万ヘクタールと比較的狭いにもかかわらず、海岸線の全長は約35,000kmもあり、海岸から深山幽谷にいたるまで複雑で起伏に富んだ地形が見られます。全国的に降水量に恵まれ、多くの地域に四季が存在し、南北約3,000km、標高差約3,800mの中に、亜寒帯から亜熱帯にいたる気候帯が存在します。この多様な自然環境の中に約9万種以上の生物種が確認されています。その中にはわが国だけにしか確認されていない固有種も多く、陸上の哺乳類の約4割、両生類の約8割がそれに当たります。
環境省レッドリストによると、日本の絶滅のおそれのある野生生物は3,155種で、日本に生息・生育する爬虫類、両生類、汽水・淡水魚類、貝類の3割強、哺乳類、維管束植物の2割強、鳥類の1割強に当たる種が、絶滅のおそれのある種に分類されています(図1-5-2)。
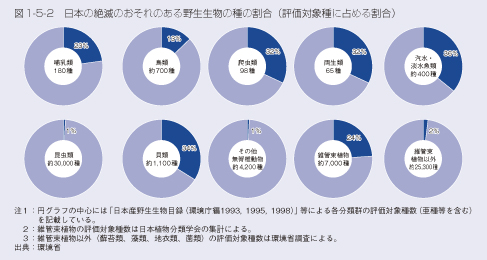
この中には、南西諸島や小笠原諸島などの島嶼域に生息・生育する固有種だけでなく、メダカに代表されるように、里地里山に生息・生育する身近な種や水辺の種も多く含まれています。他方で、コウノトリやトキのように、自然界では一度絶滅した種を、人工飼育下で繁殖させ、野生に戻す取組も行われています。下北半島や西中国地域のツキノワグマなどのように生息地の分断などにより地域的に絶滅のおそれがある種もいる一方で、ニホンザル、ニホンジカやイノシシ等のように地域的に増加又は分布域を拡大して、農林漁業被害など人とのあつれきや生態系のかく乱を起こしている種もいます。
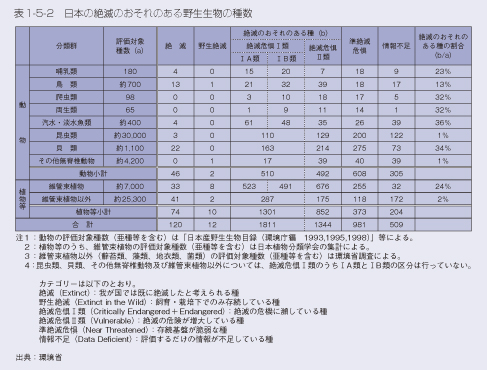
| 目次 | 次ページ |