��2�߁@�l���̒n��݂Ɗ�
�P�@���n���R�n��
�l�ԂƎ��R�̂�����肠�������o���Ă������n���R�́A���R���R�n��Ɠs�s�n��̒��ԂɈʒu���A���{�̍��y�̖�S�����߂Ă��܂��B���̒n��ł́A���R�̒��j���Ȃ��тƂƂ��ɁA�l�H�сA���c���̔_�n�A���ߒr�A���n�������U�C�N��ɑg�ݍ��킳��A�l�ׂɂ��K�x�ȝ����ɂ���ė��n���R���L�̊����`���ێ�����A��Ŋ뜜����܂ޑ��l�Ȑ�������ޒn��ƂȂ��Ă��܂��i�}1-2-1�j�B�܂��A���n���R�́u��ꎟ�Y�Ƃ̏�v�ł���Ɠ����ɁA�s�s�ߍx�ɂ����Ă͓s�s�Z���̐g�߂Ȏ��R�Ƃ̂ӂꂠ���̏�A���w�K�̃t�B�[���h�Ƃ��Ă̏d�v�������܂��Ă��Ă��܂��i�}1-2-2�j�B
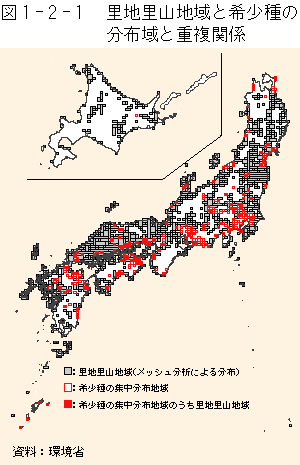
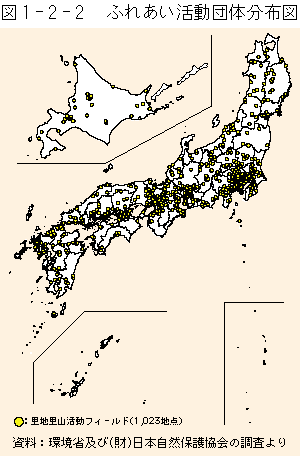
�i�P�j���n���R�n��̌���
�A�@�ߑa���̐i�W
�n�����Ɉʒu���闢�n���R�n�擙�ł͉ߑa�����}���ɐi�W���Ă��܂��B�ߑa���̗v���Ƃ��ẮA�ߔN�A�l�̈ړ��ɂ��l���̎Љ���k�����Ă�������A�o�����̒ቺ�A���S���̑����ɂ��l���̎��R�����g��X���ɂ���A�Љ�Ɠ������ɂ܂ŒB���Ă��܂��i�}1-2-3�j�B�ߑa�����i�ޒn��ł́A�W�����ł̉\�����w�E����Ă���A�u�ߑa��̌����v�i����17�N�V�������ȁj�ɂ��ƁA�ߑa�n��ɂ����49,000�̏W���̂����A��10�����W���@�\���ێ����邱�Ƃ�����ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A����11�N�ɍ��y�������{�����ߑa�n��̎s�����i����1,230�s�����j�ւ̃A���P�[�g�����ɂ��ƁA�S�W���i����48,689�W���j�̂����A2,109�W���ɏ��ł̉\��������܂��B
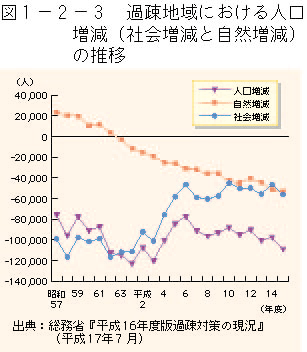
�C�@�_�ыƊ����̒��
���n���R�ł́A�_�R���ɒ�Z���Ă����l�X���_�Ƌy�їыƂ�ʂ��āA���R�ƑΗ�����`�ł͂Ȃ���������`�Ŏ��R�ɓ��������A���܂����p���邱�Ƃɂ���āA���l�Ȑ�������ނ��Ƃ̂ł�������`������A���R�Ɛl�Ԃ̋����W���ێ�����Ă��܂����B
�_�Ƃ́A�l�Ԃ̐����̈ێ��Ɍ������Ƃ��ł��Ȃ��H��������I�ɋ�������ƂƂ��ɁA�_�Ɛ��Y������ʂ��č��y�̕ۑS�A�����̂���{�A���R���̕ۑS�A�ǍD�Ȍi�ς̌`���A�����̓`�����̑��ʓI�ȋ@�\������Ƃ���������L���Ă��܂��B�������Ȃ���A�ߔN�A�S���I�ɔ_�ƏA�ƎҐ�����������ƂƂ��ɁA�o���ɂ��|���Ă����m����Z�p��L����_�Ǝ҂̍�����i�W���Ă��܂��i�}1-2-4��i�j�B����ɔ����A�_�Ɛ��Y�����̒�E��ނ�W���@�\�̒ቺ��������ƂƂ��ɁA�k������n���g�債�Ă���A���ɁA���R�Ԓn��Ȃǂ̌X�̌������n��قǂ��̌X�������������܂��i�}1-2-5�j�B
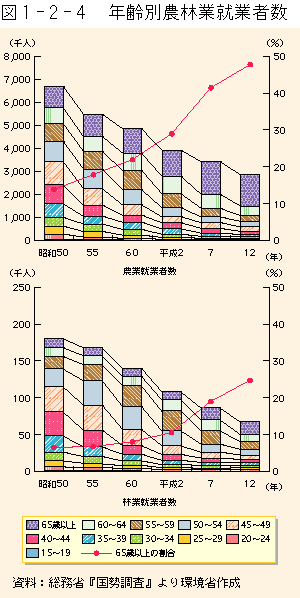
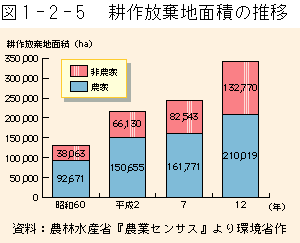
�܂��A�ыƂ́A�X�т̐�����ʂ��A�؍ނY����ƂƂ��ɁA�n�����g���̌����ƂȂ��_���Y�f�̋z���E������C���E���x�̒�����ʂ����C��̈��艻�A���y�̕ۑS�A�����̂���{�A�������l���̕ۑS�ȂǁA�l�Ԃ̐����ɂƂ��Č������Ƃ̂ł��Ȃ����̊�Ղ����ł��܂��B�������Ȃ���A���Y�މ��i�̒�����ɂ��ыƍ̎Z���̈����A���̃G�l���M�[�v���ɂ��d�Y�ނ̎��v�̒ቺ�Ȃǂɂ��A�X�я��L�҂̎{�ƈӗ~���ቺ���āA�ыƐ��Y����������Ă��܂��B���̌��ʁA�ыƏA�Ǝ҂ɂ��ẮA������i�ނƂƂ��ɁA���̐����傫���������Ă��܂��i�}1-2-4���i�j�B�܂��A�X�тł́A�X�V�A�ۈ�A�Ԕ����̓K���Ȏ���ꂪ�\���ɍs���Ă��Ȃ��X�т��ꕔ�Ō�����悤�ɂȂ��Ă���A���v�I�@�\�̔����ւ̎x���A�R���n��̌o�ς�Љ����邨���ꂪ�����Ă��܂��i�}1-2-6�j�B
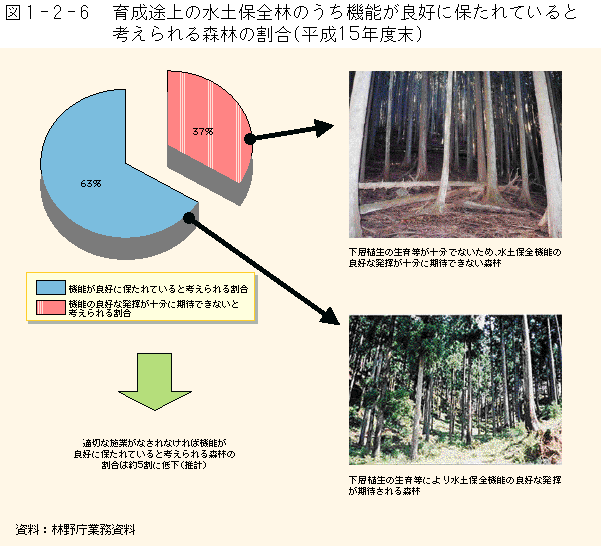
�i�Q�j���n���R�n��ɂ����鎩�R�Ɛl�Ƃ̊W�̕ω��Ɛ������l���̊�@
�ߑa���̐i�W�A�_�ыƂ̍̎Z���̒ቺ�ɂ��_�ыƊ����̒����E���Y�l���̕ω����ɂ��сE���n�̗��p�ቺ���ɂ��A�K�x�Ȑl�ׂ̓��������ɂ���Č`���E�ێ�����Ă����I�Ȏ��R���̎����ω����A�����������ɓ��L�̑��l�Ȑ�������������ȂǁA���n���R�n��̐������l�����܂ގ��R���ւ̉e�������O����Ă��܂��B
�A�@���c
���c�́A���Ǘ������Ȃnjp���I�Ȑ����̉c�݂Ȃǂ̐l�ׂ̓����ɂ���āA���ʂ������n���`���E�ێ�����A���_�J��h�W���E���̒W������A���l�ȍ����⏬�����̐����̏�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�����H����͐쓙�ւƂȂ���_���̐����̒��S�Ƃ��āA�������A���ɂƂ��ĂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ�������Ă��܂����B�������A�k������ɂ�萅�c���g���Ȃ��Ȃ�ƁA���c���������A�G�����ɖ��錋�ʁA���c�����݂��Ƃ��邱��琅�ӂ̐����̐���������ɂȂ�܂��B�܂��A�R�ԕ��̍k������n�ɃX�X�L�A���V���̑��N���A�������ɖ���ƁA�C�m�V�V���̉B��ƂƂ��čD�K�Ȋ��ƂȂ�A���b�Q�������ꍇ������܂��B�܂��A�n�����̂���{�@�\���ቺ���邱�Ƃɂ��A�����ł̗N���ʂ��ω����A�������̏�Ƃ��鐶���ւ̉e�����l�����܂��B

�C�@���ߒr
���p����Ȃ����ߒr�͖������ɂ�茸�����Ă���A���̎��R������������܂��B
���쌧���\����i�ςƂ��Ȃ��Ă��邽�ߒr�Q�́A�{���̖ړI�ł���_�Ɨp���̊m�ۂ����łȂ��A���ȃ��b�h�f�[�^�u�b�N�Ő�Ŋ뜜�TA�ނɕ��ނ����j�b�|���o���^�i�S�̐����n�Ƃ��Ă��̏d�v�����F�߂��A�u���{�̏d�v���n500�v�i2001�N���ȁj�ɂ��I�肳��Ă��܂��B���쌧�̎��Ԓ����ɂ��ƁA���a61�N��16,304�������������ߒr���A����12�N�ɂ�14,619�����Ɍ������Ă���A�����������ߒr�̂قƂ�ǂ͎R�ԕ��ɂ���A�_�Ɨp���Ƃ��ė��p����Ȃ��Ȃ������Ƃ������̈�ƂȂ��Ă��܂��B
�E�@��
�R�i���A�N�k�M�A�A�J�}�c�ѓ��́A�d��Y�̗D�ꂽ�ޗ��Ƃ��āA���t�͔엿�Ƃ��ė��p����Ă��܂����B���̂��߁A���Ă�10�`30�N���Ƃɔ��̂���Ă���A���͏������A���z�����閾�邢�я����L�����Ă��܂����B���̂悤�ȓтł́A���邢�я����D�ރJ�^�N���A���̉Ԃɋz������M�t�`���E�̂悤�ȍ����������܂��B�������A�d�Y��엿�Ƃ��ė��p����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ�A�ߑa�����̉e�����A���u���ꂽ�т�����������悤�ɂȂ��Ă��܂��B���u���ꂽ�тł́A���傫���Ȃ�A�\���S�Ȃǂ̏�L�t����T�T�ނ��������A�я��ɑ��z�����͂��ɂ����Ȃ�ȂǁA���A���̐����E������̕ω��ɂ��A�����������ɓ��L�̑��l�Ȑ����̏��������O����܂��B

�G�@�l�H��
�l�H�т͐A�͌�̉�����E�������̕ۈ��A�K�v�Ȏ����ɊԔ����̓K���Ȑ������s�Ȃ����Ƃɂ���āA�R�n�ЊQ��n�����g���̖h�~�A��������{�Ȃǂ̌��v�I�@�\�����܂��B
�ߔN�A�ыƂ̒���ɂ��A�K���Ȑ������s���Ȃ��l�H�т��ꕔ�Ō�����悤�ɂȂ�A�X�т��{�������v�I�ȋ@�\�֎x��������������ꂪ����A�ѓ��ɂ��鑐�{���ؗނ����ƕs���ɂ��\������ł����A�܂��A�n�\�ʂ̓y�낪�I�o���č~�J�ɂ���ė���₷���Ȃ�ȂǁA�X�ѓ��₻�̎��ӂɐ����E���炷�铮�A���ւ̉e���������O����܂��B
�I�@�l�ƒ��b�̂��ꂫ�̑���
�l�ɂ��K�x�Ȏ��R�ւ̊֗^�������邱�Ƃɂ��e���́A�T���A�C�m�V�V�A�V�J���̖쐶���b�ɂ�����Ă��܂��B���R�̎��R�n��Ɨ��n���R�n��Ƃ̋��E��≜�R�̎��R�n��ɐ������Ă��������̒��E��^�M���ނ��A���̐������z����g�債�Ă���X���������܂��B�}1-2-7�́A���{�S�����T�L�����[�g���l���̃��b�V���ɋ�敪�����A��悲�ƂɃC�m�V�V��1978�N�i���a53�N�j�y��2003�N�i����15�N�j�̐��������������̂ł��B�����̐}������ƁA�C�m�V�V�́A�_�k�n�A�сE�A�ђn�ɕ��z����g�債�Ă��邱�Ƃ�������܂��B����́A���̂悤�Ȓn��ɂ����āA�k������n���g�債�đ����ؓ����ɖ��A�������C�m�V�V�ɂƂ��Đl����̉B���ƂȂ�悤�Ȉ��S�n�тƂȂ��Ă��邱�Ƃ◢�R���ɂ����Đl�Ԃ̊������ቺ�������Ƃɂ��A�X�т���k������n�ւƃC�m�V�V�̈ړ��ɓK�����ƂȂ��Ă��邱�ƂȂǂ��A�����̈�Ƃ��čl�����܂��B
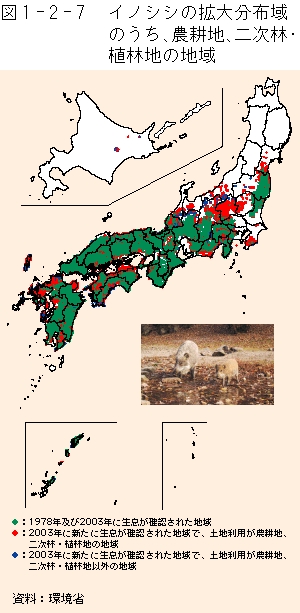
�C�m�V�V���̐������z��̊g��͂��̂ق��ɂ����g���ɂ��ϐ�ʂ̌������͂��߂Ƃ����C��I�v���Ȃǂ��d�Ȃ������߂ƍl�����Ă��܂��B
�l�ɂ��K�x�Ȏ��R�ւ̊֗^�������邱�Ƃ́A�T���A�C�m�V�V�A�V�J���̐������z��̊g��̂ق��A�쐶���b�ɂ��_�ыƂւ̔�Q�ɂ��Ȃ����Ă��܂��B�u���b�Q��Ɋւ���s���y�є_�ƒc�̓��ɑ���A���P�[�g�������ʁi����Łj�v�i����17�N�_�ѐ��Y�ȁj�ɂ��ƁA�C�m�V�V�ɂ��ẮA��Q�����������Ɖ����_�ƒc�̓����S�̖̂����߂Ă��܂��B���b��Q�̊g��͉c�_�ӗ~�̒ቺ���������A���ꂪ�k������n�̊g��ɂ��Ȃ���A���ʂƂ��Ă���Ȃ钹�b��Q�ނƂ������z�������炵�Ă���ƍl�����܂��B
���̂ق��A�W���ɕp�ɂɃT����C�m�V�V������A�l�ƒ��b�̂��ꂫ����������X���������܂��i�\1-2-1�j�B
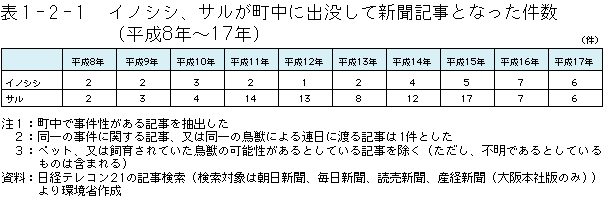
���̂悤�ȁA�l�Ɩ쐶���b�Ƃ̂��ꂫ���y�����邽�߂ɂ́A�쐶���b�̓K�ȕی�Ǘ����s���ƂƂ��ɁA�h���̐ݒu����Q�h�~��𑍍��I�Ɏ��{���邱�Ƃ��d�v�ł��B
�������Ȃ���A���b�̕ی�Ǘ��ɏd�v�Ȗ�����S���Ă����ҁi��Ƌ��ێ��ҁj�́A���a45�N�ȍ~�A�����A������i�s���Ă���A��҂̊m�ۂ��Ɋւ���m���̎�����ւ̌p�����ۑ�ƂȂ��Ă���܂��i�}1-2-8�j�B
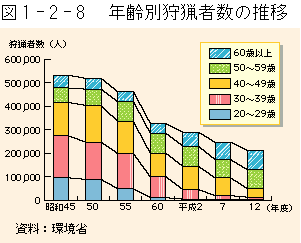
�i�R�j���ꂩ��̗��n���R�n��̂����
����A�l������������}���A�ߑa���̐i�W��_�ыƊ����̒ቺ�����O����闢�n���R�n��ł́A���R�Ɛl�Ƃ̃o�����X�W�̕���A�l�ׂ̓��������̌����ɂ�鐶�Ԍn�ւ̉e���ȂǁA�������l���ۑS��̊�@�����܂邱�Ƃ�Ɠ��Ȍi�ς������邱�Ƃ����O����Ă��܂��B
���n���R�n��ɍL����L���ȓI���R�����A�����I�ȗ��p��}��Ȃ��玟����Ɋm���Ɉ����p���ł������߂ɂ́A�K���I�ȑ[�u�����ނ���ϋɓI�Ɋ��p���邱�Ƃ�ʂ��A�l�Ǝ��R�̂�����肠���̒��ō��o����Ă����n��ł��邱�Ƃ��ĔF�����A�l�̐����E���Y�����ƒn��̐������l������̓I�������I�ɂƂ炦�A�ۑS�E�����ɕK�v�Ȋ����̊m�ۂƂƂ��ɂ������~���ɒ�������悤�ȃV�X�e�������ꂼ��̒n��ɂ����ē������邱�Ƃ��K�v�ł��B
���̂��߁A�_�k�n�Ȃǂɂ����ẮA�e�n��̎Љ�o�ϓI�ȏ⎩�R���̓������l�����āA�_�Ƃ��܂ޒn��Z���̎Q������Ȃ���A�_�n�␅�H�A���ߒr�̕ۑS��Ԍn�ɔz���������H�₽�ߒr�̐����A���ۑS�^�_�Ƃ̐��i�A���ʓI�@�\�̊m�ۂ�ړI�Ƃ����x���[�u�ȂǁA���l�Ȑ���������E�����ł�����Ɣ_�Ɛ��Y�����̒��a�ɓw�߂Ă������Ƃ��d�v�ł��B
�܂��A�X�тɂ����ẮA�X�т̎����v�I�@�\�̔����̊ϓ_����A�X�V�A�ۈ�A�Ԕ����̐X�т̓K���Ȑ����y�ѕۑS�𐄐i���邽�߁A���I��̂ɂ����{�ƂƂ��ɁA�R���n��ł̒�Z�̑��i�̂ق��A�s�s�Z���Ȃǂ�����S������W����ȂǁA�X�я��L�҂ƘA�g�E���͂��ĕۑS�E���p�ł���̐��Â��蓙���d�v�ł��B
�����̎�g�ƂƂ��ɁA��K���̌������Ⓓ�b�̕ی�Ǘ��{��̋����ɂ��A���ߍׂ������b�̕ی�Ǘ��̎�����}�邱�Ƃɂ���āA�l�Ɩ쐶���b�Ƃ̂��ǂ��W���\�z���邱�Ƃ��d�v�ł��B
����ɁA�S�ʓI��g�Ƃ��āA�s���E���ƁENPO���̘A�g�ɂ��Ǘ���@��̐��Â���A�y�n���L�҂Ƃ̋���̒����A�����I�i�ς̕ی�ȂǁA��X�̎d�g�݂L�����p���A�����I�ɕۑS���Ă������Ƃ����҂���܂��B
�Q�@�s�s�Ɗ�
�킪���ł́A����т��Ĕ���I�Ȑl���̑����ƌo�ϐ����̒��A�}���ȓs�s�����i�W���܂����B�s�s�����ɂ�����r����Z��C���X����������ł���s�s�I�n���\���u�l���W���n��v�i�l�����x���P�����L�����[�g��������4,000�l�ȏ�̊�{�P�ʋ悪�s�撬���̋�����Ō݂��ɗאڂ��Ă���A���A�����̗אڂ����n��̐l����5,000�l�ȏ��L����n��B�ȉ��uDID�v�iDensely Inhabited District�j�Ƃ����j�̑S���I�ȓ���������ƁADID�l���̑S�l���ɑ���䗦�͑����𑱂��A����12�N�ɂ�65.2���ƂȂ�܂����B�����ŁA���̂悤�ȓs�s���ւ̐l���������̃y�[�X������y�[�X��DID�ʐς͊g�債�Ă��������Ƃ���ADID�̐l�����x�͌����������Ă��܂����i�}1-2-9�j�B
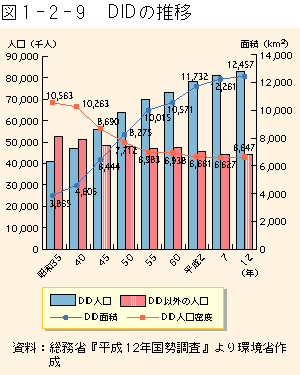
���̂悤�ɁA�킪���̓s�s�ł́A���̎��ӂɏZ��𒆐S�Ƃ���ᖧ�x�̎s�X�n���x�O�ɔ����L����u�s�s�̊g�U�v���i��ł��܂��BDID�̐l�����x�͋ߔN�����~�܂��Ă�����̂́A���ɒn���s�s�ł́A�ˑR�Ƃ��Ē��S�s�X�n����̐l�����o�������Ă���A�Ⴆ�A�x�R���x�R�s�ł́A�x�O�̐l���͑������Ă�����̂̒��S�s�X�n�l���͌����������Ă��܂��i�}1-2-10�j�B
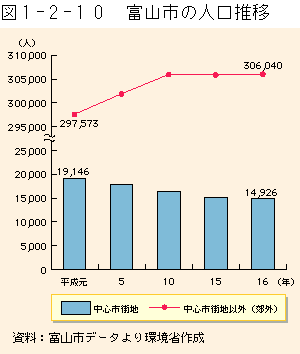
����ɁA���S�s�X�n�ɂ������s������a�@�Ȃǂ̌����{�݂��x�O�Ɉړ]���邱�Ƃ�A�o�C�p�X�����ȂǍx�O�ł̑�K�͏��Ǝ{�݂̐V�K���n���A�s�s�̊g�U��i�߂Ă��܂��B
�s�s�̊g�U���i�ޓs�s�ł́A���S�s�X�n��n��R�~���j�e�B�̐��ށA�ƍ߂̑����ȂǁA���܂��܂Ȗ�肪�������Ă���A�Ⴆ�A�R�~���j�e�B�ɂ��ẮA���S���̐l�����o��x�O���Z�ɂ��A�s�s�����҂̒n���W��������̓I����ɂȂ��Ă��Ă��܂��B
���̂悤�Ȗ��ɉ����A�s�s�̊g�U�́A���ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ��܂��B
�i�P�j�s�s�\���Ɗ�����
�킪���̉^�A���傩��̓�_���Y�f�r�o�ʂ́A����16�N�x�i2004�N�x�j�ɂ����ĂQ��6,200���g���i���r�o�ʂ�20.4���j�ƂȂ��Ă���A1990�N���20.3�����������Ă��܂��B���̂����A���Ɏ��Ɨp�����Ԃ���̔r�o�ʂ�1990�N���50�����������Ă���A�^�A����̖����߂Ă��܂��B
����30�N�ԂŁA�����ԕۗL�䐔�͖�7,700����Ɩ�S�{�A�^�]�Ƌ��ۗL�Ґ��͖�7,900���l�Ɩ�Q�{�ɒ����������܂����B����́A���[�^���[�[�V�����̐i�W�ɔ����k���������ʂ��ւ��������ł͂Ȃ��A�s�s�̊g�U�ƂƂ��ɍL��I�Ȉړ����K�v�ɂȂ�ɂ�āA���ł��ǂ��ւł��ړ��ł���֗��ȏ�蕨�ł��鎩���Ԃ��̑��Ƃ��ė��p���邱�Ƃ��K�v�s���ƂȂ������Ƃ��傫�ȗv���ł���ƍl�����܂��B
DID�l�����x�Ǝ����Ԉˑ����E�^�A���q����̓�_���Y�f�r�o�ʂ̊W������ƁADID�l�����x���Ⴂ�s�s�i�g�U�X���������s�s�j�قǂ��̓s�s�ɋ��Z����Z���̎����Ԉˑ����������Ȃ��Ă���A�܂��ADID�l�����x���Ⴂ�s�s�قlj^�A���q����̏Z���P�l������̓�_���Y�f�r�o�ʂ������Ȃ��Ă��邱�Ƃ�������܂��i�}1-2-11�A�}1-2-12�j�B
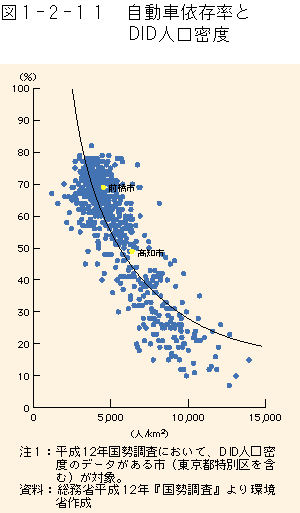
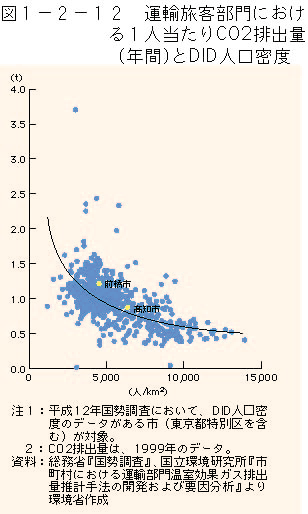
�ȏ�̂��Ƃ��A�ʐςƐl�����قړ����K�͂ł���O���s�ƍ��m�s���Ɍ���ƁA�ᖧ�x�̎s�X�n���L�����Ă���O���s�ł́A�����Ԃ̈ˑ����������Ȃ��Ă��܂��B���̌��ʁA�^�A���q����̂P�l������N�ԓ�_���Y�f�r�o�ʂ��r����ƁA���m�s��0.87�g���ɑ��A�O���s�ł�1.21�g���ƁA��S�������Ȃ��Ă��܂��i�\1-2-2�A�}1-2-13�j�B

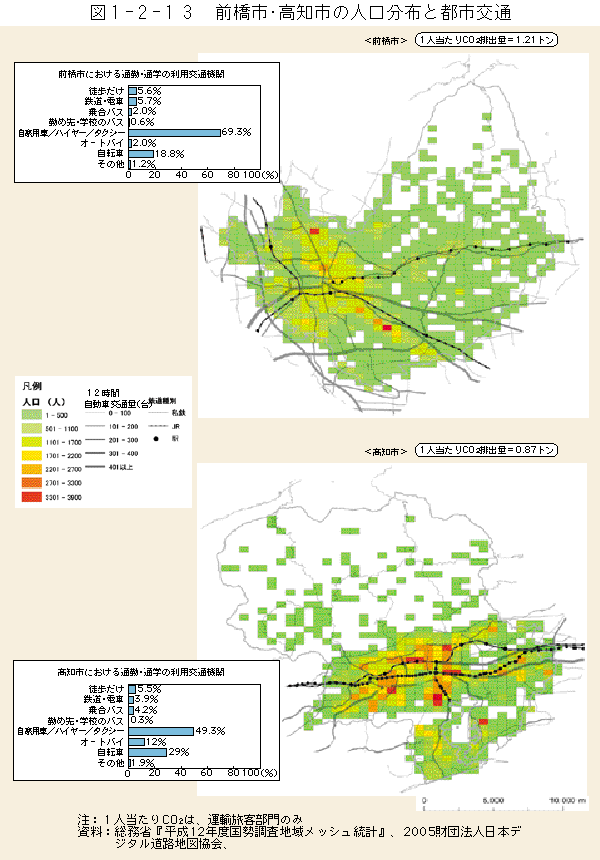
���O���s�F�����Ԉˑ��^�s�s��
�������H�ł��鍑���ɂ͂��ĘH�ʓd�Ԃ������Ă��܂������A�����Ԍ�ʂւ̎x�ᓙ�����O���ꂽ���߁A1950�N��ɔp�~����܂����B���H�Ԃ��c���ɒ��菄�炳��A�o�C�p�X���H�����Ȃǂ̍x�O�ɋ��Z�n�悪�g�債�Ă���A��^���Ǝ{�݂����n���i��ł��܂��B���S�s�X�n�ւ̐l���W�ς͂قƂ�nj���ꂸ�A�l�����x�̒Ⴂ�n�悪�L���͈͂ɂ킽���Ċg�U���Ă��܂��B
�����m�s�F���S���W��^�s�s��
�s�X�n���S����H�ʓd�Ԃ�������k�Ɋт��Ă��܂��B�܂��A��v�ȓ��H�Ԃ́A���������̎厲�ł��鍑���S�{�ƁA����ɓ�k��������ڑ����錧���ō\������A�s�X�n���S���Ɋ������H���W������`�ԂƂȂ��Ă��܂��B�s�̖k���͎R�Ԓn�ŁA�Z��n�͎s�̓암�ɏW�����Ă��܂��B���S���ɂ͈ˑR�Ƃ��Đl���W�ς������܂����A�l���̌����͑����Ă��܂��B����ŁA�x�O�̐l���͑������Ă��܂��B�s�̐����ɂ͏Z��n���`������A������ʂ鍑���͎s���ōł���ʗʂ̑����H���̈�ƂȂ��Ă��܂��B
�O���s�ƍ��m�s�̒ʋE�ʊw���̗��p��ʋ@�ւ����Ă݂�ƁA�O���s�ł́A���Ɨp�Ԃ̗��p�������Ȃ��Ă��܂����A����́A�s�X�n�̊g�U�E�L�扻�ɂ��ړ������������Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����ƍl�����܂��B����A���m�s�ł́A�O���s�Ɣ�r���Ď����Ԃ̗��p���Ⴍ�A�I�[�g�o�C�E���]�ԗ��p�̊����������Ȃ��Ă��܂����A����́A�s�s�@�\�̂���s�X�n���S���ƏZ��n�����אڂ��Ă��邽�߂ƍl�����܂��B
�i�Q�j������ʋ@�ւ̏k���Ɗ����ׂ̑���
���[�^���[�[�V�����A�s�s�̊g�U����w�i�Ƃ��������Ԉˑ����̍��܂�𗝗R�Ɍ�����ʋ@�ւ̗��p�҂͋ߔN�������Ă���A����A�l���������i�ނ��Ƃɂ��]���̂悤�Ȍ�����ʋ@�֖Ԃ��ێ��ł��Ȃ��Ȃ����ꍇ�A����Ɏ����Ԉˑ��������܂�Ƃ��������z�����O����܂��B
�l���P�l�^�ԂƂ��ɔr�o�����_���Y�f�̗ʁi�l�|�L��������j����蕨���Ƃɔ�r����ƁA�����Ԃ́A�S���̖�9.1�{�A�c�Ɨp�o�X�̖�3.2�{�̓�_���Y�f��������������̒Ⴂ��蕨�ł��B����A������ʋ@�ւ��k�����A�����Ԉˑ������܂邱�Ƃɂ��A�����ׂ����傷�邱�Ƃ��뜜����܂��B�Ⴆ�A�n���S�Ɣ�r���Ĉ����ɐ������邱�Ƃ��ł��A�n���s�s�̐l���K�͂ł��L���ȗA���@�ւƂȂ�H�ʓd�Ԃ�p�~�����s�s�Ƒ������Ă���s�s�̓�_���Y�f�r�o�ʂ����Ă݂�ƁA�H�ʓd�Ԃ�p�~�����s�s�́A�������Ă���s�s�ɔ�ׁA�����ԗ��p�����܂錋�ʁA�^�A���q����̂P�l�������_���Y�f�r�o�ʂ����ς��Ė�15�������Ȃ��Ă��܂��i�}1-2-14�j�B�܂��A�H�ʓd�Ԃ𑶑������s�s�́A�p�~�����s�s�ɔ��DID�̐l�����x����20�������A�H�ʓd�Ԃ��s�s�̊g�U��h�~�����ň��̖������ʂ������ƍl�����܂��B
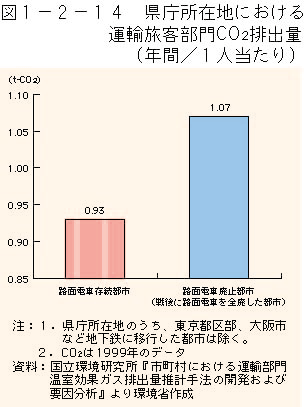
�Ȃ��A����҂���l�ŗ��p�ł���O�o��i�����Ă݂�ƁA�o�X�A�d�Ԃ̊����������A�����Ԃ͔N������Ȃ�ɂ��������āA���̗��p���������������Ă��܂��B���̂��߁A������ʋ@�ւ����ނ��邱�ƂŁA�����̌�ʎ�҂����܂�邨���������܂��i�}1-2-15�j�B
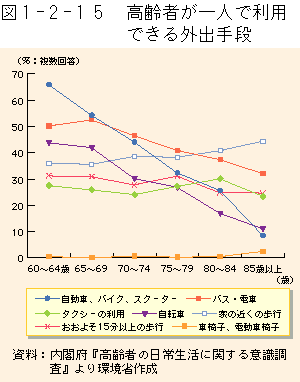
�R�����@�����Ԍ�ʂ�CO2�r�o��
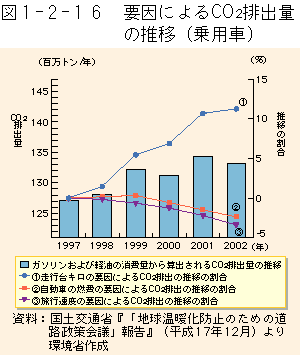
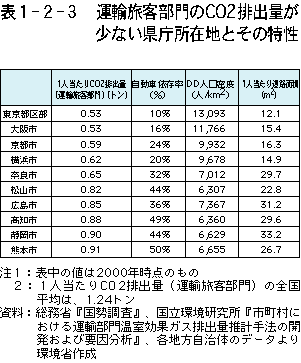
�����Ԍ�ʂ����CO2�r�o�ʂ́A��ɁA1)���s�ʁi��L���j�A2)�P�䂲�Ƃ̔R��A3)���s���x�̂R�̗v���ɂ�茈�肳��܂��B1997�N��2002�N�̊Ԃł́A�����ԁi��p�ԁ{�ݕ��ԁj�����CO2�r�o�ʂ͂Q���������܂������A��p�Ԃ݂̂����CO2�r�o�ʂ͂T���������܂����B���̗v��������ƁACO2�̑����v���ł����p�Ԃ̑��s�ʁi��L���j��11���������A�����ŁACO2�̌����v���ł����p�ԂP�䓖����̔R��Ƒ��s���x�͂��ꂼ��R���A�Q�����P���܂����i�}1-2-16�j�B���ꂩ�番���邱�Ƃ́ACO2�����炵�Ă�����ł́A�����Ԃ̔R��K���̋������邢�̓G�R�h���C�u�Ȃǂɉ����A���s�ʂ��팸����ƂƂ��ɁA���s���x�����シ�邱�Ƃ��d�v���Ƃ������Ƃł��B
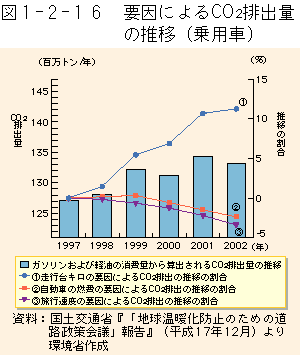
�Ƃ���ŁA���s��L���Ƒ��s���x�̂Q�̗v���ɂ͓s�s�\�����[���W����Ă��܂��B�s�s�\���̂����A�Ⴆ�A���H�Ԃ�����ƁA�����I�ȓ��H�����ɂ��A�a���ɘa����邱�ƂŎ����Ԃ̑��s���x�����シ��ACO2�̔r�o�͌������܂����A�����A���H�������A�V���Ȏ����ԑ��s��U�����邱�Ƃ�����A���H������CO2�r�o�ʂɂ͐��E�����ʂ̊W������܂��B
�U������鎩���ԑ��s�̑召�ɂ́A��ւ̌�ʋ@�ւ̐����A���ӂ̓y�n���p�A���H�l�b�g���[�N�̌`��A���X�̓��H�̏a�E���G��ԂȂǂ��e������Ƃ����Ă��܂��B
�Ⴆ�A�������ݓs�s�i�\1-2-3�j���r���Ă݂�ƁA�P�l������̉^�A���q����CO2�r�o�ʂ���r�I���Ȃ��s�s�́A���s�⋞�s�s�̂悤�Ɏs�X�n�������x�ɏW�ς��Ă��邱�Ƃ�A���R�s�⍂�m�s�̂悤�ɘH�ʓd�Ԃ����邱�ƂŌ�����ʋ@�ւ̉ʂ����������傫�������Ԉˑ������Ⴂ�A�n��̎����Ԍ�ʎ��v�ɑΉ����Ă������H�̖ʐς��n��̐l���ɔ�ׂď������s�s�\���ƂȂ��Ă��܂��B
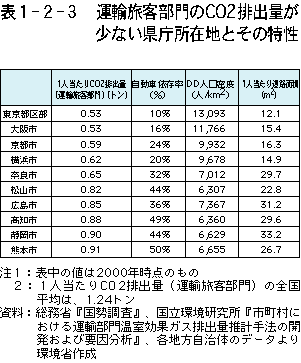
�����܂���ƁA�����Ԍ�ʂɔ���CO2�r�o�ʂ����炵�Ă�����ł́A���H����ʋ@�ւ̐����A�s�X�n�̊g��}���ɌW��y�n���p�s���Ȃǂ������ɑg�ݍ��킹�Đi�߂Ă������Ƃ��d�v���Ƃ����܂��B
�i�R�j�s�s�\���ƍs���R�X�g
�s�s�\���͍s���R�X�g�ɂ��e����^���܂��B�l�����x�ƍs���R�X�g�̊W������ƁA�l�����x���Ⴍ�Ȃ�قǁA�P�l������̍s���R�X�g�������Ȃ�X��������܂��i�}1-2-17�j�B
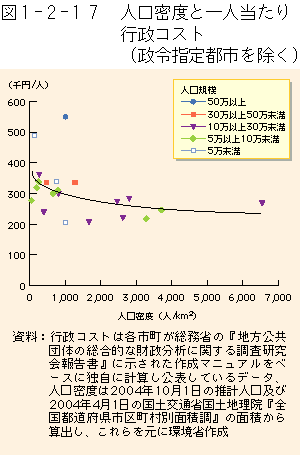
���ɁA�������̐����₲�݂̎��W�Ƃ��������Ɋ֘A���鎖�Ƃɂ��Ă��A�n�������c�̂��Ƃɔ�r����ƁA�l�����x�̒Ⴂ�n�������c�̂ł͂P�l������̔�p�ɂ͑傫�Ȃ��������܂����A�l�����x�������Ȃ�قǁA�P�l������̔�p�������Ȃ�X���������A�W��̃R�X�g�����b�g�������Ă��邱�Ƃ�������܂��i�}1-2-18�A�}1-2-19�j�B
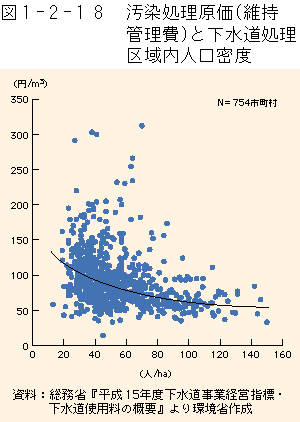
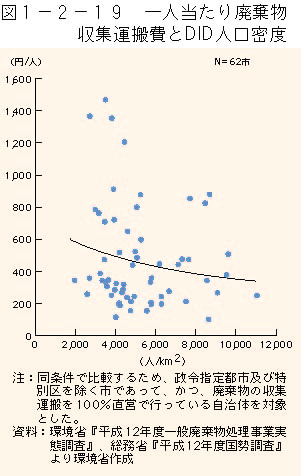
�����āA�l�������⏭�q����ɔ����A�킪���̓����]�͂͋}���ɒቺ���邱�Ƃ������܂�Ă��܂��B���̂悤�Ȓ��A���x�������ȍ~�Ɍ��z���ꂽ�Љ��Վ{�݂�j���[�^�E�����͂��߂Ƃ��錚�z�����z��30�N�`40�N���o�߂��čX�V�������}���邱�Ƃ���A����A��ʂ̔p�������������邱�Ƃ��\������Ă��܂��B
���z������̔p���ʂ́A2030�N�ɂ͂P��2,000���g���ɏ��A���̎��ɗv����Љ�I��p�͊T�Z�łP��3,000���~�ƂȂ邱�Ƃ����Z����܂��B�܂��A�y�؍\��������̔p���ʂ͓������P��5,000���g���A���̎��ɗv����Љ�I��p�͂P��3,000���~��v���邱�Ƃ����Z����܂��i�}1-2-20�j�B
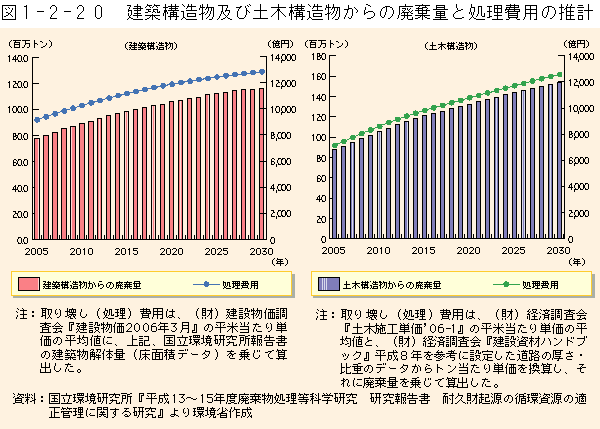
�i�S�j���ꂩ��̓s�s�̂����
�s�s�̊g�U�ɂ��A���������̒ቺ��s���R�X�g�̑�����͂��߂��܂��܂Ȗ�肪�����Ă���A�����̖��͐l�������ɔ�������ɐ[�������邨���ꂪ����܂��B
�s�s�̊g�U��h����g���n�܂��Ă��܂��B�Ⴆ�A�X���X�s�ł́A�s�X�n�̊g��ɔ����A�����ȂǑ��z�̍s��������]�V�Ȃ����ꂽ���Ƃ��_�@�ɁA�x�O�̃X�v���[�����⒆�S�s�X�n�̋���H���~�߂邽�߁A����11�N�ɃR���p�N�g�V�e�B�̌`������{���O�Ɍf�����X�s�s�s�v��}�X�^�[�v���������肵�A�]�[���K���ɂ���čx�O�J����}�������s�s������i�߂Ă��܂��B
�܂��A�s�s�@�\�̏W�ς̑��i�ȂLjӗ~�̂���n��ւ̎x������ʂ����u���킢�̊j�v�Â����X�Ȃ����Z�̑��i�ɂ�蒆�S�s�X�n�̊�������}�邽�߁A���S�s�X�n�ɂ�����s�X�n�̐������P�y�я��Ɠ��̊������̈�̓I���i�Ɋւ���@���̉����Ă��A����ɁA�l�������E������Љ���}���钆�A��K�͏W�q�{�݂�������v�{�ݓ��̍L��I�s�s�@�\�̓K�����n��}��A����҂��܂ޑ����̐l�X�ɂƂ��ĕ�炵�₷���R���p�N�g�Ȃ܂��Â�����������邽�߁A�s�s�v��@���̉����Ă��A���ꂼ�ꍡ����ɒ�o����܂����B
���̂悤�ɁA����́A�l���K�͂ɂ����������K�ȓs�s�\���ɍĕ҂��邱�Ƃ��d�v�ƂȂ�܂��B���̂��߁A�s�s�@�\�̖������Ȋg�U�Ɏ��~�߂������A�n��̎���ɉ����āA�s�s�̍x�O�J���̗}����s�s�̒��S���ւ̓s�s�@�\�̏W�ρE���i�Ƃ������R���p�N�g�Ȃ܂��Â���Ɍ�������g�𐄐i���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�܂����A�s�s�\���̍ĕ҂ɓ������ẮA�n�����g�����p������̊ϓ_�����łȂ��A�ȉ��̊��ʂւ̉e���ɂ����킹�ė��ӂ���K�v������܂��B
�A�@���R�Đ��̎�g
����܂łɔ_�n�A�ђn�Ƃ������_�ыƓI�y�n���p����H��A�Z��n�Ƃ������s�s�I�y�n���p�ւ̓]���ɂ��s�s�̊g�U���i�݁A�����̎��R���������Ă��܂����B
����A�s�s�̍x�O�J���̗}����s�s�̒��S���ւ̓s�s�@�\�̏W�ρE���i�ȂǓs�s�\���̍ĕ҂ɓ������ăR���p�N�g�Ȃ܂��Â����i�߂�ꍇ�ɂ́A�n��ɂ����鎩�R����芪�����悭���܂��A���R���̕����E�Đ��Ɍ�������g��i�߂Ă����K�v������܂��B
�C�@�y�뉘���̑�
�s�X�n�̍ĊJ����s�S���̍H��Ւn�̏Z��n�Ȃǂւ̓]�������_�@�Ƃ��āA�y�뉘�����������錏�����ߔN�������Ă��܂��B������������̓y�n���p������ƁA�H��E���Əꂩ��Z��n�ɓ]������Ă��鎖��������Ă��܂��i�}1-2-21�j�B
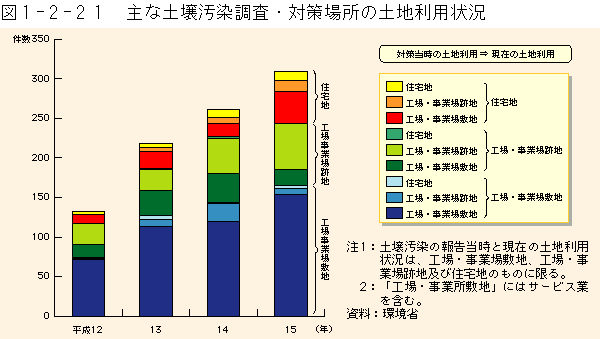
����A�H��Ւn���Z��n���֓]�������ɂ�A�y�뉘��������Ɍ��݉����邱�Ƃ����O����邱�Ƃ���A���o�ϓI�ō����I�ȓy�뉘���̒������𐄐i���邱�Ƃ����߂��܂��B
����ŁA�y�뉘�������炩�ɂȂ����Ƃ��̒n��̊W�҂ւ̐����̓���̌��O�Ȃǂ���y�뉘���̒�����v����y�n�̉��ς��������邱�Ƃɂ��A�L���ȓy�n���p�̖W���ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ��������O�������Ă��܂��B���̂��߁A�y�뉘���̏���������ł̓y�n���L�ғ��̕s���@���邽�߂̃��X�N�R�~���j�P�[�V������S���l�ނ̈琬�Ɗ��p���ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B
�E�@��ʌ��Q��
�s�s�\���̍ĕ҂��s���Ă����ꍇ�ɂ́A�n���s�s�ɔ�ׂ���s�s�n��ɂ������C�����̒��x�܂��Ȃ���Ȃ�܂���B�����ԂƊW�̐[����_�����f�iNO2�j�y�ѕ��V���q���iSPM�j�Ƃ�������C���������̑��������ƁA�ǒn�I�ɍ��Z�x�ɂȂ��Ă���n��̓����Ƃ��āA��ʗʂ��������Ƃ��^�ԍ��������������H�ɖʂ��Ă��邱�ƁA���ӂ̌������g�U��W����悤�ȕ��z�ł��邱�ƂȂǂ��������܂��B
���̂��߁A�����Ԃ̒���Q����i�߂A��C�������������n��ւ̌�ʏW����������邽�߂̎����Ԍ�ʂU���銲�����H�l�b�g���[�N�̐����������ʋ@�֊��p�ւ̃V�t�g�A���ԑ����̌�ʗ���A�����_�t�߂ł̃I�[�v���X�y�[�X�̊m�ۂɉ����A�X��⌚�z���̌`���ǒn�I�ɑ�C���̎��ɉe����^���邱�Ƃ�F�����A���܂��܂ȑ��g�ݍ��킹�Ē������I�ɓs�s�����i�߂邱�Ƃ��K�v�ł��B
�G�@�q�[�g�A�C�����h��
�s�s�`�Ԃ̉��P�ɓ������ẮA�Βn�̕ۑS��}��A�Βn�␅�ʂ���̕��̒ʂ蓹���m�ۂ��铙�̊ϓ_����A���Ɨ̃l�b�g���[�N�̌`���𐄐i����K�v������܂��B�Ⴆ�A�������S���ł́A�ċG�̓����ɂ����ĐV�h�s�X�n����33���ł��������ɁA�����_�{�̒��̎��ђn�́A��7.5���Ⴂ25.5���������Ă����Ƃ����f�[�^������܂��i�}1-2-22�j�B

�܂��A�s�s�̑�K�͗Βn�ł���V�h�䉑�̗�M���ʁi�N�[���A�C�����h���ʁj�����đ��肵���Ƃ���A�s�X�n�ɔ�ׂĕ��ϓI�ɂP���ȏ�C�����Ⴍ�A���̋C���ጸ���ʂ͎���100���[�g���͈̔͂ɋy�ԂƖ��炩�ɂȂ��Ă��܂��i�}1-2-23�j�B
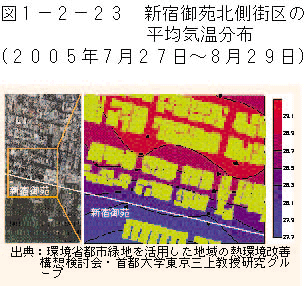
����ɁA�V�h�䉑�̎������ʂ܂��A���̂悤�ȑ�K�͗Βn�̎��ӊX��ɂ��āA��K�͗Βn����̗ǍD�Ȓʕ����̊m�ہA�������ւ̍ő���̗Ή��Ȃǂɂ��N�[���A�C�����h�̌��ʂ��ő�������o���悤�v�����ꍇ�A�n�\�ʂ����C�ɕ��o�����M��S�ʎŒn�������ꍇ�Ɠ����x�܂ŗ}���邱�Ƃ��ł���Ƃ��������Z��������Ă��܂��i�}1-2-24�j�B
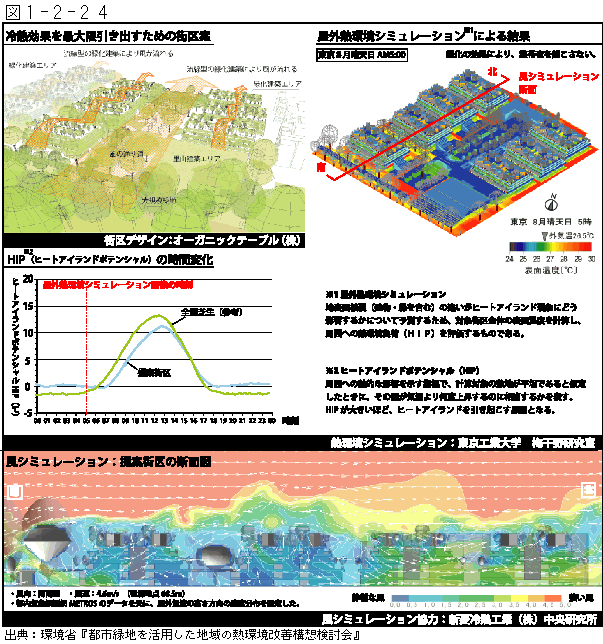
�����āA�R���p�N�g�Ŋ����ׂ̏��Ȃ��s�s�̍\�z�𐄐i����K�v������܂��B���g�߂ȂƂ���œ��퐶�����ł���悤�s�X�n���`�����邱�Ƃ́A�Ⴆ�A�����Ԍ�ʂɉߓx�Ɉˑ����Ȃ��G�l���M�[����̏��Ȃ���ʑ̌n�̎����A��g�[���̃G�l���M�[���p�̌������A�s�X�n���ӕ����ł̎��R��̉��\�ƂȂ�܂��B
�q�[�g�A�C�����h���ۂ́A�l�H�r�M�A�n�\�ʔ핢�A�s�s�\����n�`�E�C�ۏ����ȂǑ���ɂ킽��v���ɂ��`�������ȂǁA���J�j�Y�������G�ł��B������A���ʊW�̉𖾂⌻�ۂ̃��J�j�Y���A����ɂ͂��̉e���̕]���Ɋւ��钲��������i�߁A�����œ���ꂽ�ŐV�̉Ȋw�I�m����Z�p�̐i�W�ɍ��킹�đ���������Ă����K�v������܂��B
�l�������E������Љ���}���钆�ŁA�s�s�\���̍ĕ҂ɓ������ẮA�����Ԉˑ��^�̓s�s�\���������ׂ̑���ɂȂ��邱�Ƃ���A���ɒn���s�s�ɂ����ẮA�s�s�@�\�̊g�U��}�����A������ʃl�b�g���[�N�����Ƃ����A�s�s�J���̗��n��U�����Ă������Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B
����A��s�s�ɂ����ẮA�����x�Ȏs�X�n�̌`���Ɠs�S�����ɂ�����s�s�@�\�̏W�ςɂ���āA������ʃl�b�g���[�N���L���Ɋ��p����Ă��܂����A�����Ԍ�ʂ̓���I�ȏa��������ƂƂ��ɁA���ċl�܂��Βn�̌������������炷�����ꂪ����ق��A��ɏq�ׂ��q�[�g�A�C�����h���ۂ̂悤�ɁA�s�s�̊��Ɋւ���V���Ȗ�����\��������܂��B���̂悤�ɓs�s�@�\�̏W�ς�i�߂����ŁA�s�X�n�ɂ�������̈������ɘa���邱�Ƃɂ��Ă��ڂ�������K�v������܂��B
�s�s�S�̂̊��͗l�X�Ȏ��ۂ����G�ɉe�����y�ڂ������Ă��邱�Ƃ���A�������I�ɍl�����鎋�_�������ēs�s�S�̂̊����ׂ����債�Ȃ��悤�ɂ���ȂǁA�����ׂ̏����ȓs�s�̍\�z��i�߂Ă����K�v������܂��B
����̓s�s�`���ɓ������ẮA�ȏ�̂悤�Ȋ��z��������ɓ���A���̓s�s�̗��j�╶���Ȃǒn�搫��y�n�����\���ɐ������A�l���W�܂葽�l�Ȋ������W�J�����u���K�ŋ��S�n���ǂ��A����������Ȃ���A�������܂��Â���v���s���E�s������̂ƂȂ��Đi�߂Ă����K�v������܂��B
�R�����@�V�������L���O�E�|���V�[

�h�C�c�̃t�����N�t���g�s�́A�E�����߂Ă̘J���͂̈ړ��A�o�����̒ቺ�Ȃǂɂ��}���ɐl���������i�݂܂����B���̌��ʁA���S�s�X�n�ł͋Ƃ��������A�܂��S�̂̊T�ς˂���肩�A�s�s�C���t����Y�ƒn�т̗��p�̕ω��Ȃǂ̂��܂��܂Ȗ�肪�������܂����B����������ߊς��邱�ƂȂ��A��D�̃`�����X�ƂƂ炦�A�Ƃ̉�́A�P���A����ɂ͏Z��̓P����̓y�n��Βn��X�тȂǂ̎��R�ɖ߂��Ƃ�������g��ϋɓI�ɍs���A�u�V�������L���O�E�|���V�[�i�n���I�k������j�v�Ɋ�Â�����Ƃ肠��܂��Â��肪�i�߂��Ă��܂��B���R�Ƌ������邱�Ƃň��S�Ɣ������Ƃ�Ƃ�����߂��A�܂������̍������͓I�ȋ�Ԃւƕς��Ă������ʂ����҂���Ă��܂��B
