第3節 京都議定書の問いかけ
1 条約の究極の目的に向けて
条約は、「気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させること」を究極の目的としています。そして、安定化の水準は、「生態系が気候変動に自然に適応し、食料の生産が脅かされず、かつ、経済開発が持続可能な態様で進行することができるような期間内で達成されるべき」としています。
(1)温室効果ガス濃度を安定化させる
大気中の温室効果ガス濃度の安定化とは、大気中に排出される温室効果ガスの量と、海洋や陸上生態系によって吸収される量とが平衡することによって、大気中の温室効果ガスの濃度が一定の状態に保たれることをいいます。現在、化石燃料の燃焼などの人の活動に伴って、年間約63億トン(炭素換算)の二酸化炭素が排出されていますが、地球の純吸収量(自然由来の排出量を差し引いた自然吸収量)は約31億トンと推計されており、年間約32億トンが大気中に蓄積されて、濃度が上昇し続けています(図1-3-1)。
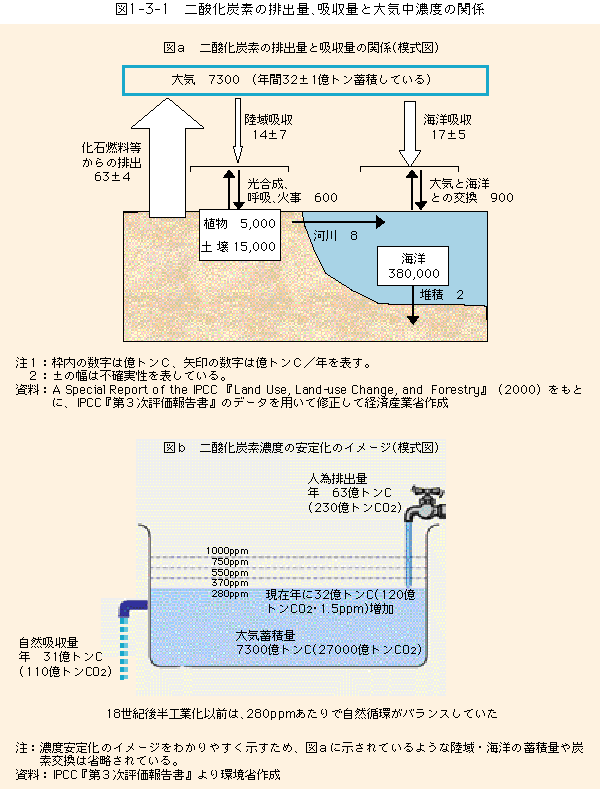
大気中の温室効果ガス濃度がどの程度の水準で安定化するかは、安定化するまでの温室効果ガスの累積の排出量によって決まります。今後、温室効果ガスの増加が続いた場合、どの程度の温暖化がどの程度の確率で生じ、それによりどのような影響が生じるのかを科学的に評価し、いつまでにどれだけ削減するのかを政策的に決定しなければなりません。
(2)さらに大幅な削減が必要
温室効果ガス濃度の安定化水準に関しては、いまだ国際的な合意が形成されていませんが、IPCC第3次評価報告書では二酸化炭素の450、550、650、750、1000ppmの5つの濃度を例として安定化にいたる排出パスを推計するとともに、二酸化炭素排出量や濃度、気温上昇の関係などを予測しています(表1-3-1)。

これらの推計によると、いずれの濃度で安定化を図るにしても、今後、二酸化炭素排出量の大幅な削減(50〜80%)が必要となります(図1-3-2)。
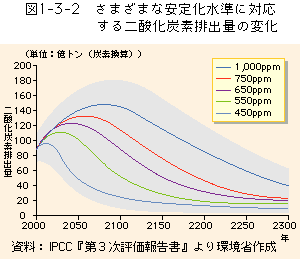
今後、二酸化炭素の排出量を大幅に削減したとしても、直ちに二酸化炭素濃度や気温、海面上昇が安定化するわけではなく、百年から数千年もの時間的なずれが生じます(図1-3-3)。
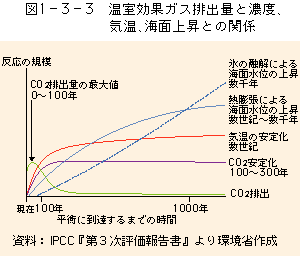
京都議定書の第1約束期間は2012年(平成24年)までですが、温室効果ガスの排出量と、地球温暖化の影響との間の時間的なずれを考慮すると、第1約束期間以降の国際的な枠組みについて、直ちに検討していく必要があります。
削減対策が遅れた場合、同じ温度目標を達成するためには、後からより大きな対策を取る必要があり、5年の遅れでさえ大きな違いをもたらすことが複数のモデルにより示され、また、排出削減対策が20年遅れた場合、その後、必要となる削減速度が3〜7倍になる可能性も指摘されました。
2 京都議定書の先へ
(1)次の枠組みに関する議論が始まっている
大気中の温室効果ガス濃度の安定化のためには、京都議定書の第1約束期間以降も、さらに長期的、継続的な温室効果ガス排出量の削減が必要になります。
2004年(平成16年)12月にブエノスアイレスで開催された条約の第10回締約国会議(COP10)では、中長期的な地球温暖化対策に向けた議論が行われました。さらに、先進国と途上国との信頼関係を築く上で、途上国の関心が高い「適応策」については、途上国への資金支援や人材育成支援を内容とする「適応策と対応措置に関するブエノスアイレス作業計画」が採択されました。
2005年(平成17年)5月にはCOP10で開催が決まった「政府専門家セミナー」が開催され、中長期的な将来の行動に向けて、効果的で適切な対策を展開していくための行動について情報交換が行われました。
(2)中長期的な観点からの取組の必要性
条約の究極目標である温室効果ガス濃度の安定化のためには、京都議定書のような短期的な数値目標の達成に向けた対策に限らず、中長期的な観点から対策を講じることが必要となります。
究極目標の達成のために、どのレベルの濃度の安定化が必要なのか、どのタイミングで世界全体の温室効果ガス排出量を減少方向に転換させなくてはならないのか、そのときの総排出量はどの程度にすればよいのか、という点について、科学的な知見の充実を含め、積極的に検討していく必要があります。また、温暖化問題の特質を踏まえれば、意識の変革、社会システムの変革、技術の開発・普及・投資などに取り組むとともに、中長期的な観点からどのような姿の社会をつくっていくか検討し、対策を講じていく必要があります。
|
コラム EUにおける長期目標の設定
EUでは、長期的な観点から、1996年(平成8年)には既に「産業革命以前のレベルから気温が2℃以上上昇しないようにする」という目標に合意しており、平成17年3月の欧州理事会でもその旨が確認されました。また、EU各国でも具体的な長期目標を掲げる動きがあります(表1-3-2)。 |
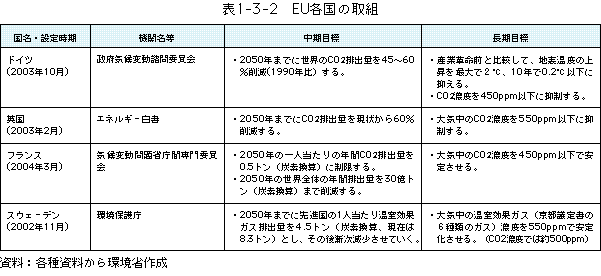
3 次の枠組みの姿は
京都議定書は、数値約束の差異化や吸収源の扱いなど、各国のさまざまな主張を取り入れた枠組みとなっています。京都議定書の第1約束期間の終了する2013年以降について、衡平で実効ある枠組み(いわゆる次期枠組み)を構築するため、条約における共通だが差異ある責任及び各国の能力に従い気候系を保護すべきという原則を踏まえつつ、米国や開発途上国を含むすべての国が参加する共通のルールを構築していくことが重要です。
(1)最大の排出国の参加が不可欠
現在、京都議定書に参加していない米国は、世界最大の温室効果ガス排出国であり、国際的な地球温暖化対策を実効性あるものとするためには、次の枠組みへの米国の参加が不可欠です(図1-3-4)。

米国では、州レベルで温室効果ガス削減目標の設定や排出量取引等を行い、企業レベルでも自主的に排出量の削減や排出量取引の実施に取り組むなどの動きがあります。連邦政府の政策を含め、米国の動きに今後も注目していく必要があります。
(2)開発途上国の具体的努力が必要
これまでの世界の温室効果ガス排出量は、先進国からの排出が多くを占めていましたが、今後、2010年にも開発途上国の排出量が先進国を上回る見込みです(図1-3-5)。

開発途上国における1人当たりの排出量は先進国と比較して依然として少ないこと(図1-3-4参照)、過去及び現在における世界全体の温室効果ガス排出量の最大の部分を占めるのは先進国から排出されたものであること、各国における地球温暖化対策をめぐる状況や対応能力には差異があることなどから、先進国が開発途上国の対策を協力・支援することが必要です。そこで、開発途上国では、クリーン開発メカニズムにより先進国の支援を受け、相互の信頼関係を築きながら、温室効果ガス排出量を削減する動きがあります。また、国全体の排出量はすでに相当程度大きく、今後もさらに排出量の増加が見込まれる開発途上国については、排出量削減に向けた一層の努力が必要になるとの認識が広がりつつあります。実効性のある温暖化対策を進めるためには、次の枠組みにおいて開発途上国における実質的な排出抑制が行われるような仕組みが必要です。
4 脱温暖化社会に挑戦する日本
大気中の温室効果ガス濃度の安定化という条約の究極の目的達成に向けて、世界は、今後、その排出量を長期的、継続的に削減していく必要があります。その中で、日本は率先して、温室効果ガスの排出が少ない社会、すなわち脱温暖化社会を構築していかなければなりません。
温室効果ガスの排出はあらゆる主体のあらゆる活動に関わっているため、その削減対策の選択肢はさまざまです。例えば、既存の技術で削減を図るよりも、将来、革新的技術が進展した後に急激に削減させる方が効率的という考え方があります。しかし、温暖化の進行に伴う被害や対策費の増加、技術開発の不確実性や技術普及の難しさなども考慮すれば、それだけに期待することはできません。一方で、生活の豊かさや利便性を制約して、人間活動が環境に大きな影響を与えていなかった時代に戻るかのような社会のあり方は、人々の理解を得ることができないでしょう。今、私たちは、あらゆる主体の参加によって、また多様な社会システムや制度を組み合わせて温暖化対策を進めていく必要があります
私たちが築くべき脱温暖化社会とは具体的にどのようなものなのか、長きにわたる挑戦の目指す先が、今、問われています