

|
|
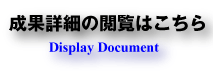 (9.2Mb)
(9.2Mb)
|
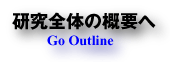
|
独立行政法人産業技術総合研究所 |
||
環境管理研究部門 |
副部門長 |
山本晋 |
環境管理研究部門 |
大気環境評価研究グループ |
近藤裕昭・蒲生稔・村山昌平・三枝信子 |
環境管理研究部門 |
地球環境評価研究グループ |
兼保直樹 |
環境管理研究部門 |
域間環境評価研究グループ |
前田高尚 |
独立行政法人農業環境技術研究所 |
||
地球環境部フラックス変動評価チーム |
宮田明・原薗芳信・永井秀幸・山由智康・吉越恆・ |
|
Gwang Hyun Han・Md. A. Baten・小野圭介 |
||
独立行政法人森林総合研究所 |
||
気象環境研究領域 |
気象研究室 |
大谷義一・溝口康子・渡辺力・安田幸生 |
学振科学技術特別研究員 |
戸田求(現北海道大学) |
|
森林環境部 |
樹木生理研究室 |
石田厚 |
森林総合研究所関西支所 |
森林環境研究グループ |
玉井幸治 |
独立行政法人農業技術研究機構九州沖縄農業研究センター |
||
環境資源研究部気象特性研究室 |
大場和彦・黒瀬義孝・丸山篤志・中本恭子 |
|
山梨県環境科学研究所 |
植物生態学研究室 |
中野隆志・大塚俊之(現茨城大学)・安部良子・ |
渡辺美紀 |
||
筑波大学生物科学系 |
鞠子茂 |
|
筑波大学大学院地球科学系 |
田瀬則雄・濱田洋平 |
|
千葉大学環境リモートセンシングセンター |
西尾文彦 |
|
岡山大学環境理工学部 |
大滝英治・岩田徹・三浦健志 |
|
京都大学農学研究科 |
谷誠・小杉緑子 |
|
大阪府立大学農学部 |
文字信貴 |
|
九州大学大学院農学研究院 |
真木太一・杉浦裕義・平田竜一・鈴木義則・柳博 |
|
〈研究協力者〉 |
国際林業研究センター |
藤間剛 |
平成12〜14年度合計予算額 122,264千円
(うち、平成14年度予算額 40,522千円)
本研究による観測はアジアフラックスネットワークの確立による東アジア生態系の炭素固定量把握を目的として展開されている観測網の一環を成すものである。ここでは東アシアモンスーン気候帯の各種生態系において7種類のフラックス観測サイトを選定して、大気と植生間のCO2等交換量や気象の連続観測を実施した。各種生態系毎の炭素収支の特徴を把握し、気象条件の差異が各生態系と大気間の交換量に及ぼす影響、さらに、観測データの蓄積を図り、炭素循環過程の定量的解明を目指した。以下に各サイトにおける代表的な成果を述べる。
(高山落葉広葉樹林サイト)岐阜県高山市郊外の冷温帯落葉広葉樹林において、渦相関法による二酸化炭素・水蒸気・顕熱フラックス、気象条件などを長期連続測定している。8年間の年間NEPは平均224±82gCm-2であること、年によって100gCm-2以上の大きな違いがあることなどが分かった。二酸化炭素フラックスの年による違いの第1の要因は光合成有効放射が梅雨期、夏季の降水状態により年々変動すること、第2に展葉を開始する時期の違いである。葉面積指数(LAI)の観測結果に基づいて春季にLAIが増加を開始した日(LAIが1を超えた日)を比べると、展葉開始日は年によって20日程度変動していること等が分かった。
また、高山サイトでは、夜間および冬季の二酸化炭素フラックスは主に気温の関数、夏季の日中の二酸化炭素フラックスは光合成有効放射と気温の関数で表現できた。一方、二酸化炭素フラックスに対する土壌水分量と飽差の影響は明瞭ではない。このことは、高山サイトは年間降水量が多く(2000mm以上)湿潤な条件下にあることに関係すると考えられる。
高山サイトの年間のNEPを求める際、現在のところ最大の不確定要因は、夜間安定時の補正をどの程度行うかという事である。また、夜間の補正が年間NEE(Net Ecosystem CO2 Exchange)に大きな影響を及ぼすという結果は、複雑地形地でのフラックス観測の一つの特徴であり、年間NEEの値は慎重な取り扱いを必要とする点ではないかと考えられる。
(富士吉田アカマツ樹林サイト)山梨県富士吉田市富士山北麓のアカマツ林サイトにおいて、群落上のCO2フラックス、群落のエネルギー収支の評価を目的とした、森林微気象の通年観測を継続実施した。あわせて、森林群落炭素収支を見積もるための、土壌呼吸量の自動連続測定、生態系の成長量調査を行った。タワーフラックス観測で得られた年間のNEEの変動は大きく、変動幅は3年間で28%に達した。気温が高く生態系呼吸量の多い時期にどの程度の日射量が得られるか、冬季の休眠期間の有無と長短が、年間のCO2吸収量に大きく影響することが分かった。土壌呼吸量の連続測定から地温と土壌呼吸速度の関係が整理された。土壌呼吸量は夏季に大きく、その月積算値の最大値は130gCm-2y-1に達した。近似された指数関数の係数や土壌呼吸量の年積算値が、年によって大きく異なることが測定結果から示された。観測対象である森林群落の種組成が詳細に記述され、生態学的な成長量調査の結果から、積み上げ法による年間の純一次生産量が解析された。純一次生産量の年々変動は大きく、年々の樹木成長量、葉以外のリター量の相違が大きく影響することが分かった。リターフォール量、とりわけリタートラップでは捕捉できない大型のリターによる供給量測定の重要性が示された。
(桐生試験地ヒノキ樹林サイト)滋賀県南部の桐生水文試験地の観測サイト周辺はヒノキの閉鎖した樹冠をもつ森林で覆われている。京都大学チームが中心となって渦相関法による樹冠上フラックス測定を、大阪府立大学チームが中心となってREA(簡易渦集積)法によるCO2フラックス観測を行っている。CO2フラックスは、冬から初夏にかけては温度の増大ともに吸収量が増大するが、夏期には正味吸収量は低下した。湿潤な夏期における昼間の吸収速度のピークは初夏と変わらない値を示したが、夜間の呼吸速度が大きくなるために収支としての夏季の日積算炭素吸収量は減少した。また、潜熱フラックスの季節変動特性は概ね飽差の季節変動特性に従うが、乾燥時に飽差の増大から予測される程度に潜熱が増加しない期間もみられ、個葉の気孔開閉による調節が行われた結果、変動を生み出していると考えられた。
さらに本試験地では、従来から多く行われているように森林樹冠上フラックスをAPARや気温との単相関をみることによって解析するだけではなく、群落構造や個葉のガス交換特性、乱流拡散現象などを考慮した多層モデルを用いた解析を試みた。渦相関法による観測値と土壌呼吸・温度の関係および葉呼吸・温度の関係、および個葉ガス交換モデルを含む多層モデルによる見積もりの総合的解析から、乱流フラックス観測値による夜間のCO2放出が多層モデル等の値よりかなり小さく、渦相関法によるNEEが過大評価である可能性を示唆する結果となっている。
(釧路湿原サイト)北半球中緯度帯に位置する湿原と大気との間のCO2、メタン、エネルギー交換量の特徴を明らかにするため、北海道東部の釧路湿原を対象に観測を実施した。釧路湿原を代表するヨシの優占する湛水した低層湿原と、地表面にミズゴケ層が発達し、スゲが優占する高層湿原に観測点を設置し、渦相関法を用いてCO2、顕熱、潜熱の各フラックスを測定した。高層湿原観測点では、傾度法を適用してメタンフラックスも測定した。両観測点の植物成長時期の違いがNEEの季節変化にも顕著に現れ、低層湿原では消雪から6月にかけて生態系からのCO2放出が観測されたが、高層湿原では5月にNEEが放出から吸収に移行し、CO2を吸収する期間も5ヶ月間に及んだ。10月初めには、両観測点ともNEEが生態系からの放出または均衡へと移行した。2002年の高層湿原の年間積算NEEは約-200gCm-2で、水田(つくば)観測点とほぼ等しいと推定された。また、2002年の高層湿原からのメタンの年間総放出量は約13gCm-2で、炭素換算では年間NEEの6.3%に相当した。地球温暖化指数(GWP、積算期間100年)を考慮して評価すると、高層湿原は温室効果ガスの吸収源として作用してはいるが、メタン放出による温室効果ガス収支への寄与はCO2吸収の約1/2に相当する。
(水田つくばサイト)東アジアの代表的な農業生態系である水田の炭素収支を明らかにするため、茨城県つくば市の慣行栽培が行われている水田を対象に、3年間にわたり、CO2収支、メタン放出量、エネルギー収支の観測を実施し、溶存態炭素の収支や収穫物の搬出に伴う炭素フローを含めて、水田の炭素収支を評価した。NEEは水稲の成長に伴う顕著な季節変化を示し、移植から2〜3ヶ月後の6月下旬から8月初めにかけて吸収フラックスが最大となった(約10gCm-2d-1)。年間積算NEEは2001年が201gCm-2、2002年が91gCm-2の吸収と年次間差が大きかった。年次間差の主な要因は2002年の収穫時期の遅延による生態系呼吸量の増加と、2001年の収穫後のひこばえの成長と考えられた。水稲単作水田が大気中のCO2を吸収するのは約3ヶ月間で、残りの9ヶ月間は収支が均衡、またはCO2の放出であった。非耕作期間の生態系呼吸量は耕作期間の59%から80%に達した。水田の耕作期間を通じた溶存態炭素のフローは、収支がほぼ均衡していた。耕作期間のメタンの総放出量は5.4〜6.2gCm-2であり、年間の炭素収支を評価する場合には無視できる大きさであった。しかし、地球温暖化指数を用いてCO2に換算した場合、メタン放出量は42〜50gCm-2に相当し、NEEに比べて無視できない。不定期に行われる厩肥投入を除外すると、水田の年間炭素収支は100〜160gCm-2の流出と評価された。
(水田岡山サイト)本研究では、岡山大学農学部附属八浜農場で1998年12月から実施している渦相関法を用いた長期的観測に基づいて、(1)耕作地における熱および二酸化炭素フラックスの季節変化の実態解明、(2)水田での熱収支解析、という2つの課題に取り組んだ。顕熱フラックスは、2月から水稲の播種が行われる5月中旬にかけて急増し、水稲の生育期間から1月までは小さかった。潜熱フラックスは、水田が耕起される3月から6月にかけて大きな変動を示したが、水稲の成長が著しい7月から8月にかけて最大となり、その後は急減した。CO2フラックスは、播種1ヶ月後の6月下旬から下向き(水田による吸収)を示し、10月下旬の収穫期まで吸収炉継続した。収穫後のCO2フラックスは、地温の変化と対応した変動を示した。4年問平均の年間積算NEEは240gCm-2の吸収と推定された。
(暖地牧草地サイト)九州・沖縄地域は、我が国の主要な畜産基地であり、作物別作付割合は水稲の36%に続いて飼料作物が19%と2位である。そこで、農耕地での炭素循環を考える上で重要なトウモロコシ・イタリアンライグラス体系温暖牧草地生態系におけるCO2、エネルギーフラックスを測定し、その季節変動を解析した。さらにCO2吸収量積算値と収穫量乾物重の比較を行った。冬作のイタリアンライグラス畑では積算値が乾物重に対してわずかに少ない傾向がみられるが、収穫時期ではほぼ一致した。また、トウモロコシ畑では播種直後からほぼ一致しており、CO2吸収量と乾物量で一致は比較的良かった。最終的な温暖地畑生態系におけるフラックス法から求めた年間のCO2吸収量は1941gCO2m-2である。収穫法による年間の乾物重は2030gCO2m-2(5.54tonCha-1)である。両者による違いは欠測及び土壌呼吸量の補正を行っていないことなどによると考えられる。
(熱帯雨紳サイト)熱帯多雨林帯にある落葉熱帯季節林と常緑熱帯季節林のサイト、若齢二次林サイトの計3サイトで二酸化炭素収支観測を行なった。観測は渦相関法による二酸化炭素収支、熱収支測定と気象観測からなっている。また土壌呼吸をチャンバー法により測定した。
熱帯季節林の常緑林(タイ中東部サケラート)では、常緑ではあるが、生態系純交換量NEEは5-9月の雨季に大きく、12-4月の乾季に小さいという明瞭な季節変化がみられた。乾季と雨季の遷移期には光合成もそれほど下がらず、呼吸量は小さくなるため、NEEは大きい。年間のNEEは10tonCha-1yr-1と大きい結果になった。サケラートでは樹木調査が1985年より行われており、ほぼ成熟林であり、小さいNEEが期待されるが、大きなNEEとなった原因のひとつには、夜間弱風時には蓄積された二酸化炭素が水平移流で流出している可能性がある。NEEの風速の依存性を調べ、夜問のNEEは風速の大きいときの値をとるものとすると、NEEは6tonCha-1yr-1ほどまでに減少した。熱帯季節林の落葉林での観測はタイ中西部のメクロンで行っている。乾季雨季の季節パターンが葉面積指数LAIやNEEに明確に現れている。ここでは2002年のNEEは3.7tonCha-1yr-1であった。インドネシアのカリマンタン島ブキットスハルトの二次林の成長段階サイトで二酸化炭素収支の観測を行っている。このサイトでは1998年のエルニーニョに伴う異常乾燥による火災により二次林が消失し、その後5年にして高度10m近くまで復活してきている。毎木調査から求まる森林バイオマスの増加量から1次の純生産量NPPを求めた。さらに土壌呼吸量も考慮した総生産や生態系呼吸量など、この群落における炭素の分配状態を推定した。それによると、生態系純生産量はバイオマス増加量と似た値となった。
森林・湿原・農耕地生態系、アジアフラックス、渦相関法、炭素収支、生態系正味交換量